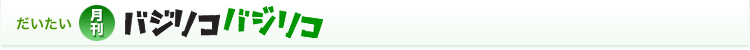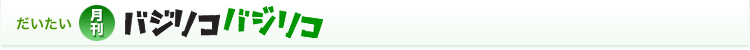俳優という仕事だけで生活ができるのは、ほんの一握りの人たちだけである。
それが氷山の一角であるとしたら、水面下には膨大な「食えない」俳優たちが存在している。
ただ、俳優「だけ」で食えない人たちがそのままアマチュアに分類されてしまうわけでもない。明らかにプロと呼ぶにふさわしい人たち、表現手段としての「演技」に心血を注ぎ、それが形として表れている人たちもいるからである。
大城英司という人も、そんな一人である。
彼が『金融腐食列島「呪縛」』(原田眞人監督)という映画に出たころ、知り合いを通して、こんな俳優がいると耳にした。この映画は第一勧業銀行の利益供与事件を扱った実録映画である。大城は初めは新聞記者役であったが、その後、テレビの報道記者役に変わった。知り合いを頼って新聞記者に取材をし、その後はNHKの報道記者にも取材をしたそうだ。主役級の俳優なら、それも分かる。労力を費やしても、相応の見返りがあるのだから。しかし、脇役、あるいは端役がそれをやっていては割が合わないだろう。
そうした過分な思い入れをもつ俳優がいることが、私には愉快でもあった。
その俳優が、今度は自らシナリオを書き、資金を捻出して、映画を撮った。
それもまた面白いではないか。
話を聞くために訪ねていった彼の自宅は、あの映画に映っていた「部屋」であった。
大城英司は一九六六(昭和四十一)年、長崎県諌早市に生まれた。
走るのが速かった大城少年は、中学二年のとき県大会の一五〇〇メートル走で優勝する。すぐに地元高校から勧誘され、鎮西学院という高校に特待生として入学した。入学試験も授業料も免除という待遇である。
将来は教師として長崎へ戻り、生徒を教えつつ、走りつづけるのが夢だった。
九州のある大学にスポーツ推薦枠で入学できる道筋も作られ、あとは秋に試験会場で一定のタイムで走ればいいだけだった。
ところが、その試験当日、大城は考えられないほど悪いタイムを出してしまう。調子が悪かったわけではない。高校最後の大会が終わった後だったため、つい油断したのかもしれなかった。大学への推薦入学はなくなってしまう。
目の前が真っ暗になった。夢が一気に崩れてしまった。
一週間ほど落ち込んだ後、急に自分の悩みが馬鹿げて見えた。陸上をつづけることも、教師になることも、自分で思い描いたレールである。他人に強制されたわけではない。ならば、今度は別のレールを作り、そちらに乗ればいいではないか。
突然、思いついたのが「俳優になろう」ということだった。松田優作演じる、『太陽にほえろ』のジーパン刑事が浮かんだ。
「なに言ってんだ、という話ですよ。教師にしてみれば、陸上部のキャプテンまでやっていた真面目な生徒が、急におかしくなった(笑)。でも、僕は真剣だったんです。だから、具体的にどうやったら俳優になれるかを模索しはじめたんです」
そんな大城にひとつの契機が訪れる。
当時、長崎県の雲仙に和太鼓の演奏グループ「鬼太鼓座」が拠点をもっていた。もともとは佐渡島からスタートしたが、メンバーの分裂を繰り返して、長野県に移り、さらに長崎へとやって来たのだ。
鬼太鼓座は、一九六九(昭和四十四)年結成時から「走る」ことと音楽とを結びつけようとしていた。七五(昭和五十)年には、メンバー全員がボストンマラソンに参加し、完走後に演奏するというパフォーマンスでデビューを果たしてもいる。
代表の田耕は、ここ雲仙で鬼太鼓座に陸上部を作るという構想をぶち上げた。やがては社会人の駅伝にも出場させる、と。
それで、地元の高校陸上部を回り、選手を集めていた。
「というのは方便であって、実はその直前にトラブルがあってメンバーの多くが脱退していたんです。ところが夏からはヨーロッパツアーが控えている。それで急造チームを作る必要があったわけ」
六人が集められたが、けっきょく大城も含めた三人が残り、さらに外部からドラマーを招聘して、この年の七月からヨーロッパツアーを敢行した。
ところが、公演一ヶ月目にして再び内紛が起き、外部参加のドラマーが帰国することになる。大城もまた田の方針に違和感を感じて仕方なかった。だから、ドラマーが帰国するというのに伴い、一緒に辞めることにした。
「たとえば木刀で太鼓を叩くとか、包丁でまな板を叩くとか。神秘性を持たせたかったのかもしれないけど、僕にはピントがずれているようにしか感じされなかった」
帰国した大城は、半年間の季節工のアルバイトで百五十万円を貯め、東京へと乗り出していくことになる。まだ、二十歳になる直前であった。
東京では俳優養成所に通ったり、小さな劇団に所属したり、アルバイトをしながら俳優修業に精を出した。
やがて芸能事務所にも入り、テレビドラマや映画、それにVシネマへの出演も果たすようになる。
二十八歳のときには結婚もした。
一九九七(平成九)年、ゴールデンタイムのドラマ『君が人生の時』(高島政伸主演)で初のレギュラー出演。清水美砂の夫役で、マザコンの暴力亭主という、かなり濃い役柄であった。二〇〇〇(平成十二)年には映画『ある探偵の憂鬱』(矢城潤一監督)で初主演も飾ることになる。
じっくりと役に取り組むせいだろう、それなりに評価はされる。だが、そこから俳優業を極めていくとはならなかった。
人を押しのけても、という我の強さがなかったせいだろうか。
しかし、今回の映画『ねこのひげ』は異なっていた。是か非でも作り上げたい、成功させたい。そう強く思っている。
なぜなら、この作品のモチーフは自らの離婚にあったからだ。映画とほぼ同じ状況が、大城の身にも降りかかっていた。
妻子と離れ、新しい結婚生活へと向かう。別れなくとも、あるいは別れても、いずれにしても悔いを抱えることになる。大城は別れて抱える後悔のほうを選択した。
映画が完成してから、やっと分かった。この作品を作り、成功させることで、初めて自分は先へと進んでいけるのだ、と。
映画製作のために借金とカンパで集めた五百万円はあっという間に使い果たした。
まだ公開時期や方法は決まっていないが、配給会社に委ねるとなると、さらに六百万円以上はかかることになる。
自主配給にして単館での公開にするか、それとも別の配給方法を考えるか。いまはまだ決めかねている。
今回の昼ドラマのように、声がかかれば出ないこともないが、いまは積極的に働きかけていくことはしない。頭の中は映画を宣伝して回ることで占められ、当分は鳶職が本業の状態である。
「昨夜も、横浜のほうの駅で仕事してきたんです。階段脇のタイル貼りのための足場を組む作業でした。階段に足場を組むのは難しいんですよ。フラットじゃないから、下駄を履かせるようにして、高さを調節していく。最初を組んだときに地面と水平じゃないと、どんどん歪んでいきますからね。これを終電の後にはじめて、タイル屋さんの作業が終わったら始発までにバラす」
高いところは怖くないというが、危険と背中合わせなのも確かである。建物の解体現場では、一歩間違うと数メートルの高さから落下するような怖さも味わった。
「心底怖いときは、踏み板に手をついて這って進みますよ。格好なんて気にしてられませんから」
鳶の仕事の面白さは何でしょう? そう問うと、即座にこういう答えが返ってきた。
「鳶という仕事は後に残らない。足場にしても建物ができるまでの物であって、建った後は壊してしまうわけです。でも、足場がないと他の作業はできない。だから、他の職人さんができるだけ作業をしやすい形で足場を組む。それがスムーズにいき、全体の仕事がうまくいくと、やはり嬉しいですね」
こうした段取り癖は、今回の映画製作にも役立ったという。
スタッフ、キャストが気持ちよく仕事ができるよう、隅々まで気を配る。そのことで良い作品が作り上げられるなら、たいした苦労だとは感じない。そのあたり、「人を押しのけても」という我の強さのない、俳優としての脆さが一気にプラスに転じたとも言えるのだ。
いずれかが主であり従であったとしても、二つの仕事が有機的に結びつく。世に無駄の二文字は存在しないのである。
それが、二足のワラジをはく面白さであるのかもしれない。 |
|