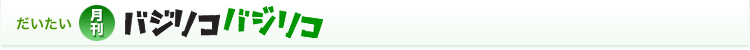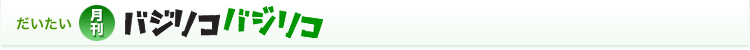「青森放送に入って、美術部に十年、CM部に三年、ラジオ制作に八年いて、二十一年目から局付という立場になったんです。報道制作局付とか営業局付とか、いろいろと動かされましてね。部に属さない、局長直属の部下。私には部下もいなければ、部会なんてのにも顔を出したこともない。仕事は、何でも屋です。あるスポンサーでCM作りたいからという特命があると、テレビなら絵コンテ描いて、ラジオならコピーを書いて。あるいは、スポンサーが三十周年のイベントやるから、余興で講演やってくれと言われれば、はいはいとそれも仕事になる。極めて曖昧な立場です。曖昧なまま定年まで来ちゃった(笑)」
どこまで忙しくなっても「会社を辞めるつもりはなかった」という。
「サラリーマンがやってるから喜んでもらえると思ってましたものね。プロとしてみたら詩だって朗読だって、たいした仕事ではない。たまにギターもって歌っても、ほとんど素人芸ですよ。喋りが上手いわけでもない。あくまで『サラリーマンなのに』と枕詞がついて、声がかかってたんです。あくまで趣味の範囲、その思い切り方が、逆に面白がられてたのかもしれない」
自分では、そう思っていても、周りもそう見るかどうかは別だろう。
上司、同僚にもいろいろな人がいる。かっぺいの活動を好意的に見てくれる人もいれば、否定的な人もいる。あからさまに「お前の活動は認めない」と告げた上司もいた。そんなときは、ただ頭を垂れて「はい、お説ごもっとも」と聞き流していた。
常にトップに近い立場の人が擁護してくれていて、それで何とか持ちこたえていたのだという。
「そりゃあ、陰で何を言ってるか分かりません。私も聞きたくないしね。それでも、洩れ聞こえてくることはあります。とてもとても順風満帆とは違いますよ。初めてNHKに呼ばれたときなんか、当時の局長から『なんでNHKなんかに出るんだ』って。『許さん』というわけ。どうしてですかと聞いたら、『お前が出ることで、もしも、みんながNHKを見たらどうする』だって。そんな理屈もあるのかと呆れました。みんながチャンネルを合わせるぐらい私に人気があるなら、うちの局で使えばいいじゃないですかと言ったけど、そんな理屈は通じない。そのときは、けっきょく出演を断ったのかな」
東京のテレビ等に出演した際、収録に費やした時間はすべて業務外になる。『かっぺい&アッコ……』は月に二回東京に行って二本ずつ撮ってくる。いつも有給休暇を使っていた。有給休暇がなくなれば、単なる欠勤となる。それも甘んじて受けねばならなかった。
仕事を終えてその足で東京に向かうことも多かった。
ラジオ制作に移ってからは、自ら何本か番組を抱えていたから、それもこなさねばならない。目の回るような忙しさだった。楽しいから引き受けていたのだが、疲れるのも確かだ。そんな状況を「気持ちにテーピング」と表現し、その疲れさえ面白がっていた。
テレビ出演や出版、レコードなどで得た収入はすべて自分の懐に入ってきた。
当然、最も忙しい時期の収入はかなり高額になった。ちょうど二十五年前、青森放送の年収の三倍を税金で払ったことがあった。青色申告も法人化も知らず、普通のサラリーマンの副収入として申告したせいだった。税金はとんでもない金額であり、どうやって払おうかと青くなった。
そのとき税務署から、個人事務所でも作って収入を管理したらどうですかと勧められた。翌年からさっそく事務所を立ち上げたのだが、この年ほどの忙しさは二度と訪れなかったと苦笑する。
周囲の人たちは、サラリーマンとしての嫉妬みたいなものもあったのではないですか、と尋ねると、しばしうつむいて考え、口を開いた。
「私が言うのもおかしいけど……あったでしょうね、きっと。私が有給休暇でNHKに出たからって、青森放送も、その上司も、あるいは同僚も、誰が損するってわけではない。勝手な思い込みかも知れませんが、むしろ、青森放送の宣伝になってるかもしれないでしょ。ある週刊誌が、『かっぺい&アッコ……』のときは数億円の宣伝効果があったと算出してましたけどね。何も諸手を挙げて送り出してくれというわけじゃなく、普通に、休みの日に旅行に行く程度に見てもらえれば……応援はしてくれなくて良いけど邪魔もしないでほしい、くらいで」
かっぺいの持論として、得意なものは二つ以上あったほうがいいという。二つあると、ひとつは職業に、もうひとつは趣味として生かせる。ひとつしかないと、それが職業になり、無趣味な仕事バカになってしまう。
得意なものが二つ以上あったほうが、人生も楽しい。
「得意だっていうのは、好きだってことだから。好きなことって学ぶのが楽しい。美術部時代、写植の打ち方を教わったり、ほんと、面白かったもの。いろんな方面に手を出して、そのことでバランスとっていくという仕事のやり方もあるんじゃないでしょうか」
仕事にしても暮らしにしても、「自分から辛いことや苦しいことをやる必要はない」と思っている。
「黙っていても悲しいことや苦しいことは向こうから来るんだから、積極的に何かやるときは楽しいこと以外はやらないよ、と」
そんな想いにつながる糸は……かっぺいは中学生のとき、骨髄炎で六ヶ月間の入院生活を余儀なくされている。一年生の三学期から二年生の二学期まで。三回の手術によって足が思うように動かなくなり、車椅子と松葉杖によって暮らしていた。
この骨髄炎で入院する直前、かっぺいが高熱を出して苦しんでいるときのことだ。
母親が死んだ。
長らくガンで入院した末の死だった。しかし、かっぺいは自宅で寝ていたため、その葬儀にさえ出席できなかった。
さらに……けろりと話すのだが、さらに、その五年後、かっぺいが高校三年になった年、今度は父親が亡くなる。母は四十代半ば、父親は五十代半ばだった。
「仏壇の写真が、おふくろは硬い顔で、親父は笑ってるんですよ。母親は私が十三歳のときに死んでるから、もう写真の顔しか思い出せない。その硬い顔のまま。笑ってる顔を思い出せない。だから、仏壇の遺影ってウソでも微笑んでる顔にしたほうがいい。苦虫噛み潰した顔だと、年月とともにその顔しか思い出さなくなるから」
かっぺいに「理屈(おくやみ)」という詩がある。
親父(とっちゃ)死んだて?
そりゃ お喜びで
共(いしょず)に笑てやるべ 私(おら)
(中略)
親 居ねぐなるのが
不幸だんだば
不幸がひとつ減ただでばな
こりゃ お喜びだ
大(でった)だ声で笑るべし
その前に
少々(わんつか)だげ泣いでも良いよ
少々(わんつか)だげ
私(おら)だて
少々(わんつか) 泣いだ後(あど)から
少々(わんつか) 泣いだ後(あど)がらでねば
笑えながったんだはで
二〇〇七(平成十九)年には定年を迎える。二足のワラジもいよいよ一足になってしまいますね、と聞くと……。
「拠り所がなくなると駄目になるんじゃないかと思うんですよね。両方で歩いていたから良かったけど。ま、いままでも弾みと流れで生きてきたから、これからも同じでしょう、基本は。今週と今月うまくいけば、そのまま来月へ。よく言ってるのは、四月十六日で定年だから、十五日まではサラリーマンとの二足のワラジ。十六日からはプロだからギャラ上がるよって。途端に、仕事なくなったりしてね」
伊奈かっぺいとしての歩みは、すでに単行本、CD(レコード)ともに三十冊、三十枚を超えた。
この道一筋という生き方が称揚される世の中にあって、さまざまなことに手を出し、いずれもそこそこの出来までしか達しえない人は、軽んじられてしまう。
でも、誰もがその道一筋に生きて一流になれるわけじゃない。というより、一生、イヤな思いをして一流になるより、できるだけ楽しく仕事をして二流でもいいではないか、とも思う。
二流あっての一流なのだから、と笑いにまぎらせつつ。
番組も四十分が過ぎようとしていた。CMもなし、音楽もなし。
《……ちょっと喋り疲れてきたかな。そろそろ一曲行きましょうかね。七月のこの時期、まだ梅雨なんですが、団塊の世代としては死ぬまでといいましょうかね、記憶に残る歌があるんです。関口宏さんの奥さんとはまた違った歌い方で、これもまたいいもんで。関口さんの奥さんも……何度も言うこたあないやね、西田佐知子さんって言えば良さそうなものですが、西田佐知子さんとは違って、この方の歌もなかなかのものでございます。気持ちとしては、傘さしながら庭の植木に水蒔いているような気持ちで聞いてみていただくといいのではないかと思いますね。クミコさん、このアルバムのころは高橋クミコさんといってましたが、はい、『アカシアの雨がやむとき』……》
月曜日の夜、番組は、さらにつづいていった。
|
|