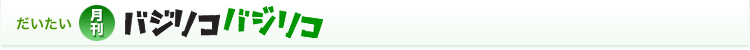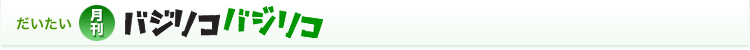毎週月曜日、夕方になると、佐藤元伸は自宅から歩いて十五分ほどのところにある勤め先に向かう。
午後五時を過ぎると正面玄関が閉じられてしまうため、夜間出入り口のドアを開ける。すぐ左手に警備員の待機する小部屋があり、軽く挨拶を交わすと、入り口の右手にあるタイムカードを機械に差し込む。
ここに勤めて三十七年、来年には定年を迎える。
一階のロビーは閑散としている。ソファーに腰を下ろし一息つく。
午後六時五十分、佐藤はエレベーターに乗り、三階まで上がる。エレベーターホールのすぐ前の部屋に入ると、二人の男性が機械を前に座っている。
部屋の半分はスタジオであり、こちらは副調整室。ガラスによって仕切られている。
佐藤は彼らとほとんど話をせず、スタジオの中へと進む。マイクが設置されたテーブルの前に一人腰かけ、ヘッドホンをつけ、手元の葉書に目を落とす。
午後七時。テーマ曲が流れる。
《どうも、伊奈かっぺいです……》
青森放送のラジオ番組『伊奈かっぺいの旅の空 うわの空』が軽快にスタートする。
佐藤元伸は、いつの間にか「伊奈かっぺい」になっていた。
《……昨日今日あたり暖かくなってきた。いまの時期、「暖かい」じゃ、いかんのですよ。「暑いな」というふうになっていないと。青森に限らず、夏は暑くて、「暑いね、いつまでも」なんて挨拶が似合うのであって、冬は冬で、「雪が多いね、今年も」なんていう愚痴が、一番健全な愚痴じゃないかと思うのでありますよ。健全な愚痴、口からでまかせに言ったわりには、いいフレーズだな、フフフフ、なんていうふうにね、思ったりもしているわけでございます……》
その語り口は軽妙洒脱であり、訛りのある落語家、といった風であった。
初めて、伊奈かっぺいという名前を見たのは、きっとテレビ番組だったろう。略歴をみると『かっぺい&アッコのおかしな二人』が一九八六年からとあるので、そのころかもしれない。歌手の和田アキ子と二人でホスト、ホステスを務め、毎回ゲストを呼んで話を聞くという番組だったように思う。
とにかく「ふざけた名前だなあ」というのが初めの印象だった。なにしろ「いなかっぺい」である。年齢不詳、正体不明、津軽弁、はにかみ屋、一見朴訥に見える、しかし、妙に厚かましい。
このテレビ番組は一年半で終わりを告げた。
その後、随分と経ってからだ、この人が放送局の社員だと知ったのは。そして、津軽弁で詩を書いている詩人でもあると知ったのは。
伊奈かっぺいこと佐藤元伸は、一九四七(昭和二十二)年、青森県弘前市に生まれた。いわゆる団塊の世代である。地元の短期大学を出た後、「何となく」陸奥新報という新聞社の整理部に就職する。入ってみてイメージしていた仕事とは違うことに気づき、一日で退職。知り合いの口利きで青森放送の美術部のアルバイトに潜り込む。
もともとレタリングや絵が好きで、高校時代には通信教育で学んだりもしていた。新聞社の整理部よりは向いていると思った。そして、何より報酬が良かった。新聞社の給与は、けっきょく一度ももらわなかったが一万五百円、年に二度五百円ずつ昇給するということだった。青森放送のほうは、アルバイトであるにも関わらず、何と月給が二万八百円だった。二倍である。
翌年、他の新卒とともに試験を受け、正式に社員となった。
美術部には十年間在籍。スタジオや公開放送のセットも作る、テレビ出演者が手にするフリップも書く、テロップも書く、写植も打つ、ときには新しく購入した局の自動車のデザインまで考えた。テレビにおける「目に見えるもの」はすべて作っていった。
楽しかった。中学、高校と演劇部に在籍していたため、クラブ活動の延長のような気がした。実は、このアルバイト時代に佐藤元伸は初めて「伊奈かっぺい」の衣裳も身にまとうのである。
アルバイトのかたわら、津軽弁で芝居を作る地元の劇団の美術も手伝っていた。発表会のとき、パンフレットにスタッフ名を載せなくてはいけない。アルバイトの分際で、外部の芝居などもってのほかだと、多少の自制心は働いた。それで付けたのが「伊奈かっぺい」である。だから、芸名でもペンネームでもなく「偽名」なのだ。
やはりこの美術部時代、いつからかノートに連綿と日記を書くようになった。ときには何ページにもわたる長文のものも。それらは、方言詩とでもいうべきものだった。
「方言詩人として知られた高木恭造さん、隣の町内にいたんです。本職は眼科医。中学の図書室でそのその高木さんの方言詩集に出会ったわけ。あのころ、学校じゃ、津軽弁は使っちゃいけないって言われてましたから。汚い言葉なので、みんな標準語を喋るように、ってね。ところが、学校の図書室にその詩集があった。矛盾でしょう? 喋るのはいけないけど、字で書くのはいいのかってね」
方言を使って詩が書ける、そのことがかっぺいには衝撃だった。
かっぺいじしんは、面白く笑える詩が好きだった。読む者が思わずニヤリとするような詩を書きたいと思った。
見えそうで
見えそうで……見えねェ
そのくせ
見えそうもねぇ時(どぎ)
チラッと見えだりする
「春風(スカート)」と題された詩の冒頭である。
一九七四(昭和四十九)年、二十七歳のとき、自費出版で詩集を作った。タイトルは『消ゴムでかいた落書き』。全編、文字は手書きである。「マンガ文字」「変体少女文字」などが話題になるはるか以前、見事に丸文字のごときクセのある字で書かれていた。
五百冊を印刷し、すぐに増刷、口コミによって反響が出てくる。あるときラジオの深夜放送『オールナイトニッポン』で取り上げられた。すぐ後、自費出版の詩集をもう一冊出す。『落書きのつづき』である。
やがて、東奥日報という新聞で週に一度エッセイを書かないかと頼まれる。ニッポン放送の朝の生番組に出て、詩の朗読をした。それを聞いたコロムビアレコードの社員が、どういうわけか「朗読のレコードを出しませんか」と言ってきた。驚いたが、もともと芝居ごころはある。ええいままよと引き受け、それが詩集と同タイトルのアルバム『消ゴムでかいた落書き』になった。かっぺい、三十歳のときである。
青森の放送局の社員で詩集を出し、レコードを出してるヘンなのがいる。ひょんなことからテレビ朝日の『徹子の部屋』に出演することになった。その番組を見た映画監督の山田洋次が、自分が原案を書いた映画『俺は上野のプレスリー』(一九七八年公開)の方言指導とナレーションを依頼してくる。ついでに、タイトルやポスター、クレジットまで手書きで作ることになった。
東京のテレビや雑誌からの出演やインタビュー依頼も増え、「伊奈かっぺい」という名前も、少しずつ世間に知られていった。
|
|