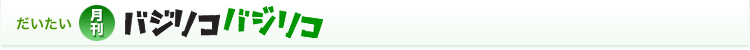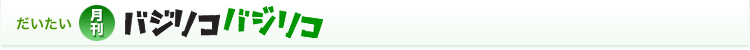昨日は荒川、今日は小金井と、都の人は、花を訪ねて忙しい。
走れど走れど路上には、花見帰りと見える人の姿が引ききりなかった。まるで自分ばかりが冬に取り残されているようだ、と明子は思う。
失恋に疲弊した心が影響を及ぼしてか、熱海の避寒より戻ってこのかた、ずっと身がだるく、熱っぽい。とうてい過酷な探偵業務を遂行できる状態ではないと感じて、休暇を引き延ばした。はや一週間、自宅に籠もって鬱々としてきた。
それがこの夜になって急に、父の自動車を駆り外套を着込んで出勤しているのは、ぜひ岡田明子探偵にと指名してきて、不在を告げても待ち続けている依頼者がある、との電話を受けたためであった。
社の前に、真新しいフォード車が横付けされているのを見て取り、依頼人のものだと推測した。探偵としての習性から、無意識にナンバープレートの数字を記憶しながら、その真後ろに、操縦してきた白いオートモ号を停める。父卓三は自動車の操縦を好まず、また運転手を雇う性分でもないので、明子が免許を取得してからは、ほぼ彼女の専用車と化した。この小さな自動車を彼女は今や、手足のように自在に操ることができる。
表玄関はもう閉まっている。建物脇の路地を歩いて裏口から入り、守衛室の窓を覗いた。守衛は椅子に坐りこんで本を睨みつけている。萬【よろず】さん、と声をかけたらようやく気づいて、閉じた本を手にしたまま立ち上がった。
「岡田さん、お身体のほうはもう――?」
明子はかぶりを振って、「でも、是非とも私にという依頼者がみえているとか。ご指名とあっては出て来ざるを得ないわ。それより萬さん、勤務中に本など読むなと野暮を云う気はありませんが、ここを覗いている人間にも気づかないようじゃあ、なんのためのご立派な制服だかわかりません」
守衛はつるつる頭を撫であげて、「すみません。人から借りた本でして、そろそろ返さねばと思うと、ついつい開かずにはいられなくなり」
明子は本の表紙に視線を落とし、「その作者、昨年服毒自殺をした――。河童が出てくるんですか。そんなにも面白い?」
「いいえ、河童の話なら私にも解るかと思って借りてみたんですが、さっぱり通じませんな」
「それにしちゃ、ご熱心でした」
廊下を進み、複数ある応接室を覗いてまわったが、いずれも無人だった。唐草の執務室へと足を向ける。まさか自分で呼び出しておいて、外出したり帰宅してはいまい。
東京探偵社の代表、岡田検事の親友でもある唐草七郎は、じつに飄然たる人物であって、しばしば居所が知れない。経営にも無関心で、何不自由なく育てられてきた明子でさえ、こんな調子でいては社が存続しないのではと心配になるくらい商売気がない。
にも拘わらず社が安泰を保っていられるのには、鬼神や魑魅魍魎の仕業にも思える摩訶不思議な事件が、増加の一途をたどっているという皮肉な背景がある。無論のこと名探偵唐草七郎が論理の光を当てるや、幽霊の正体見たり枯尾花とばかり、人間特有の思い込みや錯覚を悪用した犯罪者の姿がつまびらかになるのが常であったが、それにしても――社会が複雑化しすぎてしまったのだろうか――科学万能である筈のこの時代、世人たちは明治大正の御代よりも、いやもしかしたら徳川の治世と比してすら、つねに漠たる不安感に包まれ、且つ迷信ぶかくなっているような気がして明子にはならない。なにしろ探偵社の守衛が河童の小説を読み耽るほどだ。
果たして唐草は在室だった。こちらもまた本を広げているが、机越しに見えたところ分厚い洋書である。また心理学の解説書を取り寄せたのだろう。
「おや明子くん、ずいぶん早かったね」と云って眼鏡を外した。自分で呼びつけておいて暢気なものだ。「体調は戻ったかい」
「本調子ではありませんが、ご依頼の件はこなせるかと存じます」
「なぜ依頼の内容を知ってるんだろう。僕もまだ聞かされていないというのに」
「お電話で、全面的に私に任せると仰有ったじゃ御座いませんか。先生にはご関心のない、単純な事件かと」
「誤解ですよ。まず僕は明子くんの能力を高く評価しているし――」
「ありがとう御座います」
「そもそも先方が、担当するのは君でなくてはならない、ほかの者は、たとえ僕でも願い下げると云って退いてくれないんだ」
「なぜでしょう」
「女性でしか扱い得ない事件なのかもしれないし、性別とは無関係に、あくまで岡田明子の業績を高く買っておられるのかもしれない。ともかく小さな仕事ではなかろうよ。腰を抜かす程の成功報酬の額面を書いてきた。しかも結果の如何に関わらず、月々五百円の経費を保証するという」
明子は目をまるくした。一流会社の社長でも、それほどの月給を得ている者は滅多にいない。「ご依頼者はどちらに。応接室には見当りませんでしたが」
「僕もまだ会っていないんだ」
「それは、どういった訳ですか」
「遣いの小僧が運んできた君宛ての書付に、僕が代わって返事を書き、するとまた返信が運ばれてきて――つまり僕は依頼者と、未だ筆談しか交わしていない。姿を見せるに見せられない人物、ということかな」
「表に自動車が停めてあります。その中でしょうか」
「うん、気づいていた。恐らくね」
「確認してきます」と部屋を出かけた彼女を、
「明子くん」と唐草は一度呼び止めた。「胡散臭いと感じたなら、断ってしまっても構わないから。そこを君自身に判断させたくて、わざわざ出てきてもらったんだ」
社を出て表通りに向かった明子は、くだんのフォードが、いつの間にか路地の出口まで移動しているのを見て取った。バケツ型の帽子をかむった運転手が、ドアに手を掛けて待っている。近づいた明子に対して無言でそれを開いた。兵卒に命令を送る士官のような、どこか高圧的な態度だった。
明子は従った。後部座席には既に人がいた。隣り合って坐った。
洋装の婦人である。しかし車内が暗いうえ、髮に留めたヴェールを前に下ろしているので、顔貌【かおかたち】はまったく判らない。あの――と話しかけようとしたとき、前に乗り込んできた運転手が、なにやら発して、乱暴に自動車を発進させた。日本語ではなかった。
「岡田明子さん、ご機嫌麗しゅう」と婦人のほうから話しかけてきた。気品のある、落ち着いた声音だった。「ご心配なく。その辺りを一回りしたら同じ通りへと戻ります。すこしのあいだ、誰からも邪魔されることなくお話ししたいのです」
探偵社の応接室でも、人を払ってしまえばふたりきりで話せる。邪魔など入らない。自分の姿を観察されることなく、が本音であろう。しかし自動車のナンバーは――と明子が記憶をまさぐりはじめたのを、まるで見透かしたかのように、
「これは偽名で借りた、貸し自動車です。また運転手は別途、日本語の通じない者を手配しました。私が何者か知りませんし、いまこうして話していることも理解していません」
「失礼乍ら」と明子は遮るように、「今後ともその姿勢を貫かれるお心算【つもり】でしょうか。つまり、社にも私にも正体を明かされず――」
「どうか誤解なさらぬよう。決してそこを第一義としている訳ではないのです。大切なのは、凡てが秘密裡のうちにおこなわれること。私が素性を明かさぬよう慎重を期しているのは、その為の保険に過ぎません。明子さんが幾つかをお約束してくださるかぎり、お願いする仕事は危険なものではありません。しかし破られた途端、その限りではなくなってしまいます。ですから私からの最初の条件は、こうです。依頼の内容は、誰に対してであれ口外なさらぬこと――唐草先生に対してさえ」
「少々お待ちください。探偵の看板を揚げている以上、その務めの上のことであればお引き受けいたす心算です。しかし最終の判断は、お話をうかがったのちでなければくだしようがありません」
「御尤もです。ではその点では折れましょう。そしてお断りになる場合は、この自動車の中での一切を忘れてください。きっと忘れてください」
「承知しました」
「今一つ。このさきの私の話には、問いを差し挾まないでください」
「仕事のために必要な事項もですか」
「必要な情報か否かは、こちらで区分します。勝手に踏み越えてはなりません」
「承知致しました」と今度は吐息まじりになった。なに、あまりに雲をつかむような話であれば、唐草に云われたとおり断ってしまえばいい。
「第三点は、せんに申しました保険です。私の、このヴェールの内を覗こうとしないこと」
頷くだけで済ませて、「お用件の条は?」
ここに至って貴婦人は沈黙に入った。なかなか語りだそうとしないのを明子は訝しんで、車の振動に黒いヴェールが揺れるさまを、不躾なほどじっと直視した。不図、街あかりの加減からその奧に、双つの鋭い輝きが生じて、消えた。依頼者を値踏みしているような気で、じつは自分のほうがされていたことに明子は気がついた。
あの時点に於いて自分は運命を枉【ま】げられたのだ――のちになって明子は、ほんの数十秒に過ぎなかったであろうこの沈黙を、ふかく感慨することとなる。貴婦人が放つ特異な香気に眩惑されたか、その言葉の向こうに見え隠れする謎めいた世界に、探偵としての本能が導かれたかは、本人にも定かではない。
「黄水仙の黄の字を書いて、コウと読みます。この姓を持つ、支那人の三人姉妹を探していただきたいのです。一番の上は、瑶子【ようこ】といって、今年二十二。次は、瑛子【えいこ】二十。末が、玲子【れいこ】十七です。瑶、瑛、玲、いずれも王偏の字を書きます」漸くと本題をきりだした貴婦人の、口ぶりは先程までとは打って変わって、愁【うれ】えを含んでいるように感じられた。
それにしても支那人の娘が、三人とも揃って日本の名前というのは、いったいどうしたことか。通称であろうか、それとも黄氏は帰化人なのか。つい問いかけて、交わしたばかりの約束を思い出し、唇を閉じる。
「探す目印とも、なることは――」聞き洩らさせまいとの配慮からか、貴婦人はそれまでになく明子に身を寄せた。「三人ともが左の耳に、一粒の琉璃玉が填った、白金の耳輪をしていることです」
「え――?」という聞き返しには、さすがに行き違いを避けようとしてか、
「琉璃玉の耳輪です」と彼女は繰り返した。「この三人を探して、一年後の今夜――四月十五日の一夜、丸の内ホテルの十五番室に連れてきてください」
これが現実の会話であるという確証を求め、思わず視線を窓外へと泳がせた明子だった。自動車は皇居をぐるりと巡っているようだ。喧噪と閑寂が奇妙に入り交じる、見慣れた大東京の夜景が、記憶のパノラマよろしく現れては消えてゆく。
現実の依頼であることを確信したあとの明子の心理は、探偵として不適切であったばかりか、教養人らしい分別に律されていたとも云いがたい。琉璃玉の付いた白金の耳輪と聞いて、稲妻のごとくその脳裡に走ったのは、熱海から戻る車中で耳にした、紳士ABCもしくは甲乙丙の品のない会話である。南京町のマリーの噂だ。
「面白い女だからなあ」
「支那人と毛唐の混血児【あいのこ】で」
「琉璃玉の付いた」
「白金の耳輪をした」
「凄腕なそうだね」
「南京町へ行き給え」
「若い伯爵の耳に入ったら」
「我々の友人、売笑婦さ」
白金に琉璃玉の耳輪。どこにでも売られている代物ではない。毛唐との混血児という点が引ッ掛るが、父が黄氏、母は欧州人だと考えれば一応の理屈はとおる。そういう女が不幸にして身をもちくずし、親との思い出を喚起させる南京町に棲みついているというのも、如何にも有りそうな話だ。
――と、ここまでは理知的な判断だったと云えよう。それなのに嗚呼、恋は盲目、とシェイクスピア作『ヴェニスの商人』にあるように、熱海での片恋の残り火は、閨秀の探偵岡田明子の目を曇らせた。そして彼女をして、徒労に満ちた長い捜査行へと迷わせたのである。
桜小路公博の心を翻弄している女を想起したことで、明子の眼力は重大な事実――みずからを取り巻きつつある過剰なまでの符合――を見逃した。月五百円の必要経費をぽんと払える富豪の情報網が、偶然の見聞に劣る筈などないという当然に、気づかなかった。
それどころか、この仕事を受けたなら、姿も声もわからぬままに自分を苦しめてきた恋仇と、接触できる、どちらが公博に相応しい女かをめぐって対決できるかもしれない――そう、無邪気な空想に心を躍らせてさえいた。
詮ずるところ、ルリダマのミミワという響きを耳にするや、明子の心は調査開始へと大きく傾いていた。そう即答しなかったのは、マリーが瑶子瑛子玲子のどれに当たるにせよ、残るふたりの行方を知っている確証はなく、きっかり一年という調査期間が充分とも不充分ともつかなかったからだ。
見つかり次第、連れて来いと云うならともかく、特定の日に一所に集めてほしいとの旨が、また解せなかった。極端を云うならば、首尾よく期限内に三人を発見できたとしても、来年の今日までに誰か事故死でもしてしまったら、明子は任務を完了できなくなる。確実に身柄を保護しておけとの意であろうか――。
「旅行はそろそろ終わりです。お応えを頂戴したく存じます。引き受けてくださいますか」
貴婦人の問い掛けに、はたと我に返る。はや調査に臨んでいるような気で、手順を算段しはじめていた。明子は改めてヴェールの貴婦人を見返した。この不可思議な人物が自分を見込んでくれたことが、今は嬉しい。
「お引き受けする所存ですけど、そのまえに一つだけ教えていただきたいのです」
「条件をもうお忘れですか」
「いいえ。でもご依頼の儀にも貴方の正体にも、恐らく無関係なことなんです――世間に大勢いる探偵のうち、なぜこの私を頼ってくださったのでしょう」
「お答えできません」拒絶は、鰾膠【にべ】もなかった。貴婦人は膝に置いていた手提げから紙包みを取り出し、明子に寄越した。「三个月ぶんの経費です。以後は三月毎【みつきごと】、東京探偵社宛てに郵便でお届けします」
自動車が停まり、外に出て駆けてきた運転手によってドアが勢いよく開かれ、愕いた明子は慌てて地上に降り立った。そうして星空の下に立ってみれば、まるで一篇の映画を観て映画館から出てきたような心地であった。向き直ったときフォードは既に走りはじめていた。街灯を照り返す硝子の向こうに、もはや貴婦人の姿を見極めることは叶わなかった。
唐草は社に居残っていた。明子が引き受けることにしたと述べると、依頼内容を問うこともせず、
「そう。じゃあ任せたから」とのみ云った。
明子は自分の机上で、渡された紙包みを開いた。中身は真ッ新【さら】な百円札十枚に、二十円札が二十五枚――都合千五百円であった。
ふたたびオートモ号を駆って自宅に戻った彼女を、まず女中が、次いで岡田夫人が出迎える。
「お帰りなさい、明子。お仕事は済んだの」
「ええ、今日のところは。ありがとう」手を伸べてきた女中に、首巻や外套を預ける。遠縁の岡田家を頼って山陰から出てきたこの娘を、明子は実の妹のように可愛がっている。「町子の今日はどうだったかしら。なにか素敵な出来事はあった?」
「いいえ、そんな」と少女ははにかんだ。「いつもと同じ一日です」
帽子掛けに、山高帽は見当らない。
「お父様はまだ――」
母が諦めきった笑みで、「厄介な案件を抱えていらっしゃるとかで、また夜半を過ぎるとお電話が。晩ご飯は私たちだけでいただきましょう」
明子はやや考えてから、「そうですね、楽しくいただきましょう。残念乍ら私も明日からは、食事もゆっくりととれそうにありませんから」
「まあ、いつまで」
「一年間」
母はぽかりと口を開いた。「まあ、まあ」
――倹約を旨とする岡田家の食卓に、庶民のそれと変わるところはなんらなく、あるじ不在の当夜はいっそう簡素であった。食後、お茶の支度をしている町子を、明子はつかまえ、「ねえ町子、本物の琉璃の玉を見たことはある?」
女の子はかぶりを振った。「御座いません」
「夜空のように深い青をした石で、ところどころ金色が混じっているの」
「それで透き通っているんですか」
「透明ではないわ。でもみずから光を放っているように見える」
「想像もつきませんけど、きっと美しいんでしょうね」
「そんな玉の填った、白金の耳輪、町子はどう思う?」
「どうと云われましても――耳たぶに孔を空けるんでしたら、私には怖くて出来ません。お嬢様、なさるつもりですか」
明子は声をあげて笑い、「そんなに目立つ物をつけたら、誰も尾行なんか出来やしない。なにか、そんな人の噂でも聞いたことがないかと思って」
「いいえ」町子もほっとしたように頬笑んだ。「せんに鳩居堂へお使いに行きましたとき、全身に綺麗な更紗をまとった、印度の御婦人を見掛けました。耳にも、それから鼻にも飾りをつけておられましたが、印象に残っているのは赤い輝きです。青い宝石ではありませんでした」
「つけているのは、きっと支那の娘よ」
「支那では、よく琉璃を身につけるのですか」
「そうではないわ。私がこれから――」探さねばならない三人の娘の話だと、つい教えそうになって、貴婦人との約束を思い出した。「ともかくそんな人を見掛けたら、誰にも云わず私にだけ教えてちょうだい」
「わかりました」
「お遣いのあいだだけでいいから、気をつけておいて。もし有用な情報を提供してくれたなら、お駄賃をはずみましょう」
明子は半ば冗談として云ったのだが、町子は真に受けた。「本当ですか」
かえって心配になり、「お給金が足りないの?」
女の子はまた頭を横に振って、「花園神社の前で興業している好奇座が、とても面白いので観ておいたほうがいいと、電車のなかで話している人がいました。もしお嬢様のお役に立てたら、私を連れていってくださいますか」
「どんな見世物なの」
「手品や軽業だそうですが、外国仕込みの珍しい芸も多いとか。ああ、それから去年開通した地下鉄道にも乗ってみたい。どちらにしましょう」
「浅草から上野の? たった五分を乗るための行列が一、二時間も続いていると聞くわ。好奇座とやらで手を打ちましょう」と握手を求めてやった。無論、町子が調査の役に立つなどとは期待していない。興行が長いならいつか自分が、近々切り上げられるようならば人に頼んで、観せてやろうと考えた。
町子は心底嬉しそうに、ふっくらした手で握り返してきた。「ありがとうございます」
明子の部屋は、二階の質素な西洋間である。茶を飲み干した彼女は、階段を上がり、机の前でノートを開きペンを取った。社にいるあいだは、いったん家に寄ったのち横浜南京町まで自動車を走らせるつもりだったのだが、母や町子とののんびりしたやりとりが、彼女の頭を冷却した。今夜は動かず、平静に調査の手順を計画するべき、と思い直すまでになっていた。
まずは慎重な聞込みからだ。準備なくしてマリーの許に飛び込んではならない。
人探しにおいて最も手間なのがこの点で、たとえ目星がついていても、接触にはくれぐれも慎重を期す必要がある。尋ね人が、今も表社会に属しているとは限らないからだ。否、裏社会に身を潜めている場合が大半であり、追えば逃げるのが、いつしか身に染みついてしまった彼らの性分である。
逃げるとすればどこ、とまで身辺を洗ってからでないと、とてもではないが来年まで身柄を確保し続けることなど出来ない。自分という人間を信用してもらうか、もしくは確実に騙し続ける必要もある。これらを独力で、三人ぶん――。
この案件、思った以上に難しい。色恋に対してはともかく、探偵業務に対しては絶対的とも云えた、明子の自信が揺らぎはじめた。彼女の部屋の、窓の灯は、明け方になって、消された。
山崎というその男、女性への執着だけは、子供の頃から一廉ならぬものがあった。
但し、決して生まれ乍らの変態性慾者ではない。
大人びた少年だった。実直な性格、優れた頭脳は尋常小学校では称賛の的で、家の貧しさから中学に進めなかったのが悔しく、教会に通って英語を学んだほどの努力家でもある。
他にこれといった技能も資格も持たなかったものの、人好きのする容姿も手伝って、目上からよく可愛がられた。しかし勤め先の破産や倒産が重なり、職は転々とせざるを得なかった。
二十代、魚河岸で掃除夫をしていたとき、怪我人を見掛けて介抱してやったことがある。そのさまを一流料理店の店主が見ていた。気配りも手際も見目も申し分ないから、ひとつボオイとして店に入らないかと誘われた。これが転機となった。
客あしらいに長けた彼は、たちまちボオイ長に出世し、三十路で帳場を任されるに至った。使われ上手――主君の心を巧みに読んでは的確に行動して、名を振るった偉人が歴史に散見されるけれど、山崎はまさにその型で、店主の彼に寄せた信頼は、絶大にして絶対だった。
目下の足場が世間並みであれ、それ以下であれ、人生が上向いているあいだなら、人は心を豊かに保つことができる。その頃の山崎もそうだった。彼の不幸の端緒は、やがて青天の霹靂としか称しようのない、ある事情から、一財産を掴んで、人を使う側に立ってしまったことである。
新しい立場に、彼はとことん向かなかった。下の者にはっきり道を示すということが、どうにも難しい。頭の切れに自信があるぶん、泛んでくるどれもこれもが名案に思えて、何个月が経っても決心に至らない。長考と云えば聞こえがいいが、たんなる優柔不断である。
しかし商売が露骨に下火となり、資産が目に見えて減りはじめると、暢気にしてもいられなくなった。焦りが高じて今度は、儲けの口ありと耳にすれば、精査もせず投資を試みるようになった。運試しのつもりで初めて買ってみた株が、短期のうちに値を上げたのがいけなかった。みずからの直感に根拠なき自信を抱いてしまった山崎は、たちの悪い仲買人たちの、絶好の鴨となった。
本人は攻勢に転じている気でも、外から見れば悪足掻きに過ぎない。足掻くほどに貧しさは増し、気がつけば貯えも職も失ったうえで、生まれ育った深川の裏長屋に逆戻りしていた。彼にはお峯という妻がおり、この頃、ふとした風邪から寝付いた。どうしたことかと彼が慌てているうちに、どんどん弱って、急に遺言めいたことを口走ると、その翌朝には冷たくなっていた。死因は未だに判らない。もはや医者に診せる金も残っていなかったのである。
――ここまで記してきたのは、山崎の半生を翻弄してきた波風の、ごく表層に過ぎない。より重要とも云える内幕は、のちの季節、或る女の口より仔細に語られようからそちらに譲るとし、本項に於いてはそんな彼が、如何にして豪邸を構え別荘を借りられるまでにふたたび這い上がったかを、取り急ぎ語るに留めておこう――。
身を裂かれるような転落の日々は、彼の人品を一変させた。一日、もはや何一つとして失うものかと叫び散らすや、一路、成田山を目指して歩きはじめた。昼夜を徹して歩きに歩き、漸くと新勝寺まで辿り着いた彼は、不動明王に身勝手な立願【りゅうがん】をした。
一年――二年――いや三年間、女との目合【まぐわい】はせぬし手淫もせぬ。酒も、好きな煙草も断とう。手段を選ばぬ覚悟もある。だからその三年で、これまでに失った総てのものを、どうか我が手に返したまえ。
数日後、帝國ホテルのロビーに、借り物の背広に身を包んだ山崎の姿があった。裕福そうな外国人と見るや近づいていき、自分を通訳として雇うよう申し出る。断られても断られてもロビーから消えない。しかし通訳で地道に稼ごうという気など、更々無かった。山崎が求めているのは日本語を解さぬ金持ちだった。然からば、何彼【なにか】につけ、彼の弁を鵜呑みにするより他にない。
ロックという英国から来た高等遊民が、彼を気に入って雇い、やがて口車に乗った。みずからが儲ける胸算用で、北海道のある鉱山【やま】の、向こう三年ぶんの石炭の発掘権に出資した。日本の発掘権は安いとご満悦だった。
安いのもその筈、それはとうの昔に鉱脈が切れ、打ち捨てられて久しい鉱山だった。本当の権利料は、ロックが支払った半額に過ぎなかったのである。しかし山崎は、掘れば出ると踏んでいた――正確には、不動明王が出してくださると。
差額を借金の返済や当座の生活費に充て、ロックから首尾を問われるたび、手続きに手間取っているだの、坑夫が集まらないだの、事故が起きたのと言い訳を重ねながら、ひたすら北からの報せを待った。
一年後、長屋に朗報を運んできた配達夫は、這い出てきた受取人の姿に、ぎょっとなって電報紙を取り落とした。絶え間ない不安と緊張に起因する強烈な不眠、慢性的な頭痛、抗するための大量の睡眠剤とミグレニン、体内に嵐のごとく渦巻く性的欲求と、それが招く幻想や耳鳴りに疲れきった山崎は、墓地から舞い戻ってきた幽鬼さながらの風情だった。
拔け目なく権利書に自分の名も並べていた彼は、一躍金満家となり、ロックに糾弾される恐怖からも解放されたが、未だ自分が総てを取り返したとは感じていない。不動明王への誓いをやぶるや、一切が水泡に帰してしまうとも考えている。
禁慾が生む幻想はいっそうまざまざしい。薬は日一日と量を増して、夢とうつつの区別がつかなくなりつつある。それでいて脳内の一部は常に覚醒して冴えわたり、まるで自分を模した木偶を後ろから操っているようだ。
――岡田明子がヴェールの貴婦人と接していた、四月十五日の晩。その深夜、杉並の山崎邸を、前触れなく訪ねてきた人物があった。
高い木塀と土蔵を気に入って買ったこの家に、来客はきわめて珍しい。山崎は決して人を招こうとしないし、近所付合いも極力避けている。門の外を出歩くこと自体が少ないから、離れに寝起きしている下女の婆さんを別にすれば、いま彼の日常に佇んでいるのは唯一、玲子のみである。
下女――寅というこの婆さんは、病気のお峯によくしてくれた、同じ裏長屋の元住人だ。山崎が炭鉱で当てたと聞きつけ、下女は要らないかとみずから売り込んできた。家賃をためて長屋を追い出されそうなのだと云う。
他人を入れるのを好まないとはいえ、新しい住処を以前のようなごみ溜めにはしたくない。かといって家事を玲子に押しつける訳にもいかない。日一日と花開いていく彼女の美貌を、他の男の目にさらすのが厭で、外出させる時は男装を強いるようになっていた山崎だったが、顔見知りの婆さんなら仕方あるまいと、雇い入れた。
「旦那様、旦那さん――山崎さん」とその寅が庭から、閉めきっている雨戸を叩いてきた。日が落ちてからは母屋に踏み入らぬように、と固く云い渡してある。
「いったいなんだ」と雨戸越しに怒鳴る。
「お客さんです。母屋は人の気が無いからと、離れのほうに」
山崎は戸を動かして薄く開いた。「裏木戸を閉めておかなかったのか」
「ちゃんと閉じましたとも。どうして入ってこられたんでしょう」
「追い返せ」
寅は隙間に顔を近づけてきて、薄ら笑いをうかべ、「綺麗なお嬢さんですが、宜しいんですか」
山崎は舌打ちした。病的な迄に女に目がない彼の性情を、寅はよく知っている。「どこに居る」
「離れの玄関に待たして――」
「ここに居ますよ」と闇から声がした。「山崎さん、初めまして」
寅を押しやって雨戸の前に立ったのは、顔の半分を隠すような奇妙な断髪の、洋装の女――いや、まだ小娘と云っていい。南国の出なのか色黒で、山崎の好みからは遠かったが、目鼻立ちの華やかな痩身の娘である。
「戻りなさい」と、呆気にとられている寅に命じた。そして娘に向かって、「なんの御用かな」
「花園神社の前で興業しております、好奇座の、ツェッペリン八重子と申します。お見知りおきを」
山崎は苦笑した。「なんて名前だ」
娘は無表情に、「綱渡りの芸人なんで御座います。その宙を往く優美さたるや、菩薩が乗りし雲の端【は】か、はたまた科学の粋を集めて、地球を巡りしツェッペリン号か――とね。今は綱渡りは引退し、もっぱら手裏剣の的やら、胴体切断の叫び役、飛行船どころか泥船八重子と揶揄されていますが」
「あまり興味を持てないな。早く用件を」
「琉璃玉の耳輪を付けた女、お探しだとか」
山崎は驚いて身を反らし、雨戸を大きく開いた。「どこでそれを」
「妾【あたし】もご同類でしてね、旅の先では必ずといって、そんな女を見掛けなかったかと聞き込んでまわってきたもんです。山崎さんのことは前々から存じ上げていました。ある聞込み先で、山崎という炭鉱主も同じ女を探しているって教えられまして。で、久々に東京に上って、お客のひとりが仰有るには、お前の云っていた女を確かに見た、横浜南京町の路上で見た、と」
「――瑛子は、横浜に?」
「やっぱり違った」八重子と名乗った女は、山崎を責めたてるように云い、それから笑いだした。「秘密の倶楽部に居るらしいとも聞いた妾は、毎夜舞台が捌けるごと終電車に乗って横浜へ行って、夜が明けるまで路上で見張り続けました。だって、たとえ倶楽部の場所を突きとめたって、女の妾が入ってはいけませんから」
「あんたの苦労話など、どうでもいい。結論を。瑛子とは会えたのか」
「そういう名前なんですか、あの金髮女」
「金髮? いや違う」
「夜目にも鮮やかな金髮でしたよ、色を抜いているのかもしれませんけど。そして左の耳には琉璃玉の耳輪。でも妾が探してきた女じゃありません」
「あんたが探しているのは――すると瑶子か」
髮に隠れていない一つの眼が、爛々と輝きはじめた。「やっぱり知っているのね、瑶子を。いまどこに」
山崎は首を横に振った。「分からん。もう十年も会っていない。あんたはどこで瑶子に」
「同じ好奇座にいたんですよ。三年前に逃げ出していきましたけど――妾の大事な右眼を突き潰してね。それで仕方なく綱渡りを引退したんです」
八重子がそう云って長い前髪を掻き上げたので、山崎は思わず身構えた。しかし現れた右眼は固く閉じられて、すくなくとも瞼には、傷も変形も見当らなかった。
「――いい加減を抜かすんじゃないよ。瑶子のことなら誰よりもよく知っている。おっとりとした優しい子だ。人に乱暴をはたらくなど考えられない」
「じゃあ山崎さんがご存知なのは、また別の女かも――同じ琉璃玉の耳輪をした」
思わず家のなかを振り返りかけた山崎だったが、かろうじて自制した。
「妾の記憶に間違いはあり得ませんよ。頭じゃなくて眼が憶えてるんですから。この右の側は入れ眼です。元の眼そっくりにも造ってもらえたんですけどね、頼んで刻んでもらったんです、決して忘れないように――この世でいちばん憎くて、いちばん愛しい女の名前を」
八重子は瞼を開いた。山崎は男だてらに悲鳴をあげた。そこに眸は無く、囲む虹彩も無く、代わり、白眼の上に、瑶の一文字が刻まれていた。
(この項続く。次回掲載4月中旬) |
|