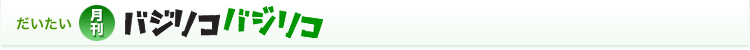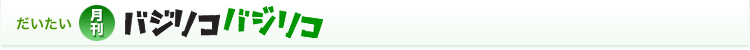熱海駅の構内にはいつも乍らに人が殺到し、汽車到着の報を待ちわびて、佇んだり、ぶつかり合ったり、出立を待ちきれずに弁当を広げたりしている。桜小路伯爵と夫人の茘枝(りえ)、ふたりを見送るためやって来た令息公博、この三者が一席を占めている一等待合にも、その喧噪は不穩な地鳴りのように響いていた。
「なかなか興味ぶかい」と伯爵。読んでいた新聞から顔を上げ、片眼鏡を外す。「物理学者エプスタイン博士、シオン主義運動を公然と支持、とある」
貴婦人ははたと夫を見返して、「博士が日本に?」
「外電からの転載だよ。学者なら学者らしく研究室へでも隠り、まつりごとに口を差し挟まずともよかろうにと思うが、それはそれとして、興味ぶかい」
「博士はユダヤ人ですからね」
「よくご存知だ」
「それはもう――」と茘枝は芝居がかって眉を動かし、「高名な方ですもの」
「パレスチナは英国領だが、在住のアラブ人は多かろう。そこに大量のユダヤ人が流入する事になどなれば、きっと争乱が起きようね」
「伯爵がそう仰有ると、まるで争乱を望んでおいでにも聞えます」
「まさか。懸念しているのだ。人間とはまこと愚かしくも、争いを希求して絶えない生き物だとは思わないかね。ましてや、異なる信条と文化を背負った者同士ともなれば」
「お互いの立場を尊重しさえすれば、どんな人間同士だって仲良く共存できます。そういう国家はたくさん御座いますわ。それに、ユダヤ人のいま置かれている立場は余りにも可哀相。いかなる民にも祖国を有する権利はございましょうに」
「君もシオン主義者らしい」
「共存主義者です」
両親が時折交わすこの種の論議に、公博はてんで興味が湧かない。しきりに背広の衿やらネクタイやらカフス釦を整えたり、腕の時計を覗いたりしていたが、到頭、
「そろそろ時刻ですね。ちょっと外の様子を見てきます」と生欠伸をかみ殺して立ち上がった。
伯爵がチョッキのポケットから金時計を取り出して、開き、「いや、お前の時計は進んでいるらしいよ。ゆっくりしているがいい」
「そうですか」と空惚ける。
外に出ていくきっかけは失ったものの、辛抱して論議の続きに耳をかたむける気も、自分から新奇な話題を提供しようという気も起きない。かしらを巡らせ、レエス布の掛かった窓縁に、変わった形のランプを見つけるや、余程のこと興味を抱いた振りをして大股に近づいた。
プラットフォームとは反対側にある窓で、レエスの隙間から構内が見通せるようになっている。そしてランプは、背を反り返らせた鋳物の蟷螂(かまきり)が硝子球を支えているという、なんとも風変わりな意匠の代物であった。尤も着物にも、虫の柄はべつに珍しくない。これは仏蘭西辺りの品だろうけれど、此国であちらの風俗がもて囃されるのと同様、彼国では東洋趣味、日本趣味が人気だとも聞く。案外にこれは和風を気取った、一種の折衷様式なのかもしれぬ。
不図、これは南京町のマリーそのものだと気がついた貴公子は、怺(こら)えきれず、両親に気づかれぬように顔を背けてくくくと笑った。
巣窟に相応しくいつも支那靴を履き、父は仏蘭西人、母は支那人と公言して、根っからの自由者を気取っている一方で、公博からだけはつまらぬ蔑視を受けたくないらしい、母は帰化していたから日本人、だから自分も半分は若様と同じ日本人だと云い張る。本当であれ嘘であれ、東洋西洋の折衷には違いない。
ランプを手に取り逆さにして蟷螂の腹を観察する。別な生き物を呑み込んででもいそうな、ふくよかな曲線を認めて、ほら雌だ、と呟く。そのうえ三角の頭と二つの斧に支えられた球体には、様々な色硝子がとろけ合わさり、マリーの髮の色、肌の色、口紅の色、彼女がいつも左の耳にさげ、閨(ねや)にあっても決して外そうとしない白金の耳輪と、そこに埋め込まれた琉璃の玉の煌めきまでもが見出せるようであった。駅長に交渉をして買い取って、ほらお前の銅像を見つけたよ、とでも云い彼女に突きつけてやったらさぞ面白かろう――そんなことまで考えついた。
しかし今朝のところは遑(いとま)がない。さっさと見送りを済ませ、ホテルに戻りたくて仕方がない。馬を飛ばしてあの蒼い洋館に向かいたい。
帽子を失ったのは、高窓から落下し尻餅をついた際に、まず違いない。窓を見上げていたあいだや、より遡って猫の声に似た悲鳴を耳にしたときは、まだ頭の上にあった。耳や額に当たる布の感触を、温もりを、漠とだが思い出せる。だから落ちたときだ。高窓の下だ。
頭文字だの家紋だのが縫い取られている訳ではないが、裏地に付いた横文字の刺繍を見る者が見れば、そこらで売られている形ばかりの安物擬物(まがいもの)とは別格だと気づこう。英国の老舖に型紙を送って縫わせた別註品である。
他客に身分を隠しているとはいえ、ホテルの者たちは自分が誰かを知っている。あれを被って歩いている姿も見ている。どこでどう洋館のあるじ――変態性慾の持主としか称しようのない、下劣極まりないあの男――と話が通じて、桜小路の御曹司は出歯亀、と云われはじめるか知れない。
南京町での不行跡には無頓着、いや、そもそも自らの風評を気にかける術も知らぬほど大らかに育った公博の神経を、今回の件にかぎってこうも尖らせているものは、むろん変態性慾の男への畏怖などではなかった。今やその愛人と確信するに至っている、唐人髷の――あの娘にばかりは死んでも低くは見られたくない、そんな切なくも滑稽な、男の矜持である。
だから男や娘に発見されるまえに一刻でも早く回収したいのに、昨日は梅園から戻るや両親に掴まって、最後だからと街場の逍遥に付き合わされた。ホテルに戻ったときにはすっかり日が暮れていて、その日の探索は諦めざるを得なかった。まさか他人の裏庭で、角灯(ランタン)を翳して探しまわることもできない。
そのまま明け方まで眠れなかった。朝食の直前、ボオイのノックに起こされて――。
枕の上で、はたとそれまでの短い夢を思い返した。彼は自分が恐ろしくなった。
夢のなか、公博は、あの変態性慾の男に成り代わっていたのである。
唐人髷の娘を縛りあげ、猿轡(さるぐつわ)をさせて、白き顔(かんばせ)に焼けた火箸を近づける。娘の両眼に赤い耀(かがや)きが反射した瞬間、肚の底から泉のように沸き上がった喜悦は、覚醒後の身にも明白にその名残があった。
さらに娘の失神していくさまは、彼の心に、絶対的支配者としての誇りを漲らせた。気付けを嗅がせて無理に目覚めさせ、卑猥な言葉で語りかけ、白魚のごとき指に顔を近づけ、口を開け、舌を出し、今しも舐(ねぶ)りあげんとしていたとき――館を一気に崩壊させる程の大地震が起きた。
現実世界に於けるそれは、ボオイの遠慮がちなノックと、寝覚めによくある、がくりと落下した錯覚に過ぎなかったのであるが。
ばしゃり。
窓が鳴った。公博はひどく驚き、両手からランプを滑らせかけた。
胸に抱きなおして、レエスをはぐる。硝子の向こうには、豆鉄砲を食らった鳩そのものの、団栗(どんぐり)まなこをした若い男の顔があった。
見覚えがある。しかし最近に見た顔ではない。
硝子を叩いた積りはなく、よろめいてぶつかっただけのようであった。恐縮しきった様子で帽子を取り、頭をさげて、窓から離れていく。身なりはそれなりだが足許が覚束ない。明らかに酔っている。汽車を待ち侘びた挙句に朝酒を決めこんだか、どうせ車中で眠ればいいと昨夜から飲みっぱなしの放蕩者だろう。また今度は、人間に後ろからぶつかっている。ぶつかられた着流しは迷惑そうに振り返ったものの、べつだん苦情を云うでもなく先を急いでいった。眼鏡の縁の輝きが、公博の網膜にとどまった。変態性慾の男――?
「そこに知人が」と父母に言訳をし、重い引戸を開けて待合いから飛び出す。
きゃあ、と大袈裟な声をあげ、その公博の前に立ちはだかった――彼に、そうとしか感じられなかった――のは、きのう肩を並べて梅園を歩いた、長身のモダンガール岡田明子である。
立ち竦んだ公博に、
「御免なさい。不意に出てこられたので愕いてしまって」と詫びはじめる。「そちらの窓にお姿が見えましたので、せめて硝子越しにでも、ご挨拶をと」
公博は群衆に視線を彷徨わせながら、口許でだけ笑い、「明子さん。そう、今朝お帰りでしたね」
「ええ、父母もあちらに」と明子が指し示した方向には、座席も、凭(もた)れる柱や壁も他人に譲って、中途半端な場に佇んでいる夫妻の姿が見える。
ときには鬼、ときには仏と頌えられてきた名検事、岡田卓三とその糟糠(そうこう)の妻の姿に他ならなかったが、公博の目には、明子の親御にしては平凡そうな壮年夫妻としか映らない。視線に気づいて、深々と頭をさげてきた。公博も一礼した。
「どうか東京探偵社に――」と続けて話しかけてくるのを、
「申し訳ないが明子さん、いまそこに知人の姿を見つけまして」と拒絶して、公博は着流しが歩き去った方向へと急いだ。人、人、また人――身分も佇まいも顔の表情も様々な、老若男女の波のなかを、きょろきょろと迷子の子供のように進んでいった。
「なんだって桜小路のご令息と、お前が――」構内を一巡りしたのち傍らに戻ってきた娘に、岡田検事が心配そうに問いかける。
明子は虚ろな目つきで、「いいえ、ぶつかりかけたのでお詫びしただけです」
「こちらにも挨拶してこられたよ」
「お父様が挨拶なさったからです。ホテルの相客だと気づかれたんでしょう」
「そうか」と、しかし得心のいかぬ調子で頷いた。「それならいいが」
別れの挨拶さえ袖にあしらわれた、明子の心はどんよりとして晴れない。昨日の梅園でも、帽子帽子と騒いで以降の公博は、まるで人が変わったように喋らなくなり、それでいて明らかに、何事かに対してひどく苛立っていた。原因が自分の言動なら、せめて詫びようがあるというものだが――。
遂にして彼女は、初々しい恋にとって最悪の可能性を、視野に入れざるを得なくなっていた。桜小路公博が、これまで自分にかけてくれた優しい言葉、向けてくれた笑顔、一切が社交上の辞令に過ぎなかったのだという――あの目映い貴公子の心は別の美しい女性が占めていて、男勝りの女探偵が入り込む余地など最初からなかったのだという――熱海の日々を彩ってくれた甘美な夢想の数々は、現実とはなんの関連もない、孤独な女の胸に去来した幻に過ぎなかったのだという――侘びしいかぎりの可能性を。
何が悲しいと云って、やはり彼女の本質は怜悧(れいり)な探偵であった。仮にこの恋が他人事なら、職業上の冷たさをもってこう断定するに違いないと、他ならぬ明子自身が気づいている。
凡て貴方の錯覚です。望みはないからお諦めなさい。ええ、これが私の推理した結論です。旅先での思いがけない出逢い、生まれて初めて経験する熱烈な慕情が、貴方を一時的に盲目にしていたに過ぎません。公博氏は、貴方が傍にいたから苛立っていたのではなく、傍にいない誰かのために苛立っておられたのです。そう考えるのが自然ではありませんか。所詮、貴方には手の届かない世界に暮らす方なのです。だからすっぱりと諦めて、これまでどおり正義のために身をお捧げなさい。
「厭」と、もうひとりの明子が耳をふさぐ。
「どうかしたの、明子」母が愕き近づいてきた。
我に返って、「いえ、なんでもないの。人の声を喧しく感じてしまって――ここは音が響くから。もうすこし歩いてきます」
「間もなく汽車が」
「ほんのすこしだけ」と応じて、ふたたび歩きだした――老若男女の波のなかへと。
母に残した言葉どおり、このたび明子が構内を巡ったのは僅かな時間に過ぎなかったが、そのあいだに二度、公博を見た。
知人の姿を求めているというのは本当だったらしく、うろうろと、人の顔を覗きこんでは小首をかしげている。明子は思わず柱の蔭に身を隠した。否、自分の視界から公博を隠した、と云うほうが正しい。苦しかった。
駅員が鐘を振り鳴らし汽車の到着を告げはじめた一方で、二度目の遭遇があった。今度は両掛けのベンチを隔てたきりの距離だったが、公博が捜しているのは男性なのだろう、明子には目もくれなかった。間に並んで坐っていた父子か、或いは手代と小僧か、ともかく年若いほうが目深に被っている鳥打帽子には、暫く視線を落していたというのに、その先に立つ明子へまでは延ばさなかった。
そういえば梅園で彼の口にのぼったのは正しく鳥打帽で、その落した帽子と似ていると感じていたのかもしれない。小僧は風邪でもひいているのか、下に着込んで膨れあがった銘仙絣(めいせんがすり)に、深々とした襟巻。やがて横の中年に促され立ち上がったその頭は、明子の目よりもすこし低く、帽子の様はよく見て取れた。ゴルフに向かう公博の頭を包んでいた、あの帽子との比較であれば、色は近いけれど似ても似つかぬ安物だった。明子にもそれくらいは分かる。
小僧がこちらを見上げすらしなかったのに対し、山高帽にトンビを着込んだ中年男の目には、モダンガール然とした断髪洋装が珍しかったらしい。大きな旅行鞄を提げているくせに、振り返ってまで、銀縁の眼鏡の向こうからじろじろと眺めてきた。
上から下、下から上へ、舐めまわすような不気味な視線で、さしもの明子も怖気が立った。両親の許へと走り戻った――。
「背が高過ぎるのが、難と云えば難だが」と山高帽の男が、猫背になり小僧に囁きかけている。「それを差し引いてさえ、むしゃぶりつきたくなるような、頗る付きのいい女じゃないか。そうは思わんかね」
「そう思います。山崎様」
「しかし鼻ッ柱が強そうだ」
「はい。山崎様」
「俺を軽蔑するように見返してきやがった。折檻が必要じゃないかな」
「その通りです。山崎様」
「同じ汽車で東京へお帰りと見た。いつの日か、飛んで火にいる夏の虫とばかり、俺の手許に飛び込んできたりは――さすがにしないか」
「はい。山崎様」
「いや、そういう椿事が起きないとも限らん」
「そう思います。山崎様」
「そしたら薬を嗅がせて眠らせて、縛りあげて梁から吊して――そう、別に妻にする訳じゃないのだから、取り返しのつかないほど傷つけたって構やしないのだ。鞭を振るって皮膚を破ろうが、火箸で燒印を入れようが、刃物で肉を切り裂こうが――ふふふ、想像するだけでぞくぞくしてこないか。ねえ玲子」
「その通りです。山崎様」
「その返事は珍妙だ。ぞくぞくしますと云いなさい」
「ぞくぞくします。山崎様」
「良い子だ」鳥打帽と襟巻の間に覗く深い琉璃色の輝きに、男は唇を寄せた。「その調子で東京までおとなしくしているんだ」
「そう思います。山崎様」
「その返事も――まあいい」男は帽子の鍔を引き下ろした。密かに念仏をとなえるような、一層の小声になって、「人いきれで熱かったり、吹き込む風で寒かったり、いつ来ても駅というのは不快な場所だ。いや熱海という土地全般、避寒によかろうと訪れてみたものの、俺の相には合わぬようだ。別荘の造りは開放的だし、庭を他人が歩きまわったりもする。引き払いどきだったよ。早く塀に囲まれた我が家に帰りたい。お前とふたりきりの、夜の世界へと」
「はい。山崎様」
プラットフォームへ、吸われては左右に溢れる人の濁流が、ふたりを呑み込み、包み隠す。
三人とも朝から酔っ払っているらしい。通路を挟んだ座席で三人の紳士が盛んに駄弁っているのを、初め明子は不愉快としか感じなかった。このまま彼らが寝入りもせずに延々と今の調子でいたならば、その声量は公衆道徳に反します、とでも注意してやろうと肚を括っていた程だ。
ホテルでも度々見掛けた紳士たちだが、むろん明子は名も知らず、また今後教えられたところで即座に忘れてしまう自信もあった、事件と関わらないかぎりは。三紳士は揃いも揃って、そう――例えば明子が閨秀(けいしゅう)作家であったとして、名付けるのも面倒で端からABCで済ませてしまうような人々であった。顔かたちといい服装といい話題といい、爪の先ほどの興味も抱けない。公博と同じ生き物だというのが信じられない。
尤もそれは、彼らの口から桜小路の名が発せられる迄の話である。耳にしたが早いか明子は息を殺し、居眠りを装って通路側に頭を傾けた。
「カーテンが捲れたと思ったら、きっとこちらを睨みつけてきたのが、まさに桜小路の坊ちゃんさ」と先刻の体験を語っているのは、B――否、乙津二助である。「初対面という訳じゃあないが、無礼者、とでも叱咤されまいかと、いささかびびった。なるほど身分相応の威厳をお持ちだ」
「しかも堅物とくる」と丙部三五郎。略するならばC。
甲賀一助が噴き出した。「どうしてどうして桜小路の若殿は、くだけないものか」
「しかしさっき迄の話だと、三十路近いというのに浮いた噂の一つもないそうじゃないか」
「頭を使えよ。世に並み居る女になんざ、とうに昔に飽きていらっしゃるんだ」
三五郎は悄然となって、「じゃあ男か」
「考え過ぎだ。下情には、通じすぎたものさ。横浜の例の所へ、始終遊びに行く位いだもの」
横浜、と三五郎は呟いたあと、はっと愕きを露わにして、「南京町の方へかい?」
「さうよ。あのどん底へ、お出入りさ」
「まさかと思うが、一体、君は本当を喋っているんだろうな」
「そこは我輩が保証しようじゃないか」と二助の作り声。「やはり、マリーに参っているんだそうだ。全く、面白い女だからなあ」
「マリーって、支那人と毛唐の混血児(あいのこ)で――」
「琉璃玉の付いた――」と二助が続ける。
「白金の耳輪をした――」と一助もまた続ける。
「凄腕なそうだね」
「そうだね、は情けないね」と得意げに云うAは、どうやら三者のうちでも遊び慣れているらしい――と、さすがに明子の耳にも三者の声が聞き分けられてきた。「一度行き給えよ。水っぽい日本の女に、さよならして、南京町へ行き給え。殊に、濃情の美人、マリーの許へね」
「こんな話、若い伯爵の耳に入ったら、大変だろうなあ」マリーとやらとの、過去の情事でも思い返しているのか、Bは下卑た笑いを隠そうともしない。
「それは、早合点すぎるよ。悪びれる必要の、いずくにかあらん。マリーは、まだ伯爵夫人じゃないんだ。我々の友人、売笑婦さ」
そうだそうだ、というけたたましい歓声には、辛抱の塊のごとき岡田検事も、さすがに大きな咳払いを重ねて警告を発した。それに起こされたような顔つきで頭を起こした明子は、すぐさま微笑で周囲に応じたけれど、双眸には以前の彼女が無縁であった、一種異様な輝きがやどっていた。
南京町のマリー――琉璃玉の付いた耳輪の女。
私は忘れない。
同じ頃、公博は過日と同じく馬に立木に繋ぎ留め、蒼い西洋館への道を急いでいた。
唐人髷の娘――いや、今は姿を見られずともよい。まずは帽子を――鳥打帽を取り戻さねば。
異変には、間もなく気づいた。館の生垣に接する、ずっとまえの時点だった。
そこでまず公博のとった行動は、近くの電信柱に身を隠すことだった。というのも――。
窓という窓が、重厚な天鵞絨(びろーど)のカーテンによって塞がれていた筈の館だ。ところが今朝、いっとう最初に目に入ってきた二階の窓に、その色が無いのだった。
かといってあの娘や、変態性慾の男らしき影が見えるでもない。硝子の向こうには、ただがらんとした薄闇があるばかり――すくなくとも公博の位置からはそう見えた。
彼は数分間にわたって、辛抱強くその一つの窓を見つめ続けた。云わば、悪い予感との最後の戦いだった。
漸く蔭から離れた際には、もしこれが判断違いで、例えばあの男が不意に焼け火箸で襲いかかってきたにせよ、抱いているこの予感が的中するよりはましだという、捨鉢な程の気でいた。
果たして、次第に眼前に現れた洋館の全容は、公博が脳裡に描いていたとおりだったのである。凡てのカーテンが半開きか、もしくはすっかり開け放たれていた。
そんな真似をする必要性があるのは、まず灯りがとれない、即ち電力が通じていない場合のこと。そして、それでも屋内で作業せねばならぬときのこと。
移転。
生垣の隙間から、ぼんやり覗き見える屋内には、未だ家具が調っているようだ。しかし貸別荘だとしたら最初からの備品に過ぎない。
家人に姿を見られるのを怖れ、これまでは一度も足を運ぼうとしなかった、館の正面へと公博は進んだ。遠目に、鉄の門からして、だらしなく開いているのがわかる。そこでもう充分に落胆をおぼえていたものの、門扉の端に引っ掛けられた物体を目にした瞬間、彼は更に打ちのめされて、ああ、と掠れた声をあげたのである。
鳥打帽子だった。
(この項 了。次回掲載3月中旬) |
|