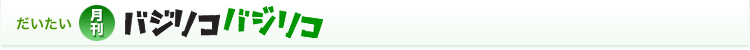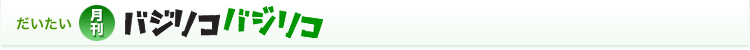「坊ちゃんの身になにか御座いましては」と付きまとうホテルの者を、「子供ではない」と叱りつけた。馬の腹を蹴って一気に引き離し、もう充分だと感じても猶(なお)、疾走を続けた。
振り返ると相手の馬はもはや豆粒、追ってくる気配もない。安堵して丘へと進路を変える。
――夜のベッドで、公博は昼間の記憶を反芻している。脳裡に展開する映像が彼を愉悦へ、そのうち苦悶へといざなう。思惑が当たり、過日はちらりとしか望めなかった窓の向こうの白きかんばせを、じっくりと観賞できたまではよかった。しかし得られたのは眼福のみではなかった――。
蹄の音で辺りの住人を驚かさぬよう、手前の林で馬を降り立木に繋ぎ、あとは歩いてあの蒼い別荘へと向かう。愚かしい、と公博は内心で自分を嗤った。
妙齡の貴婦人たちからのそれとない、いや赤面するほど露骨な誘惑でさえ、頑(かたく)なに身を躱(かわ)すのが常だ。無論、より若い時分は、相応の女性との恋に夢中にもなった。家柄、学歴、嗜み、贅を尽くした装い、優雅な口調と、上目遣いの笑顔――そういった諸々との交遊が青年に残したのは、実社会では無用な無数の知識と、身を捻られるような不気味な思い、即ち彼女らへの不信感だった。只の一度として彼は、女たちの真意に触れた気がしなかったのである。
長い睫に彩られ弓なりに細まった眼を輝かせているもの、それが公博のいずれ受け継ぐ権威と資産であるのは明々としている。なのに貴婦人たちはおくびにも出さず、ひたすら彼の気品と人柄を誉めそやした。家の威光に照らされない間の自分など、退屈なお人好しに過ぎないと考えている公博にとって、それらは手間暇かけた虐待にも等しかったのである。
失意は青年の心を低徊させ、身を悪所へと走らせた。乱痴気騒ぎ、かりそめの情と戯れ、阿片の幻想――明けてタクシーの窓越しに旭(あさひ)を浴びれば、もはや夜への後ろ髮は無く、屋敷で風呂を使い惰眠を貪(むさぼ)った後は、魂の隅々まで清潔な貴公子に戻った。自分でも不思議なほどだった。
遊里の女たちは身なりも言葉も卑しいが、少なくとも開けっぴろげに心を見せる。彼の身分を珍しがり、その躯に触れて喜悦の声をあげ、欲しい物を云っては小遣いをねだる。籠の小鳥より野鳥のほうがどこか神秘の感を与えてくれるように、女たちは青年の目に物珍しくも愉しくもあった。上辺を飾っているかいないかの違いこそあれ、女性とは所詮その程度の生き物、という確信が心に深く根づいている。
その公博が――女という女の本性を見切ったつもりでいた貴公子が、今は一瞬捉えたかぎりの小さな顔に胸を高鳴らせ、灯蛾よろしくその窓に吸い寄せられている。また逢えますようにと神仏に祈ってさえいる。哀れなるは高潔な女探偵明子の遅い初恋。早春の緑洋ホテルに綻びつつある花は、どうやら彼女の望む庭には無い。恋の手綱が公博に握られているとするなら、それは思いもよらぬ日陰においてグロテスクな色香を呈しつつあった。
昨日と同じ窓に、人の顔らしき白い影。公博の足取りはあたかも夢遊病患者のそれとなった。家の者に見つかったなら、紳士にあるまじき覗き見として糾弾されるのではないか。予感が胸を過ぎる。しかし足は止まらない。生垣に寄り添っても飽きたらず、枝の間に頭を突っ込んで、頭を少しでも窓へと近づけた。
もし向こうから見えたなら、生垣の隙間に男の顔――吃驚仰天して叫びだしてしまう光景だったろうが、娘の顔は上向いたきりである。空の模様に、よほど気をとられているらしい。裕福な家庭と思しく、髪は古風で子供っぽい唐人髷(とうじんまげ)である。その喉から顎にかけての曲線が、昨日の記憶そのままであることに気づいた公博の脳裡を、ひょっとして――と奇想が過ぎった。人形? 持主によって気紛れに飾られ片づけられるだけの活人形に、自分は想いを寄せてしまったのだろうか。
娘の顔には蒼い紗(しゃ)がかかり、未だ細部は瞭然としない。硝子が空の色を映しているのだった。表情に苦痛の歪みが生じたような気がし、目を瞬かせてみれば、空の雲が様子を変えたに過ぎない。頬に傷が走ったという錯覚は、空を渡る鳥影の為せる業だった。同時に、公博の視覚は確かに捉えた――鳥の動きに合わせて娘の顔が幽かに向きを変え、くっきりとした黒目が揺れ動いたのを。人形ではない。生きている。
不意に娘は窓から消えた。芝居の大慌ての幕切れよろしく何者かの手でカーテンが引かれ、一切を覆い隠してしまった。カーテンはしばらく波打っていた。
――荒々しい余韻は公博の胸を騒がせ、薄暗い想像力を掻き立てた。今のが令嬢に対する扱いだろうか。いかに了見の狭い親であれ、いったい愛娘がただ空を眺めるのを咎めるだろうか。陽を浴びると身に障る病にでも? それとも継子苛めか。
令嬢ではないのだろうか。せいぜい十六、七――いやもっと若くも見えたが、はや囲われ者の身空か。とすれば親に売られたか、それとも悪漢に勾引(かどわ)かされたか。
毛布の温もりによって夢の入口まで運ばれるたび、色鮮やかな妄想が去来して、思わず瞼が開く。その繰り返しである。むくつけ男に嬲(なぶ)られ、呻き声をあげる唐人髷の娘。切れ長の眼の奧底には、怯えと悦びが入り混じっている。逃げだそうと決心すれば可能だろうに、そうしないのは弱味でも握られているのか。それとも旦那の歪んだ愛を、娘なりに感謝して受け容れているのか。
頭を振って身を起こし、電気スタンドの紐を引く。切子の水差しに手を伸ばして、中身が空っぽなのに気づく。ホテルの者を呼ぼうとしたが、考えなおして書きもの机の前に行った。夜食のチーズや果物と一緒に運ばせたワインを、だいぶデカンタに余らせている。
マニラ産のシガリロを燻(くゆ)らせ、グラスを傾けながら、公博は独り笑いした。なんと愚かしい。妄想を推理してどうなる。やがて胸苦しさを感じて、今度は病人のように喘いだ。置時計に視線を遣る。針は深夜過ぎを示している。あの娘はどう過ごしていよう。夢路を逍遥しているのか、それとも旦那の肌の下か。
デカンタが空になる頃には、公博はすっかり探偵気分に囚われて、娘にまつわる真相を見届けるのを自分の使命と感じるまでになっていた。箪笥(たんす)を開き、寝衣(ねまき)を脱ぎ捨ててシャツを羽織りツイードに脚を通す。闇に紛れやすい黒カシミアのセーターを纏い、鳥打帽を目深に被って部屋を出た。
ロビーを大股に横切っていると、夜勤の受付係が即座に気づいてカウンターから飛び出してきた。「お出掛けで御座いますか。お車を手配致しますか」
「いいえ、すこし外の空気を吸いたいだけです」とにこやかに応じた。「このホテルの暖房は客に季節を忘れさせてしまうね」
「お暑いですか。すぐ係の者に伝えまして――」と踵(きびす)を返そうとするのを、
「いい、いい」と引き留めた。「そういう意味で云ったんじゃない。室内も快適ながら、梅の香をはらんだ夜風は、さぞ芳しかろうと思い立ったんだよ」
「庭には暗い場所が多く御座いますが、角灯(ランタン)を用意させましょうか」などと云いながら、ドアの外まで付いてこようとする。
已(や)むなく厳しい口調で、「考えごとをしている。独りにしてもらっていいですか」
「失礼致しました」相手は頬をはたかれたような顔つきで引き下がった。
熱海とはいえ早春の深夜は冷えた。花の匂いを楽しむどころではない。外に出た公博は目的とは逆方向に進み、建物をぐるりと大回りしてから丘の側に出た。外灯はないが宵っ張りたちの窓灯りで、かろうじて足許はわかる。いくぶん緩やかな斜面に目星をつけると、彼はいま再び、蒼い西洋館を目指して丘を上りはじめた。
ゴルフ靴を履いてきたお蔭で、足許は過日よりずっと確かだ。しかしホテルから離れる程に闇は深く、不意に灌木(かんぼく)に顔をぶつけて声をあげもした。また上りはじめたときは最短の角度を選んだつもりでいて、小径(こみち)に出て下方の灯りを望んでみれば、どうも建物の見え方が前回と同じである。いつしか遠ざかる方向に上っていたようだ。かぶりを振って無駄骨を自嘲する。
そろそろと小径を進み、時間をかけて別荘に達した。遠目にまた、昼間立った生垣の隙間から覗いてみても、灯りの洩れ出ている窓はない。公博は愈ゝ(いよいよ)大胆に、フェンスを跨ぎ木々の枝を分けて庭へと入り込んだ。うっかり開けられたままの戸口や、様子を見て取れるカーテンの隙間がないものかと、洋館の周囲を慎重に巡りはじめた。
時折、雲間に月が顔を出す。その冷たいあかりだけが頼りだった。どこかで盛りのついた猫が長い声をあげ、公博は不吉な思いで立ち止まる。犬にも馬にも愛着があるが、どうも猫は好かない。腹がわからない。
南京町のマリーの店に、老いて眼も耳も利かなくなったペルシャがいて、これなど人の気配を察してくれないからどこに鎮座しているか知れず、ぎょっとさせられる。獣の勘を頼りにテーブルや戸棚の上まで辿り着いて、そこで不気味にじっとしている。あんまり動かないので、ついに死んで剥製になったかと、触れかけて、寸前に跳び退(の)かれたことがある。猫も驚いたのだろうが、公博も床に尻餠をついた。
また猫が啼く。公博もまた、ふたたび立ち止まり、やがて引き返しはじめた。猫ではないかもしれない。まさか。
未だ確かめていなかった方角の高窓が、うっすらと黄色い光を放っているのを見つけた。覗けるだろうか――背伸びすれば、かろうじて指先が届く。
迷わず飛びつき枠に指を掛け、渾身の力で身を引き上げる。汚れた硝子越しに、天井が見えた。壁が、ドアが――指の力を補って枠に顎を掛け、次いで片方の肘を――。
奇妙な熱情にかられていなければ到底発揮できないであろう剛力でもって、公博はついに窓枠に両の肘を掛けた。英雄的というには余りにも狂信的な奮闘。その先に待ち構えていたのは、彼のベッドの中での悪夢的妄想を凌ぐ、驚嘆すべき光景だった。
高窓は、納戸として使われているらしい小部屋のものだった。開け放たれたドアの向こうに廊下が横たわり、その更に向こうには、暖炉に火の入った絨緞敷きの洋間が見える。灯りは煉瓦の内の炎だけだ。
前に二つのシルエットがある。片や着流しの、痩せた男の立ち姿。顔には眼鏡の輝きがある。
いま一方の影は、跪(ひざまず)いている唐人髷の娘。暖炉の火が爆ぜて、一瞬そのさまを仔細に浮かびあがらせる。長襦袢ひとつのしどけない姿で、不自然に身を細めている。後ろ手に縛られ、膝も括られているようだ。口には猿轡(さるぐつわ)を噛んでいる。公博が猫の声と聞いたのは、発語を禁じられた娘が、懸命に鼻から洩らした悲鳴であった。
男が暖炉に向かい、背を屈(かが)める。やがて娘に迫ったその手には、焼けた火箸が握られていた。赤く耀(かがや)く先端を娘の頬に近づける。やめろ、と公博は苦しい体勢で口走ったが、くぐもった悲鳴にかき消された。娘は身を仰け反らせ頭を振り、言葉とならぬ叫びを重ねに重ねた挙げ句、不図、絨緞に倒れこんだ。はっと息を呑み目を見張る公博。しかし火箸は慎重に娘から遠ざけられていた。熱さでも痛みでもなく、恐怖の念により失神したようである。
男はいささか慌てた様子で火箸を暖炉へ戻し、いったん公博の視界から去った。戻ってきた手には手巾(ハンケチ)が握られていた。男は片膝をついて娘の頭を抱え、鼻先でそれを振った。気付けのようだ。
娘の身がびんと反る。頭が動く。手巾を放り猿轡を解きながら、男は娘に語りかけている。硝子越しの小声で、殆ど母音しか聞き取れなかったものの、想像によって補足するならば、恐らくこのような科白であった。
「冗談事に決まっているだろう、――子。なんで大切なお前を疵物へなどするものか、満願成就のあかつきには、晴れて私の妻となるお前を」
次いで男は、娘の身を前のめりに倒した。手の縄を解いてやるのかと思いきや、その見当は外れた。男のとった行動はそれまでにも増して奇怪だった。娘の後ろ手に顔を寄せ、その指を一本一本、まるで子供が棒飴を与えられたような懸命のていで、丁寧に舐(ねぶ)りはじめたのである。
茫然となった公博の、腕からも肩からも一気に力が抜けた。おかしな姿勢で地面に落下して、そのまま仰向けに転がった。腕をひどく捻ったのが分かったが、痛みを感じない程の自失ぶりであった。再び高窓に這い上がる力もなく、それから随分と長いあいだ、雲に嬲(なぶ)られては形を変える月を眺めていた。
ロビーで鉢合わせにぶつかりかけた。
失敬、と仕事中のような調子で詫びてから、相手が公博なのを見て取った。途端に表情が霽(は)れ、まあ、と声音まで女らしくなった明子である。「ごめんなさい。余所見(よそみ)をしておりました」
いえ、と彼のほうもうわの空で云い、それから知った顔と気づいて微笑した。「どちらにお急ぎですか」
女らしからぬ大股歩きを注意されたと感じ、明子は赤面した。「べつに急いでは――東京へ帰るまえに、もう一度梅園まで遠乗りにと思いまして、これから乗馬の支度を」
「もうお帰りに?」
「ええ。父が急の仕事で呼び出されてしまい」
「いつお立ちですか」
「明日、朝一番の汽車で」
「おや、では僕の両親も一緒です」
「御両親だけ? 公博さんは」
「僕はもうすこし、のんびりしていますよ。いま東京に戻っても閑(ひま)を持て余すばかりだ」
「そう」と明子は落胆した。なにか口実をこさえて、自分だけ滞在を延ばせないものか。しかし切符はもう手配してしまった。
「明子さんまでお帰りとは、困りましたね」
「どうかなさいました」
「まだゴルフをお教えしていない」
憶えていてくださった。その事実だけで彼女の心は浮き立った。
「弱ったな。今からでもお教えしたいのに、昨夜、左腕を捻挫してしまいましてね。大した痛みではないんですが、クラブを振るのはちょっと」
明子は思わず手を突き出し、「どうかお大事になすってください。ゴルフはいつかの機会に」
「しかし、またお会いできるとも限らないし」
「いつでも東京探偵社に御連絡を」思わず身分を明かしかけ、はっと口を被う。
「探偵社?」と、やはり怪訝な顔をされた。
「その――事務員として勤めております。岡田明子を、とお呼び出しください。それで通じます」
「探偵社とはまた、今や職業婦人は珍しくありませんが、それにしても風変わりな――失礼、もちろん悪い意味で云ったんじゃありません。複雑な現代に欠くべからざる業種だと分かっているつもりです。官憲が凡てを解決してくれる訳ではありませんからね」
「父が社長と懇意で、それで」と仕事の話題を濁したうえで、「あの――職場のお話なんかより、でしたら如何でしょう、ゴルフの埋め合せに、これから梅園までお付き合いくださいませんこと」と軽い思い付きめかして提案した明子だったが、無論その筈があろうか。この語らいを一分でも一秒でも長引かせたく、上着の裾に縋り付くような心地で口にした科白だった。
「いいですね」と公博があっさりと乗ってきたので、却って面食らった。「僕も着替えてきましょう」
「でもお腕が。自動車で参りましょう」
「お楽しみの予定を変更するには及びませんよ。馬なら慣れていますから右手で充分です。それに左手だって使えない訳じゃない」
互いに部屋に戻って乗馬服に換え、各々のお気に入りの馬に跨りホテルを出た。公博は巧みに片手で手綱を捌いて、明子の見る限り一度も左手を使わなかった。あたかも既に結納を交わした男女のように、梅園前の草地に達した二人は、互いをいたわりながら馬を降り、手綱を立木に留め、肩を並べて梅の木の狭間に入り込んだ。甘酸っぱい息苦しい迄の香気は、多幸感に酔った明子の頭をいっそう朦朧とさせた。乗馬靴越しの地面が、ふかふかと蒲団でも踏んでいるように覚束ない。
「明子さんのようにお美しい人には、きっと素敵な恋人がいらっしゃるんでしょうね」公博が遠い花々を眺めがら、漫ろに云う。
「おりません」思わず大声をあげた。
「それは失礼」と吃驚した顔で見返され、
「すみません。今――いまちょうど木の根に躓いて」と懸命に取り繕う。息を整え、改めて、「外聞より、それなりに忙しい仕事ですの。殿方のお目にとまる機会なんて、望みようがございません」
「職場は男性だらけでしょうに」
「既婚者ばかりです」
「勿体ないお話ですね」
そう述べながら公博が見せたアルカイックな微笑が、追跡の専門家たる明子を愈々迷子にした。いま彼女は職業上の知識を総動員して、貴公子の本心を見出そうとしている。
梅園の半ばまで歩いたところで不図、気は先へと急いているのに脚がもつれて伴わない、常ならぬ感覚をおぼえた。身を過度の緊張が満たしている。公博へと顔を向けると、彼もこちらを見ていて、
「お疲れのようだ。歩く靴ではありませんからね」と優しい言葉をかけてきた。「入口近くに掛茶屋があった。あそこまで戻って休みましょう」
来た道を戻り、茶店の縁台に並んで掛けて、甘酒をとる。その仄かな酒気にも、この日の明子の頬は火照った。
梅花の色を夕空や貴石に譬えたり、時折の風の冷たさに、平気です、無論僕も、と意地を張り合ったりと、差し障りないやり取りがあって、それから、どちらともなく默り込んだ。いつからか公博の顔が、自分の側に向いたきりであるのを意識した明子は、いましも接吻を受けるのではないかとあらぬことを考えた。しかし盗み見る彼の眼差しは、どうも虚ろである。同じ方角に顔を向けると、梅林の切れ間に、緑洋ホテルが寄り添っている小高い丘が細く覗いていた。
思い出したように明子に視線を戻して、「春ですね。いや、ホテルからついて来たのかな」
小首をかしげた。
「お上着の肩に、蜘蛛が」
見れば、指先にとまれる程の小さな蜘蛛が、乗馬ジャケツの肩口にしがみついている。明子は手で払いかけて急に思い直し、きゃ、と発して公博に肩を寄せた。いささかわざとらしい態度ではあったけれど、公博はそうなるのを予期していたように彼女を柔らかく受けとめ、むしろ深く引き寄せて、
「刺しはしませんよ。だいいち息で吹き飛ぶ程の大きさだ」と笑った。それから本当に首を伸ばして、ふう、と息を吹きかけてきた。明子の喉を掠めた。「ほら、どこかに飛んでいってしまった」
彼女は身動きの術を失っていた。はしたなく思われるのは怖いが、自分から寄り添っておいて押し退けもできない。そもそも全身に力が入らない。五官からも第六官からも現実感覚が遠のいて、羊水のなかを、あるいは宇宙空間を漂っているような気がする。限りなく不安で、同時に、とろけそうなほど幸福だった。おのずと瞼が落ちて、自分が目覚めているのか睡っているのかも定かではなくなった。唇は温もりを待った。
「帽子を」
耳に飛び込んできた言葉は、しばし意味を成さなかった。ボウシヲ――帽子?
振り払われた。とつぜん立ち上がった公博を、明子は呆然として見上げる。
「帽子を落してきた」
「公博さま――公博さん」降って湧いたる不条理に、明子の声は掠れた。「お帽子でしたらそちらに」
彼女が云うように各々の乗馬帽は、一対の狛犬よろしく縁台の両端にある。
「違う、それではない」貴公子は叫ぶ。目の前にいるのが何者かを失念しているような、強く高圧的な調子であった。「鳥打帽――窓の下に落してきてしまった」
(この項続く。次回掲載2月中旬) |
|