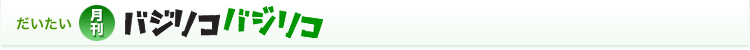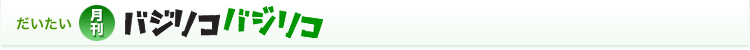日本の女性は、きものの下にはもともと何もはいていなかったが、パンツ(もともとはズロースといわれていたと思うが)をはくようになったのは1932年(昭和7)東京日本橋の白木屋の火事がもとになっている。ちょっと物を知っていそうな方はみな、そういうのだ。女性は当時、みなパンツははいていなかったため、百貨店白木屋の火事の折、和服を着ていた女性従業員は、すそを気にして飛び降りることができず、多くの女性が犠牲になった。これをきっかけに、女性はみんなパンツをはくようになった、というのだ。まことしやかに、言い伝えられている。きもののころは何もはいていなかったんですよね、などという話をすると、多くの方は「白木屋の火事がきっかけにはくようになったんです」とおっしゃる。
でも何だか変だ、とずっと思ってきた。いのちがかかっているのですよ。そこで飛び降りないと、いのちがかかっている時に、すそが乱れるのを気にするだろうか。というか、それくらいのすその乱れを気にするのであれば、とうの昔に女性は下着をつけていたのではないか、とつねづね思っていた。
はっきりいって、女性が下着をつけていなかったのは、そのほうが快適だったからだし、少々、ときおり見えようが、かまわない、という認識があったからこそ、その快適さを続けていったのではないか、と思う。だいたい、おばあちゃんたちは、野良でも道でも、40代後半であるわたしの記憶にある範囲で、「立小便」をしていた。おしりをくるっとからげて、突き出し、おしっこをしていたものである。
ちょっと前まで、日本の家庭のお便所には汲み取り式のしゃがんで用を足すための便器と、男性の小用につかう「あさがお」という小便器が両方あった。それは「トイレ」ではなく、「便所」であった。お便所の戸をあけるとそこには「あさがお」があり、もうひとつ別の戸をあけるとしゃがむ便器があった。今の合理的家屋では、そんなに贅沢にトイレのスペースをとることはできないので、洋式便器が一個あるか、もっとせまいと、ユニットバスとして、風呂場と一緒になっている。ふたつも便器をつける、なんて贅沢のきわみだ。洋式トイレでは、男性が小用を立って足すと、汚れやすいので、「男は座っておしっこするように」という指令を出されている家が結構多いらしい。昔は別の小便器があったのに、ご苦労なことである。男性が座っておしっこしないといけない、というのもなんだかさびしいのではないだろうか。しかしそれもまた、文化的なもので、イスラム圏の男性は座っておしっこされるようである。現地に暮らした方によるとそのほうが「きれ」がよいのだとか。そういうものか、と思う。
とにかく、日本の以前の家屋には「あさがお」という小便器があった。そしてそれは男性専用、だったわけではなかった。うちのおばあちゃんは、「あさがお」でおしっこしていた。「あさがお」に背をむけ、やっぱり、おしりをくるっとからげて、突き出し、おしっこをしていた。戸なんかあけていても平気だった。だから、わたしが知っている。
こうやって女性が「立小便」するには、それなりのスキルが必要である。今の女性がやってみても、きっとうまくいかないと思う。おしりをからげて、突き出して、おしっこして、汚さないためには、おしっこはとても勢いがよくないといけない。ちょろちょろ、足にたれてしまっては、よごれてしまう。そして、このおしっこの勢いのよさ、というのは骨盤底筋群の鍛え方と関係があるのではないか、と思っている。
骨盤底筋がしっかりしているので、わたしたちはトイレで用をたすことができる。腹圧性尿失禁という、くしゃみしたり、せきをしたときにちょっとおしっこがもれる、というのは骨盤底筋がたるんできている、ということだ。日本の昔の生活では、骨盤底筋が鍛えられるようなことが日常所作にくみこまれていた。しゃがむ、という姿勢がよい。いわずとしれた、和式トイレ、しゃがんで洗濯、しゃがんでかまどの具合をみる、など、昔はしゃがむことが多かった。正座も、廊下の雑巾がけも骨盤底筋を使うし、きものを着ること自体が骨盤底筋トレーニングでもある。からだをゆるめて、中心軸をすっと意識するときれいに着られるが、これは骨盤底筋を意識している状態に近いと思う。「小股の切れ上がった」姿勢は、骨盤底筋をひきあげているような感覚の姿勢ではないか。つまり、骨盤底筋がよく鍛えられた昔の女性だからこそ、おしりをからげて、おしっこしても、汚れなかったのだ。今の女性に「おしっこの勢いがよいか」どうかきいてみるといいのではないかと思うが、「尿漏れパッド」が商品化されているような現在、すっごく勢いのよいおしっこをしておられる方は少ないのではあるまいか。こういう女性たちはきっと「立小便」できないと思う。勢いよくないおしっこでは足をよごしてしまうだろう。
つまり、昔の女性は、よく「立小便」していたのである。そして、それは、人目にふれていた。そんなことをしていた女性たちが、いのちとすその乱れを等価のものとして扱うとは到底思えない。「飛び降りなければ命が危ない」ところで、すその乱れを気にしたのではないか、というのは、どうやらあとからつけられた理由ではないか。
と、常々思っていたら、こういうことについて研究された方があった。井上章一さんの『パンツが見える』という本によると、白木屋の火災で無くなった従業員の大部分の死因は間違いなく飛び降りたことによるものである、という。亡くなった従業員のほとんどは「ロープが焼ききれた」「友人と一緒に死んだ」などといわれており、「すそを気にして躊躇して飛び降りられなかった」ということはない、と調査しておられる。ただ、火事のあと、記者会見した白木屋の幹部が、いざ飛び降りなければならない、というときに、下着をつけていないと、躊躇することもあるだろうから、これから女子従業員には下着をつけさせたい、というようなことを話し、その後、実際にいわゆるズロース、が広がっていった、ということらしい。実際には、そういうことがあったわけではないが、おそらく、そういうこともあるのではないか、と思うから、これからは女性にズロースをはいてもらったほうがよいだろう、という経営側の判断、とも言うべきコメントから、西洋下着着用が広まった、ということ、である。
そう思えば、「すそを気にして飛び降りられなかった」ことはないが、「白木屋の火事がきっかけとなって、ズロース使用が進められるようになった」ことには間違いがない。ただ、それは「女性の尊厳か、いのちか」などという、女性の側の思いがきっかけだったわけではなく、むしろ、百貨店側の新製品導入、という意向があったのではないか。まあ、理由はとにかく、この1930年代から西洋下着が広まっていった、ということにまちがいはないようだ。
現在、お話をきいてみても、90代半ば以降の方はほとんど「お股」に布が密着する西洋下着をつけておられないが、90代前半から80代の方の多くはズロースをはくようになっておられる。そして、戦後、ブラジャーも普及する。
女性がなぜきものを着なくなったのか、ということについては、いろいろな理由があるだろう。活動的でないから、手入れが大変だから、着るのに時間がかかるから、といろいろに言われていると思うが、わたしは「日本女性がきものを着なくなった」のは「日本女性が西洋下着をつけるようになった」からだ、と思っている。きものは、えり、すそ、脇に空気が通る、さわやかな衣装である。最も発汗するところが外に向かって開いており、体を風が抜けていく。それが気持ちがよいのだ。そして、あたたかく保つべきおなかと腎臓周りは帯でまもられている。そこに、「お股」に布を密着し、乳房を圧迫し、脇をぴったりとさせるシャツなどを着ると、風が抜けなくなる。股、胸、脇、を圧迫しているところに帯を締めると、苦しいだけである。股、胸、脇、があいているから、帯をしても苦しくないのだ。つまり西洋下着はきものの、洗練されたディーテイルをすべてこわしてしまうのである。
今の人たちが「きものは苦しい」というのも、だからあたりまえだ。きもの、というからだに快適な衣装をわたしたちが取り戻すためには、西洋下着を使わなくなる、ということが前提になるのだが、「はい、そうですか」と使わなくなる人は実際にはそんなにいないだろう。習慣というものは、そう簡単には捨てられない。生まれてからずっとオムツ、その後パンツ、を使ってきた人は、ない、とスースーして冷えるような気がして、気が気ではない。ほんとうは腰が冷えていなければ、「お股」が冷えてもだいじょうぶなのだが、気分的に、パンツを捨てるのは抵抗があるだろう。
しかし、いったんやめた人は、もう気持ち悪くて、ブラジャーもパンツもつけたくない、とみんな言う。こういう快適さについて、もっとたくさんの人に知ってもらうのは決して悪くない、と思っている。
『パンツが見える。―羞恥心の現代史』 朝日新聞社
|
|