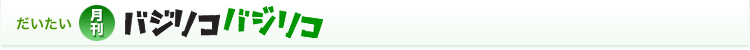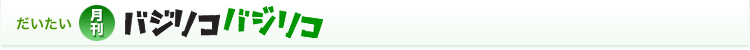「ウチ大阪、好っきやねん」「コテコテの何が悪いのん」「ベタでええやん」。大阪についてこの手の物言いをそれこそコテコテの大阪弁で喋る人間はとても苦手である。
わたしは岸和田の下町で生まれ、だんじり祭で育った人間だが、そういう物言いをする大人は回りには居なかった。ちなみに岸和田での大人は、男なら「おっさん」あるいは「おっちゃん」、女なら「おばはん」「おばちゃん」で、それ以外はいない。
彼らは実生活において「コテコテ」あるいは「ベタ」に生きることを決して目的化していない。結果として彼らの実生活というものが他者から見てそうなるにせよ、誰だって前後に子供をのせた自転車の3人乗りはしたくないし、ホルモン屋やお好み焼きの煙もうもうの2階の部屋には住みたくない。
この「大阪コテコテ&ベタ万歳」的な物言いをする人種は、やたら「〜でんねん」「まんねん」を多発するテレビのバラエティ中心の吉本芸人みたいな人種ばかりで、要するに「舞台」や「高座」といった「街場」に出ないで、大阪のコトを語るから、それがかなわんのだった。
わたしは長い間、『ミーツ』という非常に地元「らしい」京阪神の街の雑誌を長いこと編集していたので、他所の人に「大阪」のことを聞かれることが多い。その他所の人というのは、仕事柄メディアの人が多いので余計に答えが難しい。
しかしこのかた、通天閣やちんどん屋の西成〜千日前テイスト、吉本興業に阪神タイガーズ、エゲつない電照看板、一家に一台たこ焼き器…、などは確かに大阪だが、要するにB級でいちびりでレトロで「過剰なアホ」を大阪とするとらえ方、そのステロタイプまる出しの感覚に、ちゃうんちゃうの、と思い続けている。
同様にとんでもない男に尽くして、それを支え、その実それに依存する「ナニワのおんな」の夫婦善哉、坂田三吉、桂春団治の妻的な物語は、いまなお「大阪で生まれた女やさかい」と「中島らもの嫁」を再生産している。
それはメディア的な、つまりコマーシャリズムによって創られた「大阪」であるといえばそれまでであり、かといって、いやちがう「大阪はやっぱり、人情のまち。エエ街や」などといった、ふにゃけた物言いが「大阪コテコテ&ベタ万歳」に直結しているところに大阪の過酷さがある。
そういう物語を「ペラペラのつくりごとのもんや」として、あえて楽しむ大阪人もいることにはいるが、曾根崎のスナックから聞こえる「なにわ恋しぐれ」は出張転勤族の声であり、有田芳生が『歌屋 都はるみ』で書く、父が在日である都はるみの歌手=芸能人としてのリアリティはそこにはないことを〈生活者〉としての街場の大阪人は知っている。
さてそもそも大阪といっても、そこには摂津、河内と和泉の三国の大阪があり、例えばわたしが中河内の八尾の友だちに盆踊りに連れて行ってもらって河内音頭でよう踊れないのと同様に、その土地ごとの深いテロワール性がある。大阪市の平野のだんじりと岸和田のだんじりは大きく違うし、池田や箕面といった北摂の人間にとっては、それこそ大和川を越える泉州はほとんど蛮地、未知の世界である。
けれども田舎のロードサイドにジャスコやファミレスやファーストフードが幅を利かすような郊外的な土地と、豆腐屋の隣に喫茶店があり、そのまた隣にクリーニング屋があったりする商店街的な〈街場〉の違いは、同じ大阪人のDNAとしてわかる。とくに千里丘陵で行われた大阪万博EXPO'70を知る世代以上なら確実にわかる。それが「大阪」という「違う街が重層的に重なっている」土地の記憶というものである。
郊外的な〈田舎=都市〉は、徹底的に経済合理(至上)主義、つまりグローバルスタンダードなのだろうそのやり方が徹底しているから、のっぺりしていてデオドラントな感じが共通していて、それとわかりやすい。
北田暁大と東浩紀が『東京から考える』(NHKブックス)で六本木ヒルズに見る東京都心の〈郊外化〉を「六本木ヒルズはまさにジャスコ的なわけですね」(p131)と鋭く指摘していたが、われわれ大阪人からすると、あそこは感覚的に、即座に「街場ではない」ということを直観できる。
たとえばその〈郊外〉的なニュアンスとしては、「若いIT長者たちがとりあえずブランド物だとだけわかるTシャツにケミカルウォッシュのジーンズ、サンダル姿で、六本木ヒルズをうろうろしていて、コンビニに入ったり、ドン・キホーテで買い物する感覚」がかならずあることで、それはつまり、そこを訪れる人すべてが交換経済の〈消費者〉として受容され、それはホリエモンであろうが、それを見て帰って地元で「ホリエモンがいた」と吹聴する「おのぼりさん」であろうが、すべてを〈消費社会〉としてがぶりと飲み込む「のっぺりさ」のようなものである。
冒頭の「大阪コテコテ&ベタ万歳的」な物言いは、一見大阪の街場の匂いをさせているが、実は同様に郊外的つまり徹底的な〈消費者〉としてのスタンスである。
その郊外的な「のっぺりさ」は、まさに大阪においての〈郊外化〉なのであるが、これは「一家に一台たこ焼き器」がある家庭は、千里ニュータウンや泉北ニュータウンといった郊外に多く、逆に「コテコテ」の西成や生野、岸和田、尼崎といった下町には少ないことからもわかる。なぜなら、そういう大阪の街場では、たこ焼きみたいなものは、近くの商店街や市場に行けばいつでも食べられるからだ。
そういう意味で「大阪コテコテ&ベタ万歳」言説は、大阪的な郊外の家においての「テーマパークとしての街場ごっこ」に近い。が、「今日は、お父さんが板前。家で手巻き寿司」は気色悪いし、入学式に「学校行事メイク」をしている「VERYなお母さんのタコ焼き」は食べたくない。なぜなら、おいしくないからだ。それは〈消費〉が、〈食〉という〈実生活〉に優先しているからであって、そういうリアルなおいしさ=街的な感覚は、「供給するもの」と「消費するもの」間でなく具体的な〈生活者〉からの双方間でしか生まれない。
街は〈消費〉の場である。しかし、店の主人や女将、店員、料理人、給仕人、ホステス、出前持ち、皿洗い…といった「街場の人」の〈実生活〉の場でもある。
そこでは客は、身なりや言葉遣いが良くて、食べ方飲み方の行儀が良くっても、加えて酒や料理の蘊蓄をしっかり身につけていても、その街や店の「気配」が読めないと、お金を払う分と同等に交換された満足しか得られない。
店の気配というものは、ほかの何所でもないその店で、ほかの何ものでもないその人が、時おり垣間見させる〈実生活〉や〈実人生〉といった代替不可能なものにこそあるが、その気配を読み取ることが、すなわちコミュニケーションである。今日のメニューや魚の種類や野菜の産地やワインの作り手について訊ねたりすることが、店とのコミュニケーションではない。
「礼儀正しい」というのは多分、そういう店の気配を読むこと、すなわち作法を感じることだと思うのだが、80年代以降の日本のシステムは、人と人が出会わなくても回るシステムをつくってきた。
毎日マクドナルドに行っても、1日に複数回ローソンに行くようなことがあっても、その店の馴染みということにはならない。そこは徹頭徹尾、〈交換〉の原理に基づいた経済〜消費社会だ。行儀や礼儀は同一のマニュアルに書いてあり、明日から交代可能なアルバイトたちが「店」をやっている。そして東京でも博多に行っても同じイントネーションの「いらっしゃいませ、こんにちは」は、もちろん大阪キタでもミナミでも、岸和田でも同じで、よく聞けば中国人(あるいは韓国人)の留学生だったりすることが多くなってきた。けれども制服の彼らからは、〈生活者〉という姿はうかがえることがない。
観光客やバラエティ系テレビ言説のど真ん中を行く「大阪コテコテ&ベタ万歳」は、本来は大阪という街の食やコミュニケーションといった〈実生活〉のありようを例えた物言いだったが、逆にリアルなそういう大阪人の実生活を巧妙に隠蔽しはじめた。だからこそ、そういった「大阪コテコテ&ベタ万歳」言説については、どこか居心地の悪さはあるものの「それは、もうええやん」である。なぜなら、牛の内臓を「放るもん(捨てるもの)やからホルモンでええやろ」と客に出してきた大阪人にも、それ以上の自分の〈実生活〉が他人の目の当たりにされ、さらにそれ以上を〈消費〉されることは過酷すぎるからだ。
「吉本たこやきタイガース」のまるでテレビCMのような多幸的で祝祭的なイメージの裏にひそむ言説化されない敗北感や無力感は、「希望と絶望のどちらとも無縁の感受性がそれ自体として高く評価される」(清田友則『絶望論』p210)ポストモダン社会にあって、大阪という街が抑圧しその底に沈殿させてきた澱のようなものであろう。
|
|