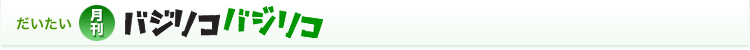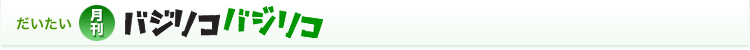私の家は、小学校の近く。時間帯によっては、ランドセルを背負った子どもたちとすれ違うのだが、この頃しばらく見ていない。
そうこうするうち、工事中のシートが張られ、遅まきながら気がついた。そうか、もう、夏休み。
夏休みの花といえばアサガオですね。宿題で観察日記をつけさせられました。終業式の日は上履き袋などといっしょに、素焼きの鉢を持ち帰ったもの。
そしてアサガオといえば、入谷の朝顔市。下町の夏の風物詩、というキャッチフレーズが、行ったことのない私でも頭に浮かぶ。鬼子母神様のいるお寺の境内を中心に、何万鉢もの朝顔が並ぶとか。周辺は車は通行止めで、道いっぱいに人が出て、警察隊が整理にあたるほど、たいへん賑わうものと聞く。
人込みはちょっと億劫ではあるけれど、次なる散歩はそこかしらと、インターネットで調べれば、何、もう終っている? 毎年七月六、七、八日の三日間だとのこと。
私にとってはアサガオは、夏休みに咲く、すなわち八月の花。
まったく江戸っ子はせっかちなんだから。女房を質に置いても初鰹を食べたがる人たちだから、アサガオも本来の「旬」より前倒しで、七月になってしまったのかしらと思えば、それは私の早とちり。入谷の朝顔市は明治になってからのものだそう。
わが散歩ガイドブック『江戸名所花暦』でアサガオを調べると、漢字は牽牛花(あさがお)とあり、続く文章を、少々長くなるけれど引きます。
下谷御徒町辺 朝顔(あさがお)は往古(むかし)より珍賞するといへとも、異花奇葉の出来たりしは、文化丙寅の災後に下谷辺空地の多くありけるに、植木屋朝顔を作りて種々異様の花を咲せたり。おひおひひろまり、文政はしめの頃は、下谷、浅草、深川辺所々にても専らつくり、朝顔屋敷など号(なづけ)て見物群集せし也。
災とは文化三年の大火で、その後下谷御徒町あたりに、空き地がたくさんできていたところへ、植木屋さんがアサガオを植えた。その人がきっとアサガオ作りの達人だったのでしょう。いろいろな花を咲かせ、それが広まり、文政のはじめの頃は、アサガオ屋敷と呼ばれて見物人の集まる家が、下谷をはじめ浅草や深川などにあったとのこと。市とか鬼子母神といった記述はなく、この本の出た文政十年にはまだ、今のような市は立っていなかったと推測される。
いろいろな棒手振(ぼてふり)のいた江戸時代、路地路地にアサガオを売りに来る人はいたけれど、そのアサガオを作っていたのは、下級武士のいわば内職という。
下谷御徒町もその名のとおり徒士(かち)組屋敷があったところで、アサガオが盛んに栽培されていたが、幕府がなくなり、代わって作るようになったのが、入谷の植木屋さんたち。鉢植えにしたものを、近くの寺で観覧に供したところ、評判になり、明治中期には、往来止めをしたり木戸銭を取ったりするほどの賑わいぶりに。入谷の朝顔市は比較的新しい名所なのです。
七月の六から八日に定めたのも、江戸っ子ゆえの気の早さではなく(それもあるかもしれないが)、アサガオの別名に含まれる「牽牛」を、牽牛織姫の伝説である七夕にかけて、その前後にしたとのこと。
入谷の朝顔市の由来はわかった。しかし。終ってしまったなら仕方ない、後の祭りとはこのことだなと残念に思いつつ、なおも探すと、ありました。向島百花園にて、アサガオの市ならぬ展示が、八月まで行われているらしい。
中央線沿いのうちからだと、JR亀戸駅で降り、日暮里行きのバスに乗るのが便利そう。「朝」顔というだけあって、展示は午前中とのこと。十時過ぎのバスに乗る。
通路を挟んで隣の席は、七十代とおぼしきご婦人の二人連れ。窓の向こうに特売セールの赤い文字を見てより、ティッシュペーパー五箱組の値段や品質比べの話を、ずっとしている。買い物袋は持っておらず、レース襟のちょっとおしゃれなブラウスなど着て、行楽ふう。あのかたがたも、アサガオ展へ?
そう読んでいたけれど、同じバス停では降りず、そのまま行ってしまった。バス停が「百花園前」と「ひ」ではじまる名だったからで、「む」と聞こえたら、ブザーを押すつもりだったのではと、少し心配。

塀の向こうがすぐ百花園らしく、内側からセミの声がはち切れんばかりに聞こえてくる。角を曲がると、入り口前はちょっとした広場で、木の幹をかたどったコンクリート製の柱に「健康づくり広場 ラジオ体操会場 墨田区」とあった。立て札ではなく、コンクリート製の柱とは、夏に限らず、通年ラジオ体操を行っているのでしょうか。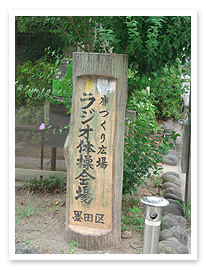
「大輪朝顔展」のポスターに、心がはやる。チケット売り場を兼ねた、瓦屋根を戴く門を通り、何はともあれアサガオへ。
すぐにみつかる。売店の先に、よしず掛けの小屋がある。三方をよしずで囲い、よしずの廂(ひさし)を張り出した下に、青い垂れ幕、白い布を掛けた段々、それが展示台らしい。
なるほど大輪。広げた手の親指の先から小指の先くらいまでありそう。
鉢に立てられた短冊から、陳列されているのは特によくできたものらしいとわかった。優と書かれた金色の短冊の挿してあるのは「万代桃泉」。品種名のとおり、ピンク色だ。秀はいくつかあり、赤紫に近い濃いピンクの「東姫」、薄いピンクの「桜化粧」、水色の「浅黄の誉」……。品種名を見ていると、堀切菖蒲園の記憶と重なる。あそこもほんとうに、いろいろな品種が作られ、雅な、というか、美人ふうの名を付けられていましたね。
陳列台には、同じ大輪でも、二種類の作り方のものがあり、左半分は、素焼きの鉢に竹の支柱を立てて、輪を組んで、それらにつるを巻きつかせた、私たちの知るアサガオに近いもの。右半分は鉢から違って、黒釉(こくゆう)のかかった丼(どんぶり)のよう。そこにはなぜかつるのないアサガオが、盆栽のごとくに植わっている。前者を行灯作り、後者を切込作りというらしい。
見たところ、切込作りで優の短冊のついたものはなく、秀の中で目にとまったのは、水色に白の筋が流れるように入ったもの。その名も「初瀬」。なんと文学的な。歌留多取りでもしたくなりそう。
掲示板には、行灯作り、切込作りそれぞれの評価基準が示されている。前者は花の径が優、秀、佳の順に、二十センチ以上、十九・五センチ以上、十八・五センチ以上、花切れや汚れのないこと、後者は同じく、十八・五センチ以上、十七・五センチ以上、十六・五センチ以上、花が鉢からはみ出ていないことと、厳密。これほど客観的な審査をされているとは思わなかった。公正で、誰もが納得できる方式ですよね。
陳列台の他にも、地面にむしろを敷いて、たくさんの鉢が並べてある。入り口でもらった案内の紙によれば、地元「墨田朝顔愛好会」のかたがたが、約五百株もを展示しているとのこと。陳列台の先に、運動会を思い出させるテントがひとつ。白いズック地の布に黒い字で、愛好会の名を印刷してあり、そちらが詰め所になっているらしい。
覗いてみると、八十くらいと思われる女性と、それよりは少し若そうな男性とが中にいる。種や苗を売っており、買う人や買おうかどうか迷っている人の対応に追われている。
「水やりは二回。午前十時頃と午後は三時前。それ以降はやらない。アサガオは夜伸びますから。そのとき土が水を含みすぎてると、根を冷やして、成長が悪くなるんです」
「他の草だと、暑い昼間に水をやるなんて、煮え湯をやるようだろ? アサガオは、いいの」
さながら朝顔栽培相談会。ですますを交えて、立って一生懸命説明しているのが男性、パイプ椅子に腰を据えているのが女性。厚い瞼と唇が、貫録を感じさせる。
「色? 咲いてみないとわからない。宝籤(くじ)みたいなもの」
そういうものなのか。
夫婦連れの妻の方が、「団十郎、団十郎」としきりに言っており、無知なる私は、百花園のどこかに市川団十郎さんが来ているのかとそわそわしたが、よくよく聞けば品種名。団十郎の代表的芝居「暫」で、柿色の素袍を着(つ)けて花道から登場するが、その色に似た茶色い花のアサガオを、入谷の市で買いそびれたそうで、ここで探しているらしい。
茶色まであるとは。
テントは混み合っていたので、先に園内をひと周りする。この前行った後楽園が、回遊式庭園の最たるものだったので、それに比べ、雑然とした印象だけれど、作り込んでいないぶん、大名庭園とはまた違った趣がある。今はひたすら緑とセミの声とに満ちているが、案内図によれば、秋の七草、萩のトンネルもあるとのこと。その季節にはぜひこなくては。
足もとの地面は、よく見ればセミの穴だらけ。これほど鳴いているのですものね。
面白がってデジカメに撮っていたら、装備からして写真を趣味としている雰囲気のおじさんが、
「こうすると、より臨場感が増すでしょ」
と言ってセミの抜け殻を二匹ぶん、そばの草から取ってきて、穴の出口にわざわざ埋め戻してくれました……。
売店の軒からは、風鈴の音。揺れる「氷」「ラムネ」の旗。「冷たく香ばしい焙煎麦茶」の貼り紙。日本の夏ですね。
売店の人が受話器をとり、「カレーうどん七つ、朝顔愛好会さんへ」と、出前を頼む電話をかけているのを聞いて、テントも一段落したのかと、再び行ってみる。私のしたかったのは初歩的な質問で、切込作りとは、もともとつるを巻かない品種なのかどうか。
男性が答えていわく、そうではなく、つるが出るたびに詰めて、つぼみも二つだけ残して摘みと、たいへんに手がかかる。女性もうなずき、
「アサガオなんてね、幼稚園や小学校でも育てたろうけど、奥が深いよ」
ずいぶん長く作っていらっしゃるんですかと訊ねると、
「三十年」
もともと備わっている貫禄に、言い切る口調が加わって、誇らしげであった。
種や鉢の他、栽培の手引きなる冊子も売られている。ワープロ打ちしたものを、白い紙にコピーし、ホチキスで綴じた、墨田朝顔愛好会オリジナルのものらしい。
「あたしたちがやってきたこと、ここに全部書いてあるから」
メンバーの長年にわたる試行錯誤を通して得た知恵の、集大成であるらしい。惜しげなく伝授して下さるとは、アサガオの審査方法と同じで、なんと公正な。
園の出口近くでは、変化朝顔の苗を配布しており、こちらは愛好会ではなく、事務所すなわち都の公園協会によるもの。百花園のサポーター基金として、一鉢につき百円をお願いしていると、貼り紙にある。
「変化朝顔って、何ですか」
ここでも初歩的な質問をすると、事務所の男性は、写真入り資料で説明してくれた。江戸時代から受け継がれてきた伝統的な園芸植物で、花の色、形、模様、葉などが突然変異したもの。
写真に載っていたのは「桔梗咲き」。ふつうのアサガオが、丸い漏斗状をしているのに対し、その名のとおり、桔梗のごとき角がある。しかも、花の縁だけ白い。もうひとつ写真があったのは「石畳咲き」で、花に切れ込みが入り、五つに分かれて、ひとつひとつの花びらが、長方形ふうで、なるほど畳。こういうのが『江戸名所花暦』に言う異花奇葉?
なぜにそうした妙なものが生まれたかと、アサガオの歴史を調べると、原産地は詳らかならずも、熱帯アジア。日本には奈良時代末期、薬用植物としてもたらされた。その頃、花の色は青のみだったとのこと。そういえば万葉集に、山上憶良が秋の七草を詠んだ歌があり、アサガオも入っているが、それは今のアサガオではなく桔梗を指すと、聞いたことがある。
中国ではアサガオの種を牽牛子と称し、古くから下剤として用いられてきた。日本でも同様だったが、種を使うだけでなく、花にもしだいに美を見いだすようになったのでしょう、安土桃山時代には襖(ふすま)絵や屏風絵、能の衣裳に描かれ、色も青に並んで白が出てきている。
観賞用となったのは、江戸時代。文化、文政には栽培が大流行し「都下の貴賤、園に栽え盆に移して莚会を設く」と、当時のできごとを記した書に綴られたように、階層の別なきブームとなり、品評会もしょっちゅう行われた。
後楽園のところでふれたように、大名屋敷の造成期にあたる江戸時代の前半、庭木が主導した園芸熱は、後半に入るとアサガオやキクといった花卉(かき)に、中心が移り、広く庶民を巻き込んでいったといわれる。たしかにアサガオやキクならば、下級武士の屋敷にも狭い庭にも植えられるし、庭がなくとも鉢植えにして置ける。プロに手入れされた庭を眺めるのと違って、自分で育てる楽しみもある。愛好会の人の言うように、どんな色が咲くかは宝籤のようなものならば、そして形も、ときに思いがけないものができるなら、面白さに病みつきになる人が増えても、不思議はない。
メンデルの法則を知らなかった江戸の人たちの(鎖国のため入っていなかったのではなく、法則そのものがまだ見い出されていなかった)自然の神秘への驚きと関心が、アサガオにおいて爆発的に「開花」したのかもしれません。
文化文政のブームのときは、アサガオの図譜もたくさん刊行され、一説によれば、千を越える品種があったとか。私も少し覗いてみたが、八重咲きなんておとなしい方。花びらが糸のように細かく裂けたもの、巻き紙のように丸まっているもの、花の上に花を重ねた二段咲き(!)など、
「これがアサガオ!?」
と目を疑うような、今の私たちからすると想像を絶するものがある。珍奇な方へいくこと、花菖蒲以上。これほど多様に花型が変化した園芸植物は、世界的にも少ないそうです。
雌しべにわざと別のアサガオの雄しべから受粉させ、いわゆる掛け合わせをすると、突然変異で生じるらしい。ただし、変わり咲きの花は、種のできないものが多く、似たようなものを作りたかったら、また掛け合わせを行って、突然変異の出現を待つしかない。その確率は低いから(理科で習った、メンデルの法則のエンドウの花の系統図を思い浮かべて下さい)、それ以外の多数は捨てられ、たくさんの命の芽を摘むことになる。植物であっても、殺生をすることに、江戸時代の人の胸は痛んだのか、アサガオ塚なるものを建て、借用したとの話も聞く。秀吉の「朝顔の茶会」とは、何たる違い! 正しくは、利休の、か。
お茶や生け花の世界では知られた話らしく、利休の庭にアサガオの垣根を見た秀吉が、それを鑑賞する茶会を所望した。当日、秀吉が屋敷に行くと、垣根を埋めつくしていたアサガオがひとつもない。不興の極みで席入りすれば、床の間にただ一輪、アサガオの花が生けてあったとか。
美学としてはあり得るでしょうが、権力者をあっと言わせるのに、そこまでのことをしなければならない緊張関係に、嘆息する。秀吉のために、大量の花を犠牲にした利休も結局、秀吉により死に追い込まれるのだから、安土桃山時代は、工芸品でアサガオを愛でるようになったとはいえ、まだまだ殺伐としたものが、人の心にあったのでは。
それに比べて、江戸の世の泰平なこと。文化文政のアサガオブームは奇をてらいすぎて、さすがに飽きられ、長続きしなかったそうだが、幕末にも二度めの流行が。日本をとり巻く国際情勢を思えば、そんなことに熱中している場合ではなかったのだけれど。
そして三度めのブームが、冒頭で述べた、明治になってからで、入谷の朝顔市を名所へと押し上げた。
明治以降、花の傾向は、変わり咲きより大輪へ。墨田朝顔愛好会も、その流れにあるわけですね。
五百円で分けていただいた手引きを、歩きながらめくれば、実に細かい。肥料の混ぜ方が、小鉢用と本鉢用、後者はさらに前期用、中期用、後記用に分けて、示され、必ずグラム計量することとある。種は前もってごく一部に小刀で傷を付け、汲み置きの日なた水に三時間ほど浸すなど、その丹精の込めようと探究心たるや、江戸の園芸熱を受け継いでいる!
門を出て、来たときと反対の方へ行けば、車二台はすれ違うことができなさそうな狭い道。お昼を少し回ったところで、日は高く、アスファルトの舗装が白く、暑そう。愛好会の皆さん、鉢を日除けの下へしまって、今頃は届いたカレーうどんを食べているところでしょうか。
路地に面した、モルタル塗り、二階建ての家のサッシの前にも、みごとな花を咲かせた鉢がある。足を止めて見とれていると、向いの家の土間で、ブリキふうの金属板の形を整える仕事をしていたおじさんが、
「前の人、アサガオの先生だから」
もしかして、テントにいた貫禄おばさんだったりして。
路地を行けば、「先生」の影響か、あの家にもこの家にもアサガオの鉢。停めてある自転車のタイヤのそばに置かれていたり、エアコンの室外機の上に載せ、二階のベランダから吊したネットに、つるを這わせてあったり。プラスティックの漬け物樽のような容器に植えて、雨樋に巻きつかせている家もある。アサガオの展示される百花園の周辺は、アサガオ率の高い町。 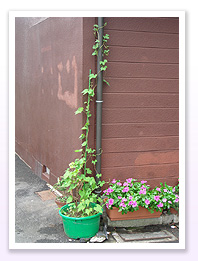
どこからか、ゆるやかな風鈴の音が。隅田川も近いのです。 |
|