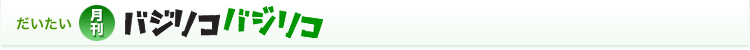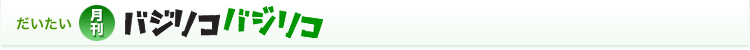| 銀座で飲む。それは男のステイタス。銀座で飲む。それは成功者の証。そんなイメージは未だ根強く残っているだろう。夜の蝶。居並ぶ高級車に照り映える七色のネオン。一見さんはお断り、一般人にはその敷居は天よりも高い、粋筋の街、銀座。
その夜、何故かそんなオトナの世界に私は、いた。
会社員としてデザイナーをやっていた頃のことだ。地方に出張校正に行った帰り、同行の印刷会社担当、高山氏は私の耳元で囁いた。
「早川さん、ひとつちょっと、ネ、どうです…?」
主語のまったくない、日本独特の曖昧な高山氏の誘いであった。大方どこかで飯でも食わせてくれるのだろう。そう軽く考えていたらタクシーはネオンの海の中に漕ぎ出し、連れて行かれたのは蠱惑の異郷、めくるめく銀座の高級クラブであった。
これはいわゆるセッタイというやつか。何気ない風を装いつつ動揺する我が心。お得意とはいえ私ごときは単なる若造、クラブなどお門違いの場違いもいいところだ。一体どういう了見だろう。
こんなところで飲んだら一杯何万円もとられたりするんじゃあないのか? オレは払わなくていいんだよな? 誘われて来ただけだもんネ? いやしかし。だが。ひょっとして…。
不安と猜疑に、にわかに身が固くなる。いかん。動揺したらこちらの負けだ。私はさも場慣れした風を装って店に入った。
「アラいらっしゃあい」
和服を着た女性が、香水の香と共に艶然たる笑みを浮かべ頭を下げる。店のちいママであった。
これがちいママというやつか。噂には聞いていたがやはり実在したのかちいママ。そして一体全体誰が言いだしたのだ、ちいママ。
不思議な「ちいママ」の存在に気をとられていたが、見回すとあちらこちらのボックス席にはすでに紳士たちが女性を侍らせながら談笑している。半間接照明の薄暗い店内に漂う紫煙。低いざわめきに時折混じる、女性の落ち着いた笑い声。オトナだ。オトナの世界だ。いや、わたしのような若造にとってはほとんどよその惑星である。
ちいママに案内され、ボックス席に座るとほどなく若い女性が花が咲くように現れた。
「タカさんおひさしぶり!」
高山氏の馴染みのホステスらしかった。「ようアキちゃん! ほら、こっちこっち!」彼女がソファに腰をおろすと高山氏の相好はにわかに崩れた。
ドラマなどに出てくる高級クラブのシーンが思い浮かぶ。あれを見るとたいてい客の男に一人ずつホステスがつくことになっている。
ひょっとしてオレの隣にも来るのか? ホステスが? 来たらどうすればいいのだ? 気を揉んでいるとやはりそれは現れた。
「失礼しまあす、ナミです」
うわ。やっぱり来た。ナミとか言ってっぞオイ。何気ない顔を装いつつも尻のあたりに緊張が走る。彼女は私の隣に座ると「こちら…初めて?」と聞いた。
「初めてデス」
精一杯くつろいだふりをしつつも、セリフは素人丸出しである。少し微笑むナミ。いかん。見透かされている。しょっぱなから身の置き所がない。「童貞少年」という言葉が頭に浮かぶ。どう対処していいかさっぱりわからない。高山氏に場のリードをお願いしたく目で合図するが、彼は私の方を見ようともしない。
「タカさんどうしてたのお、全然来てくれなかったじゃない」
「いやいやいや、出来る男はほら、仕事が忙しいからサ」
破顔しながらアキちゃんに言い訳をする高山氏。彼の額は薄暗い店の照明でもてかてかと光り、湯気がたちそうであった。
私はやたらとおしぼりで手を拭き、意味もなくお冷やのグラスを口に運んだ。場慣れした者ならここでナイストークのひとつもかまし、座は盛り上がり意気投合、そしてその後は、どうだいひとつお店がひけたら、ネ…などといったオトナの交渉が始まるのだろう。だが何しろこちらは銀座童貞。途方に暮れるばかりである。ぎごちない沈黙の後ホステスが聞く。
「あの、お仕事は何をやってらっしゃるんですか?」
グラフィックデザインの仕事内容を一般の人に説明するのはなかなか難しい。視覚伝達がどうのデザインテイストがこうの、などと説明しても、大抵「イラストを描いてるんですか?」などと言われてしまうのがオチだ。私は相手にわかりやすいように答えた。
「化粧品なんかのパッケージを作ってるんです」
「あ、じゃあ絵とかお上手なんですね!」案の定、彼女は言った。
「いや絵を描くわけじゃなくて、文字とか絵とか写真とかを組み合わせて全体を作るんです」
「それじゃ手とか疲れません?」
「手……?」
「箱とか折るんでしょ?」
「いえ箱は折りません…」
「じゃ色を塗ったりとか!」
「いや塗らないけど…」
「………」
会話は終わってしまった。ギンザでクラブでホステスである彼女は、私にとっては異性というより異星人であった。異星間コミュニケーションに苦慮し、目で高山氏に助けを求めるが、彼は若いホステスと体を寄せ合い、すでに二人だけの大気圏に突入してしまっている。ホステスのアキちゃんは高山氏に身を寄せ、彼を軽く睨みながら唇をとがらせて何事かを主張していた。
「ねえ、エルメスのバッグ買ってくれるってゆったじゃない」
「いやいや言ってないよう」
「うそォ買うってゆったァ。こないだゆったァ」
「いやいや言ってないったらあ」
「ねえエルメスぅ」
「いやいやいや!」
「うそつき」
「いやいやいや!」
「もう、つねっちゃうから!」
「あいたたた!」
無言でビールのグラスを口に運び、目の前で展開されている古典マンガのようなやりとりを見つめる。他に行動の選択肢はない。私は一応得意先で、いわゆる接待を受けているという状況らしいのだが、彼の視界から私の存在はすでに消失しているようであった。
それにしても腹が減った。時刻はすでに八時を回っているというのに何故によって料理のひとつも出てこないのだ? 隣の女と何を話せばいいのだ? オレは何故ここにいるのだ? そして何故このテーブルには柿ピーしかないのだ?
「早川さん、お腹すいてません?」
高山氏が我に返ったかのように聞く。「当たり前じゃないスか!」心の中で民衆の叫び声が上がる。しかしこういうところで
「お腹がすいた」
などと言うのも、いかにもコドモじみた事に思える。私の中の卑屈な見栄坊は、私の中の真実を無視し、少しだけ微笑むと「ええ、ちょっと」などと言った。
「ママ、何か食べるものない?」高山氏はちいママに聞いた。私の胸に希望が芽生える。何と言ってもここは高級クラブだ。食べ物も高級志向に違いない。きっとこれから「おいしんぼ」の緻密イラストのような高級料理がばかすか出てくるのだろう。そうに違いない!
だがその期待を破砕するようにちいママは眉根を寄せて言った。
「あら…うち、シューマイぐらいしかとれないんですけど…」
シューマイ。別にシューマイは悪くない。崎陽軒のシューマイは冷えていてもうまいのだ。だがここは銀座高級クラブである。何がどうなってシューマイなのだ。何かこう、気の利いた小料理のひと皿やふた皿、さりげなく出されてもいいのではないか。それなのにちいママは難題をふっかけられたかのように眉根を寄せ「シューマイぐらいしか」と言うのだ。
「いいですか? シューマイ」
高山氏が聞く。悪いと言っても仕方がない。動揺する民衆。たちこめる不穏な空気。
いやだがしかし。為政者のごとく民衆に言い聞かせる私。ちいママはシューマイと言うが、やはりシューマイだけがソロで出演、ということはさすがになかろう。きっとあれだ。中華料理の仲間たちがシューマイに付随して出てくるのだろう。そうなのだろう。だから安心しなさい。ねっ。ねっ。
ホステスとの会話は停滞したままだ。こういう時は煙草でも吸って間を持たせるしかない。ポケットから煙草を取り出し、一本くわえた。
突然ホステスがぴょこんと弾かれたようにソファから飛び上がる。何事かと思えば彼女は床に立て膝つき、火を差し出してくるではないか。異星人の意表を突く行動。「あっスイマセン」うろたえて思わず頭を下げた後に、この行為がサービスであったことに気づく。女をかしずかせることに満足を感じないような男はギンザで飲むような資格はないに違いない。ところが私はいきなり恐縮してしまった。「失格ね」とナミの目が言っているように思える向かいの席では「ゆったあ」「いやいや」が延々と繰り返され、高山氏の目尻がさらに下がる。
やがてボーイが恭しく黒い寿司桶を運んできた。でかい寿司桶が円盤のようにテーブルに降りてくる。これだけでかい桶だ、中にはきっとシューマイと愉快な仲間たち、色とりどりの高級な中華料理ちゃんたちが並んでいるのだろう。
だがテーブルに着陸した寿司桶の中に並ぶのは見事なまでにシューマイのみだった。分子配列の如く正確無比に並ぶシューマイたち。純粋シューマイというかシューマイ全体主義というか、完膚無きまでにシューマイだ。ちいママの言うことに嘘はなかった。嘘のないのはいいことだ。だが、これは。こういった場合は。
「早川さん、シューマイ来ましたよ! さあどうぞどうぞ!」
アキちゃんと乳繰りあっていた高山氏が、大手柄をたてかかのように言う。
諦念に身を委ねきると、心はいっそ清々しくなるものだ。欲も得も捨て、無心に割り箸をとる。その時の私の顔はもはや穏やかな仏のそれであったかもしれない。
ぷち、と割り箸を割った途端、時空が反転した。
「さあて皆様お待ちかね、ダンスターイム!」
司会者がマイクに叫ぶと店内が派手な照明に変わった。どこからともなく流れ出すムード音楽。あちこちで男女が嬉しそうに立ち上がる。何だ。何が始まるのだ。
盛り上がる音楽。目眩がしそうな派手な照明。その妖しい空間の中で宗教的陶酔に浸るがごとく男と女はくるくると、よたよたと、ふらふらと回る。
どうやらこの店はある時刻になるとダンスタイムなるものを催し、ホステスが客と踊るのを売りにしているらしい。だが中高年の男性が若い女性を腰に抱き、覚束ないステップを踏む様は、ダンスというよりリハビリテーションのようだった。
隣のホステスは彫像のように動かない。目の前には唯一の心の友シューマイ。
シューマイとは灰色の無彩色な料理だが、ちょこんと乗ったグリーンピースがそんな弱点をけなげに補っている。しかし赤やら青やら緑やらのライトは寿司桶を幻覚光線のように照らし出し、そんな細やかな彩りへの配慮はかき消され、シューマイは単にしわしわの不気味な肉塊と化してしまっている。
私は未開の惑星に降り立ち、原住民の謎の祭儀に迷いこんだ地球探検隊員のような心持ちになった。ここは日本でも地球でもない。秘境だ。異次元だ。未知の惑星ギンザだ。
「いこっか」
「うん!」
高山氏とホステスは少年少女のように見つめ合い、手に手を取ってダンスの輪の中に入っていった。
「あっ、船長…」
あんな高山氏といえど私の心の支えであった。だがその彼もいそいそと原住民の輪の中に入っていってしまった。心のよりどころをまた一つ失い、未開の惑星に一人取り残される隊員。いつ果てるともなく回る男と女。秘境の祭儀のまっただ中に私とシューマイだけがいた。
そうか。これがギンザというものか。男のステイタスとはこういうことだったのか。青二才の私は唸った。そして心の内で吠えた。銀座が何だ。高級クラブが何だ。オレは、オレは…地球に帰りてえ!
そう、私は若かった。青二才だった。私は事ここに至ってさえも、高山氏が会社の金で遊ぶため、接待にかこつけて私を誘ったのだという至極簡単な事実にも気づかなかったのだ。
こんな経験を重ねて人はオトナになってゆくのだろう。世慣れてゆくのだろう。そういう意味でいえばギンザ探訪も得難い体験であった。あれからもう十年以上の時が過ぎた。私が酸いも甘いも噛み分ける立派なオトナになれたのもこういった経験があったからかもしれない。私は高山氏に感謝しなければならないのだろう。
高山さん、こんなぼくをオトナの世界にいざなってくれてありがとう。貴重な経験をありがとう。
そしてお星様、どうか経費濫用の廉(かど)で、すでに彼が会社をリストラされていますように。
|