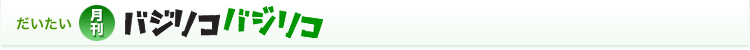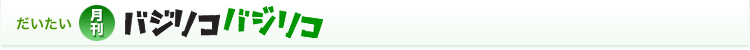昼飯を終え、会社に戻る途中のことであった。
当時、会社員だった私は、営業の山崎と
「仕事、やってらんないスよねえ」
「かーッとビール、飲みたいスよねえ」
などといった、若手社員お定まりの会話を交わしながら、神宮前から表参道へ抜ける道を歩いていた。
表参道にオフィスがある、などというと羨ましがる女性もいたりもする。だが、我々のような若手男子には、とりたてて嬉しいことでもなかった。
当時は、いわゆる「昼飯」を食えるところは、この界隈ではあまりなかった。
昼時にこの界隈で幅を利かせているもの、それは「昼飯」ではなく、「ランチ」である。ちょっと小ぎれいなフランス料理屋やイタリアンレストランが昼時に出すランチなる代物は、女性にとっては素敵に洒落たものなのだろうが、若い男子にはまことにもって食い足りない。
サラダと称する、モンシロ蝶幼虫の餌かと思ってしまうほどつましい数葉のレタス。皿の径に対し極めてアンバランスな料理の盛り。そして、足りないならこれでもお食べといった風情で添えられる薄切りパンにオママゴトカップのコーヒーがついて、しめてお値段1,280円と来た日にゃ気分はもうやさぐれ労務者、「おう、もっとドバッとつがんかいコラ」などと野卑な苦言のひとつも呈したくなってくるというものだ。
そういったわけで、いわゆる男子の胃袋を満足させる「昼飯」を食いに行くには、会社から少しばかり遠征しなければならないのだった。
小ぎれいな住宅の建ち並ぶ、静かな裏道。雲はゆったりと流れ、あちこちに若葉の緑が目に入るようになった、四月も終わりのある日、満腹のうちに私と山崎は「今日もまた残業スよとほほ」といったぬるい会話の中に、日常のささやかな幸福と平安を噛みしめながら歩いていた。
「キミ」
後ろから呼び止められた。
「そこのキミ」
振り返ると子どもである。小学校二年生ほどであろうか。トレーナーに半ズボンの少年である。後ろから走ってくると我々に追いつき、歩調を同じくして歩き始めた。左手の指という指に、仮面ライダー指人形をはめている。
「キミね」
子どもは山崎に話しかけた。
「キミ、ぴーまんは好きカ?」
山崎は黙ってしまった。
山崎公平27歳。実直に仕事をこなし、来年には妻をも娶ろうという立派な大人である。それが見知らぬ、しかも仮面ライダーの指人形をはめた子どもにキミ呼ばわりされ、その上「ぴーまんは好きか?」である。
いくら、しょっちゅう上司に怒られ、クライアントの苦情に頭ばかり下げている山崎でも、大人のプライドというものがある。
だが小春日和の中、そんな山崎のプライド、男のメンツは、年端もいかぬ小わっぱに何の前触れもなくいきなりつぶされてしまったのだ。理不尽である。あまりに理不尽である。思わずぎゅっと手を握りしめる山崎だったが、相手は子どもである。黙るよりほかはない。
しかし、虚を突かれ、揺さぶりをかけられた彼の自我はすぐに体勢を立て直した。オトナの自覚が蘇ってきた。山崎は子どもに向かってにっこり笑うと
「うん、ぴーまん、好きだヨ」
と答えた。
偉い。
さすがは好青年、山崎。見知らぬ子どものわけのわからぬ、しかもぶしつけな問いにこんなにも優しい笑顔で応対できるとは。まったく偉い。見積もりの数字を間違えたって、納期がずれこみ、客先で怒られたって、それが何だ。こうして笑顔で子どもに接することができるだけで、立派な大人じゃないか山崎。素晴らしいぞ山崎。
だが、子どもは山崎のせっかくの笑顔に見向きもせず、下を向いて歩きながら「フーンぼくもぴーまんは好きダ」と棒読みで答えた。そして間髪入れず、
「納豆にネギは入れるカ?」
と聞いていた。
ぴーまんの次は納豆にネギである。
山崎の笑顔がぎこちなく固まった。
一体この子どもは何なのだ。見たところ普通の少年である。顔つきに特に異常なところは見られない。左手の指という指に仮面ライダー人形をはめているほかは、特にどうということのない、その辺にいくらでもころがっていそうな少年である。
私の服装はラフなものだったが、営業の山崎は大柄な体躯にスーツを着用、見た目には完全に「オトナの人」なのだ。そのオトナをつかまえて「キミ」と呼び、ぴーまんだの納豆だのと問いかけてくる子どもは一体何なのだろうか。
ひょっとして狂っているのでは。
「狂気の小学生」などというものが存在するのだろうか? 頭のねじがゆるんでるというようなことがあるのだろうか?
♪アッリャリャん コッリャリャん
♪おっつむの ネージ
♪やっコリャまた バッチリ ゆっるんでる びよよ〜ん
「頭のねじがゆるむ」という言葉から、「花のぴゅんぴゅん丸」のテーマ曲が連想され、財津一郎の脳天気な歌が脳裏をよぎった。だが全然面白くない。私はだんだん気味が悪くなってきた。
空は五月晴れ、若葉が目にしみ、瀟洒な住宅が並ぶ閑静な表参道の一角に、不穏な気配が漂い始めていた。
山崎は「納豆にネギを入れるか」の質問に対し、もはや先刻の笑顔を見せる余裕もなく、
「納豆に、ネギ、入れる…かなァ、オレ…」
と、不安げに呟いた。
子どもは確固とした答えを要求するかのように沈黙している。
「うん、入れ、入れるかな、やっぱり。うん、入れる入れる…」
山崎は答えたが、子どもと目を合わせようとはしなかった。そしてその語尾はだんだん尻すぼみとなり、春の風に消えていった。
子どもはやはり下を向いたまま、「フーンぼくは入れたり入れなかったりするな」ときっぱり答えた。
この時すでに、我々の歩調はかなり、というよりあからさまに早くなっていた。もう、こんな変なガキはさっさと振り切って会社に戻り、あのぬくぬくとした、平凡な日常に戻りたい。早く戻りたい。
だが、まったく振り切れないのだ。
さりげなく、だが着実に速力を上げ始めた我々に、子どもは意識する風でもなしにピタリと歩調を合わせてくる。
湖に静かに泳ぐ水鳥も、その優雅さを保つため水面下では足ひれを激しく掻いているという。我々の上半身はさりげなさを装ってはいたものの、下半身はというとエイトマンのように激しく躍動し、何気ない表情に何故かうっすらと汗などかきながら、表参道から神宮前に向けて、高速に移動していった。
しかし、子どもも依然として同じスピードで追尾してくるのだ。
「じゃそっちのキミ」
心臓が高鳴る。やはり来た。オレだ。オレの番だ。
私は卑怯な人間である。臆病な人間である。
私は、私という人間は、同僚に突如降って湧いた災難、このわけのわからぬ事件を、脳内で「道で出会った少年とのほほえましいふれ合い」といった図式に無理矢理押し込め、軽い笑みなど浮かべて、自分は部外者であることを表現するのに余念がなかった。さらには
「いやあ山崎くん、元気のいいボクにつかまっちゃったネ。マ、がんばってお相手してあげて」
などという、この出来事を自分とは関係ない、相手のみの問題と位置づけるためのあざといセリフまで用意し、あまつさえ彼からなるべく離れようと、歩調を微妙に調節していたりするのだった。
だがそんな私の小市民的な保身根性を見越したかのように、この子どもは「そっちのキミ」と名指ししてくるのだ。
「キミはどう」
子どもは私の側へ寄って聞いた。来ンなよ。そばへ来ンな! 来ないで、来ないでつかあさい!
「キミはどうなの」
どうって何だ。何が「どう」なんだ?
ぴ、ぴーまんか? オ、オレにもぴーまんのことを聞いているのか? そうなのか?
「ぴーまんのことかい?」
私のその「分別ある大人が子どもに向かって優しく語りかける様子」を多分に意識した問いかけは、自分でも鳥肌が立つほどわざとらしかった。だが、子どもは、そんなわざとらしさもすでに織り込み済みといった風情で、やはり棒読みで答えた。
「そうダ」
私は腹をくくった。
「ぴーまんは好きだよ」
私は、自分の持てる全演技力を振り絞って、さりげなく、実にさりげなく答えた。
おお、思えば何というさりげなさだったろう。その答えはまったくもってさりげなく、そのあまりのさりげなさに、その場の空気も打ち震えるほどであった。
子どもはちょっとの間、答えなかった。
しまった。やはり見透かされたか。
オレの力もここまでか。
しかし子どもはややあって、
「フーンぼくもぴーまんは好きダ」と答え、すぐに
「じゃ、納豆にネギは入れるカ?」
と聞いてきた。
そうだろう。やはりそう来るのだろう。わかっていた。わかっていたはずなのだ。
だが、わかっていたはずだのに、私は関わり合いになりたくないばかりに、その場を「コレは山崎クンに起きた出来事ナノダ。あくまで彼ノ問題ナノダ」などと無理矢理に解釈し、何の答えも用意せず、自分は関係ナシ夫の態度をとってきたのだ。
いずれは自分に降りかかる問題であるにもかかわらずそれを先送りにし、見て見ぬ振りをしていたのだ。
山崎にすべてを押しつけ、自分は逃げようとしていたのだ。
何という小心者、何という卑怯者であろう。
「納豆にネギは入れるカ?」
子どもは念を押すようにまた聞いてきた。
私はぼんやりと考えた。
…そう、オレは納豆にネギを入れることもある。定食なんかについてる納豆にはネギがのせてあったりするもんな。でも家じゃ入れないな。そのためだけにネギを買ったりしないもんな。だいたい、男の一人暮らしでネギなんか買わないよな普通。ネギってのはいくらぐらいするんだろう。案外高かったりするのかな。
だが、待てよ。オレはガキの頃はネギが嫌いだったはずだ。いつからオレは納豆にネギを入れるようになったのだろう?
そうだ、思い出した…。オレはネギが嫌いだったのだ。たまーにしか食卓に上らないスキ焼きのネギでさえ、よけて食っていたほどだ。でも和田本町のミノルくんちでネギが出た時、子ども心に残しちゃいかんと思い、無理矢理食ったんだっけ。そしてそれ以降ネギがあまり嫌いでもなくなった。そして給食の時間、隣の席のフミエちゃんが「早川くんがネギ食べてるー。コクフクしたんだーすごーい」と言ったそのひと言が、オレをしてオトナの階段を一気に昇らせたのだった。ああ、フミエちゃんありがとう…。あの頃ボクはキミが。キミのことが。
「ホワホワホワー」という音と共に、さまざまな回想が頭上に現出した。
「納豆にネギは入れるカ?」
外交交渉における相手国の再三の要求のように、子どもは同じことを繰り返し聞いた。私の頭は混乱した。何を言えばいいのだ。えーと? ネギは嫌いだったけど好き? ミノルくんちで? フミエちゃんがオレを…?
次の瞬間、私の頭は急にしゃんと立ち直った。ひとつのアイデアが頭上に点滅した。
この小僧と同じことを言ってやれ。
「ネギは入れたり入れなかったりするな」
私は澄まして、先ほどの少年の答えとまったく同じ事を言った。落ち着いて、優しい声で、さりげなく。あくまでさりげなく。
子どもは一瞬、ほんの一瞬たじろいだかに見えた。しかしやはり下を向いたまますぐに「フーンじゃボクとおんなじダ」と答えた。
するとどうだろう、子どもはにわかに歩調を緩めると、我々から離れていくではないか。
「勝った…」
何に勝ったのかわからないが、私はとりあえずそう思った。
だが、その機に乗じてさらに歩調を加速させる我々に、子どもは後ろから追いすがるように新たな問いを投げかけてきた。
「どこへ行ク」
「会社へ帰るんだよ」と、山崎。
「サラリーマンだナ」と、子ども。
「会社員はツライよ。はは」と、私。
何ということだろう。せっかく相手の隙を衝く答えで勝利したというのに、またしても
「通りがかりの少年とのちょっとしたふれ合い」
といった図式の下にこの場を塗り込め、とりあえず表面上の空気を和ませて、終わりにしてしまいたいなどという、私の小市民的な、いじけた根性が顔を出してしまった。「会社員はツライよ」などというわざとらしい言葉は、陳腐さを伴ってその場を漂い、私はその恥ずかしさから逃げるように歩調を早めた。
私は歩調を早めながら、一度振り返ってみた。すると、その場にはもう子どもの姿などどこにもないのであった…などと書くと、何やら都市伝説風ミステリーにでも仕上がりそうだが、あいにく子どもはちゃんと存在し、花壇のレンガにけつまずいてコケたりしているのであった。
あの子どもは一体何だったのだろうか。
無礼、というよりは非常識な振る舞い、奇妙というよりは変態的な質問の数々…。子どもというより前に、何か、人間としておかしくなかったか。存在として異質ではなかったか。
私は会社に帰り、仕事をこなすふりをしながら、さきほどの少年のことをしつこく考えてみた。
ヨーロッパには子どもの姿を借りて現れ、人間に色々な忠告や助言を与えたりする妖精の伝説があるという。ひょっとしてあれは妖精だったのではあるまいか。
いやいやいや。羽のはえたフェアリーならともかく、仮面ライダー人形を、しかも指全部にハメまくった妖精などいるわけもなかろう。それにレンガにけつまづいたりしていたところを見ると、妖精のようなはかない存在でなく、まごうことなき実体があるのだ。
日本古来の座敷童(ざしきわらし)というのはどうだろう。しかしあれは家につくものであって、真っ昼間から往来を行き来し、通行人に話しかけるようなものではない。
ひょっとしてひょっとしたら。私は考えた。あれは宇宙人が化けていたのではなかろうか?
1957年、UFOに連れ去られ、宇宙人と話をしたと証言するアメリカのビル・アンダーソン夫妻は、その会話が
「『食べる』って何だ?」
「『黄色』って何だ?」
というような、ごく当たり前の意味すらも通じない、ちぐはぐなものだったと証言している。
たしかにあの子どもの言動はおかしかった。セリフも棒読みのごとくであった。だが、それでも意味が通らないということはない。意思疎通はも一応はできた。それに大宇宙の果てからやってきて、納豆にネギを入れるかどうかを質問する宇宙人などというものがいるだろうか。いくら何でももう少しマシな質問をするのではないだろうか。
では「惑星ソラリス」のように、何らかの超自然的な働きによって、私の無意識の願望が実体化してしまったというのはどうだろう?
いやしかし、美人の奥さんが現れるならともかく、仮面ライダー指人形をはめたガキに納豆にネギを入れるかどうか聞いて欲しい! などといった願望はいくら無意識とはいえ、ない。絶対にない。
…それとも山崎にそんな隠れた願望が?
いやいやいや、何を私は現実離れしたことばかりを考えているのか。
きっとあの少年は、家も貧しく、両親も共稼ぎのカギっ子で、兄弟も友達もいない、孤独な少年なのだ。誰か話し相手が欲しいのだ。遊び相手が欲しいので通りがかりの人に声をかけ…。
…ほんとか? 何だかいかにもありがちな説明だ。それに貧しいか? あいつ。服も普通だったし、第一、左手全部にライダー人形はめてたぞ。全部だぞ。ガキのくせに財力あるぞ。
しかも話し相手が欲しいのに、見知らぬ大人にいきなり「納豆にネギを入れるか」はないだろう。
その昔、辻占(つじうら)というものが日本にはあったという。
橋のたもとなどに立ち、通りすがりの人々や、たまたま声をかけてきた人の話、子どもの歌うわらべ歌など、偶然に耳に入ってきた言葉から、神のご託宣、異界からのメッセージを聞き取ろうとする、言霊(ことだま)信仰から来た占いの一種である。
ひょっとして我々は、人類を代表して、子どもの姿を借りた大いなる存在から何らかの試問を受けたのではあるまいか。神か精霊かは知らぬが、その大いなる存在は小学生男子の体を依童(よりわら)として使い、たまたま通りかかった我々に、神の問いを投げかけたのではあるまいか。
「ぴーまんは好きか」「納豆にネギを入れるか」といった問いは、ひょっとして人類存亡に関わる、重大な内容の隠喩であったのではあるまいか。かのノストラダムスの四行詩のように…。
「納豆に、ネギ、入れる…かなァ、オレ…」
そうだとしたら何と情けない返答だろう。しかも我々はテキトーに答え、その場から逃げることしか考えていなかったのだ。神はこの返答に、絶望してしまったかもしれない。人類に何事かの裁定を下してしまったかもしれない。もし明日、天変地異や熱核戦争で人類が滅びるとしたら、それはきっと私と山崎のせいである。
人類の皆さん、すいません。
しかし、まだ希望はある。大いなる存在はいつかあなたのところへ来るかもしれない。
もし皆さんが道端で仮面ライダー指人形をはめた小学生男子に謎の問いを投げかけられたら、どうか熟考して、慎重に答えていただきたい。その答えに人類の存亡がかかっているのかもしれないのだ。
最後に今一度記しておく。神の問いとは、こうだ。
「ぴーまんは好きか?」
そして
「納豆にネギを入れるか?」
●
追記
その後、「納豆にネギを入れるか?」というセリフは、「''クレヨンしんちゃん''がお姉さんをナンパする時に使うセリフ」であったことが判明した。
何だ。なーんだ。そうなのか。クレヨンしんちゃんか。やっぱり子どもじゃないか。気にすることもなかったのだ。はははははは。
…そう笑って済ませたかった。だが、しかし、依然として不可解だ。何だか全然スッキリしない。何とも言えぬ気まずさのようなものがまとわりつく。
あの少年は我々をナンパしようとしていたのだろうか? |