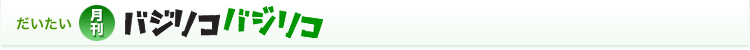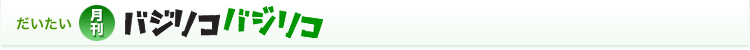カツアゲに遭ったことがある。
新宿や池袋の裏通りなどではない。犯罪などにはおよそ縁のなさそうな、お子様方が大喜びのTOKYOファッションストリート、原宿は竹下通りで遭遇したのだ。まだ会社員だった頃の話である。
退社後、JR原宿駅に向かい、夜の竹下通りを歩いていた。駅と会社を結ぶ通勤路なのだ。休日は芋洗い場となるこの通りも、平日の夜ともなると、さすがに普通の商店街と変わらぬ程度の混み方であった。
「ねーねー、お金貸してくんない」
突然の声にひょいと見ると、右手に若者がいた。ひょろりと痩せて背が高く、まだ十代にも見える。親しげに笑いかけてくるが、見たこともないやつだ。
歩調を合わせながら、さらに言う。
「ねー貸してよ、お金」
誰かと間違えているのだ、と思った。だが妙だ。人違いにしては名前を呼ばない。「お金貸して」以外の事も何も言わない。
「は。お金……」
そう問い返した。曖昧な笑みを浮かべているのが自分でもわかる。
「そーそーお金さー、あるだけでいーからさー」
「人違いだよねえ」
相手に笑いかけた。だが相変わらず相手は、へらへらと笑いながら、「ねー貸して貸して」と言っている。
こいつはひょっとして、どこかおかしいのか? そう思った時であった。
「ぶっ殺すぞ、この野郎」
いきなり後ろから声がした。
私の顔色はさっと変わったかもしれない。思わず振り向くと、斜め後方に、歩きながらこちらを睨んでいる男がいた。
俺は脅されているノダ。その段になって始めて気がついた。
ねーねーお金貸して…そんな事を言いながら近づいて、死角から別の男が突然脅しにかかる。これが二人組の手口らしかった。
その男が、志賀勝ばりの強面の大男で、港雄一ばりにドスの効いた声で凄んでいた……のなら、私はえへへと笑い、そそくさと財布を取り出してしまったかもしれない。
だがそこにいたのは、あごひげなどを生やしているものの、色白で童顔といってもいいような顔だちの若者であった。背は私より若干低く、強そうには見えない。そしてその声も細く甲高く、脅し文句も何だか板についていないのだ。
「お金お金、もー持ってるだけでいーから。千円、千円でいーから」
ひょろ長い方が言った。いーから早く、とせっつくような調子だった。
「逆さに振ったって、金なぞないね」
そんな言葉がつるりと口を滑って、出てしまった。
「しまったッ」心の中で思わず舌打ちをした。ばか、ばか。一体どういうつもりだ俺は。こんな連中にそんなことを言って、刺激してしまったらどうする、危険じゃねえか!
「あれ?」という表情で、二人の若者は顔を見合わせている。
金なぞないね、の後の二の句が継げない。我ながら不器用な間が空いてしまっている。そのまま歩き出すと二人組は無言でついてくる。
こういう場合、どうすればいいのか? 走りだせばいいのか? 大声を上げたりするのか?
わからない。わからないのでとりあえず歩を進めるしかない。二人は黙々と後からついてくる。我々は竹下通りをかたまって歩いた。
「……」
「……」
端から見たら、それは単に、三人の男が並んで歩いているだけの光景であったろう。しかし実際には、恐喝犯と被害者がお互いどう振る舞っていいかわからず、膠着状態に陥っている図なのであった。
気まずい。非常に気まずい。
その気まずさを無理矢理脱するかのように、ひょろ長い方が、また言った。
「あのさー、お金…」
「安月給なんだからさあ、金なんてないって。たかるやつ間違えてんだろ」
ばか、ばか! 今度は頭を抱えたくなる。
口が滑り過ぎだ。しかも明らかに相手を見下した口調だ。だめだ、危ない。何を言ってるんだ、俺は。
若者同士は、目を見交わし、「何だこいつ…?」という風に首を傾げている。こちらはこちらで、どうやってこの連中を振りきろうかと、回らぬ頭でそればかりを考えている。
ようやく思いついた。とにもかくにも、駅に入っちまえ。
竹下通りと、原宿駅の改札は一直線上にある。通りを過ぎて横断歩道を渡りさえすれば、そのまま竹下口改札に飛びこめる。
問題は、駅前の道路だ。信号が青であったならそのままノンストップで駅に駆け込めるのだが、赤で足止めを食ったら、二人組と並んだまま立ちんぼの状態となってしまう。それだけは避けたい。
私は信号に強い念を送った。
信号さん、どうか青、青、ここはひとつ青という方向で、何とぞよろしくお願いします……!
祈るような気持ちで見上げると、あーやっぱりなー、やっぱり人生ってこうなるんだよなー……といった具合に、赤。
とうとう横断歩道の手前、カツアゲ両君を脇に、バカ面下げて信号を待つ格好となってしまった。
横目で見ると敵も手持ちぶさたの様子。次のアクションに移りかねているようだ
気まずい。
何故によって俺が気まずさを感じなければならないのか、などと心の片隅でぼんやり考える。長い。信号は全然変わらない。故障ではないのか。車が無情に通りすぎる。道路の向こうで待つ人は、それぞれに煙草を吸ったりあくびをしたりしている。あんたのそのぬるい人生のひと時を、俺のと交換してくれ。
ようやく信号が、待ちに待った青に変わる。歩き出すと、ひょろ長が上着をつかんできた。
「おいちょっと来いよ……」
「離せコラ!」
精一杯声を荒げて引き剥がす。そして脱兎のごとく駆け出した……かと思いきや、人間、こんな土壇場でも見栄を張るものなのだろうか。頭にあったのは、今ここで駆け出せば尻尾を巻いて逃げ出したという格好になってしまう、という一念だった。
私は、ビンビンに二人組を意識しながらも、さも平然と、こんな連中など眼中になしといった風情で、横断歩道を渡っていった。
次の瞬間、背中が恐怖に粟立った。
刺される。
首筋までナイフが迫っているように感じる。髪の毛が逆立つ。ひょっとして、まさか、まさか……
撃たれるのでは?
カッと熱する頭。サッと冷える背中。だが振り返っては負けだ。平然と、あくまでも平然とだ。しかし心は毅然としていても、その歩行はガチョウの突撃といった不自然であることが自分でもわかる。
それでも改札口はぐんぐん近づいてくる。あと少し、あと少しだ。こちらには定期券という強い味方がある。
当時は自動改札などというものはなかった。改札で定期券を一閃、駅員の脇をすり抜けさえすれば、定期なぞ持たぬであろうあの二人組は、入ろうにも入れまい。原宿駅改札は、魔物をはねつける結界だ。
駅員が、邪気をはねつける頼もしき陰陽師に見える。ああ、駅員さまお助けを! あの下等な式神どもを打ち払ってくださりませ!
スタスタ、とはいかずドタドタドタと改札を通り抜ける。そのまま階段を素早く昇ると、おお、天に神はおわしますことか、今しも山手線の新宿・池袋方面行きが発車しようとしているところであった。見栄も何もかなぐり捨て、駆け上がって電車に飛びこむ。
「ぷしゅう」
山手線のドアが閉まる音が、装甲防御扉のそれに聞こえる。素早く前後左右に目を走らせるが、あの二人はいない。
失禁しそうな安堵感がうち寄せ、波のように退いてゆけば、今度は心臓が早鐘のように鳴り出す。熱くなった頭で考える。
さてこういう場合、どうすればいいのか?
無論、警察だ。警察に届けるのだ。
しかし、今はもう電車の中だ。善良な市民としてはこの場合どのような行動をとるのが最も道義的かつ合理的であるのか。
おおそうじゃ。新宿の東口駅前に交番がある。あそこに飛びこんで話をしよう。原宿から新宿まではわずか二駅、今し方の出来事だ。あの連中の人相風体、詳細に報告できる。
そしてきっとこちらの話が終わるか終わらぬかのうちに、電光石火の連絡が飛び、パトロール中の警官が現場に急行、あっという間に二人組はふんづかまって、府中か網走で木工制作や袋貼りをして過ごすことになるのだ。そうなのだ。きっとそうなのだ。
電車を降りると、足早に駅構内を抜け、新宿東口の交番に出向いた。自分の報告ひとつで警察機構が動き出し、かの小悪党どもに正義の鉄槌が振り下ろされるのかと思うと、昂奮を禁じ得ない。
「あのう!」
警官が物憂げにこちらを見た。
「あのう、カツアゲにあっちゃったんですけど…」
「カツアゲ……?」
仁王立ちのまま、警官はおうむ返しに言った。でかい図体の若い男で、館ひろしをぐっと下品にしたような面立ちである。
ひろしは、眉をひそめ、まるでこちらが何か怪しい者であるかのように睨めつけた。そのまま何も言わない。
間が持たない。慌ててつけ加える。
「あの、えと、つまりカツアゲというのは俗にいう言葉であって、あの、キョーカツ、恐喝です」
警官は面倒くさげに言った。
「どこで」
「えと、あの、原宿の、竹下通りで…」
「原宿の事件なら、原宿の署に行かなきゃだめだろうがア」
このバカが、という風情でひろしは言った。よく見るとその顔は、館ひろしのような端正さはなく、ただ大ぶりなだけの目と鼻と口がうすらでかい顔面上に適当に配置されたというような、極めて大味なものであった。
「ここ、新宿だろ」
呟くような調子で、ひろしは言い捨てた。もはやこちらのことは見ていない。そしてその後の言葉は何もなかった。
「あの、そでした、えと、どもすいません」
根本敬漫画の村田のようにへどもどと頭を下げる。私は店員に万引きをとがめられたかのような羞恥心を抱きつつ、その場を辞した。
数分後、中央線快速、立川・高尾方面行きの電車に乗っていた。
高円寺が過ぎる。阿佐ヶ谷が過ぎる。吉祥寺が過ぎる。窓ガラスに映る己の顔が、何故か薄笑いを浮かべている。
カッと熱くなっていた頭が徐々に冷えてゆく。それと同時に、腹の方から何やらムカムカとしたものが湧いてきた。
何だ。俺は被害者だぞ。しかも他の市民の安全を慮って、いの一番に交番まで出向いて届け出たのだぞ。それを何だあのおまわりめの態度は。くそ。劣化複写した館ひろしみてえな顔しやがって。
ぬあーにが「ここ新宿だろ」だ。「原宿の署に行かなきゃ」だ。するってえと何か、俺は刃物銃器その他危険物を所持している可能性のある凶悪な二人組を後ろに従えつつ、道行く人に「すいません原宿の警察はどこですか」などと尋ねながら、徒歩でえっちらおっちらと届け出にいかねばならないというのか?
「君はバカかね? 」
かのデスラー総統の名セリフが思わず口をつく。周囲の乗客がチラリとこちらを見た。おかまいなしに脳内で毒づく。バカめ。三下め。サンピンめ。公僕という己の立場すら理解できておらん犬コロめ。原生虫め。てめえみてえな無能なやつがいやがるから、三億円犯人だって結局捕まんなかったんだバーカ!
…いやしかし。
憤激も多少おさまってきたころ、理性の徒である私は考えた。あそこは新宿東口だ。歌舞伎町のすぐそばだ。きっとあの警官らの日々の業務は、発砲騒ぎを起こした組員を取り押さえたり、ヤクの売人を見張ったり、強盗を追いつめたりというようなハードなものなのだろう。そこへ「カツアゲが」などと言っても話にならないのかもしれない。
強引なポジテブ・シンキングで腹立ちをぐっと抑える。若干のわざとらしさは感じられないでもないが、まあそんな事はいい。
そうだ。そんなことよりも何よりも! ハタと膝を打つ。再び乗客の視線が集まる。
原宿駅を利用する社員は他にもたくさんいる。この危機を会社で訴え、皆の注意をうながそう。警察の態度などというものより、そういったことの方がよほど重要ではないか。前向きではないか。
電車に揺られながら、私は自分のオトナな考えにほとほと感服した。
翌朝、出社した私は、以下のようなメールを送信した。
-----------------------------
【緊急通達】
社員の皆様方へ
お疲れさまです。デザイン部の早川です。
皆様に早急にお知らせしたい事があり、このメールを送りします。
昨夜、私は竹下通りにて二人組の恐喝に出会いました。
一人が金を貸して欲しい、などと言いつつ近寄ってきて、もう一人が「殺すぞ」などと言って脅してくるという手口です。
社員の皆様の中には、竹下通りを通る方も多いと思います。また場所を変えて表参道付近に出没するかもしれません。特に女性の方はくれぐれもお気をつけください。
--------------------------
電子メールの未だ使わざる機能、【全社員に送信】のボタンを押す。
もうすでに、各社員のデスクにはこの緊迫したメッセージが届いているだろう。そして多くの社員が緊迫した面もちで「何ということだ、このような危険が存在するとは」「大変なことが起きたのね。そして早川さんは身をもってこの危険を私たちに知らせてくれたのだわ」などと囁き始めていることだろう。
私はゆったりと椅子に背をもたせ、天井を見上げた。大いなる偉業をなしとげた男に、もはや言葉はいらなかった。
満足げに吐息などついていると、背後からペタシペタシというせわしないスリッパの音が近づいてきた。見ると社長の長廻(ながさこ)健太郎氏であった。
この人物は、社長なら社長らしく革張りの椅子でふんぞり返っていればいいものを、何故かいつもアロハシャツ様の服にサンダル履きというカジュアル過ぎる姿で、用もないのに現場に出没するのであった。
「早川くん、早川くん!」
社長は、スリッパをぱたつかせながら、足早に近づいてきた。
「早川くん、カツアゲに遭ったってホント!?」
息せき切って尋ねた。瞳が少年のように輝いている。
「ええ、メールに書いた通りですよ、相手は二人組の若者で、最初は金を貸せと…」
「金取られた!?」
社長は私の言葉を遮って言った。
「……取られてませんよ、最後まで拒否したんですから」
社長の瞳に、落胆の色が浮かんだ。
「ええッ、取られてないの?」
「取られてないですよ」
「全然?」
「全然」
「そんなこと言って千円ぐらいは取られたんだろ?」
「取られてないですって!」
「……」
「……」
「なァーんだ…」
社長は露骨につまらなそうな顔をして、そのまま何の言葉もなく、ペタシペタシと去っていってしまった。
社長といえば親も同然、社員と言えば子も同然。そんな日本の美しい雇用関係を尻ふき紙のごとく扱うトップの言動。社員の身の不幸をおもしろがるとは。
嘆かわしい。まったく嘆かわしいッ。
苦り切っていると、今度はパタパタパタと軽い靴音が近づいてきた。
見ると制作部の藤山万里子さんであった。藤山さんは、常に露出度の高い服を着用し、殺風景な社内に無用のフェロモンを放出している和風美人で、陰では制作部のセックスシンボルなどと評されている、有能な女性社員であった。
「早川さん、早川さん!」
藤山さんは、スカートをひらひらさせながら、足早に近づいてきた。
「早川さん、カツアゲに遭ったってホント!?」
息せき切って尋ねた。瞳が少女のように輝いている。
「ええ、メールに書い」
「お金取られた!?」
藤山さんは素早く私の言葉を遮って、言った。
「……取られてませんって、拒否したんだから」
彼女の瞳に、落胆の色が浮かんだ。
「えー、取られてないの……」
「取られてませんったら」
「全然?」
「全然!」
「でも少しぐらいは取られたんじゃなあい?」
「取られてないですって!」
「……」
「……」
「そう…」
藤山さんは、その美貌に失望感を露わに浮かべると、再びスカートをひらひらさせながら行ってしまった。
自分の思惑とはまったく違う形で、社内の空気が変化しているのが、すでに感じ取ることができた。眉根にしわが寄り始める。その時、私はすでに道化者と化していたのだが、無意識はその現実を受け止めまいと、おのが認識力をひたすら鈍らせていた。
その事実を否応なく知覚せしめたのは、女子社員たちだった。
女子社員、などといっても、爽やかな笑顔で職場の空気を和ませるような手合いではない。卑しくも「チームリーダー」という崇高な役職にある私をいくを呼ばわり、そればかりか何かというと私の行動をネタにしてはほくそ笑む、不良女子社員なのである。
彼女らは、私が仕事の能率と生産力を高めるべく自発的に、あくまで自発的にとっている午睡に「いくをの船漕ぎ」などと名前をつけ、私がこくりこくりとやり始めると「船長の船出」などと密かに囃してはくすくすと笑った。それだけならともかく、しまいには「キャプテン」などとあだ名をつけるに至っては、もはや職場のいじめといっても過言ではなかった。
さらに、私のファッション・センスに呵責ない論評を加え、我が衣服にことごとく「いくをのドカジャン」「いくをの勾玉セーター」などというあだ名をつけくさり、あまつさえ「伊勢丹・男の新館」で買ったマフラーに至っては「ピアノの鍵盤のとこにかけとく布」などという蔑称を与え、冷笑してはばからない女たちなのだった。
気がつくと、周囲の女子社員が笑っていた。見渡すと全員がニヤニヤと笑っていた。その瞬間、社内での私のスタンスが、「滑稽」という地点まで堕ちてしまっている事実が、稲妻のように認識できた。こともあろうに原宿竹下通りでカツアゲにあった男。
女子社員の一人が近寄ってきて、言った。
「ぷ。あのさー、メール見たけどさー、カツ…」
「取られてない!」
私は叫んだ。そして憤然と立ち上がった。「金は取られてないぞ!」
叫んで立ち上がったはいいが、その後が続かない。思わず外に飛び出る。出てはみたものの、どこにも身の持って行き場がない。
所在なくうろついてふと思いつく。おおそうじゃ。ここはひとつ、あの劣化館ひろしのいう通り、原宿の警察に届け出てやろうじゃないか。何となれば、昨日の一件はどこからどう見ても立派な犯罪だし、善良な一市民には報告の義務があろうというものだ。何といっても筋を通すのが男というものじゃないか。田中正造だって筋を通したからこそ、国語の教科書にも載ったのだ。
表参道沿いの交番に赴く。一抹の不安をよそに、そこにいたのは眼鏡をかけたマスオさん風の、実直そうな警官だった。安堵の念がよぎる。
「あのう……」声をかけた。
「はいッ、何でしょう」
きびきびした応対。爽やかな笑顔。これ、これだよ君。
「実は昨日、竹下通りでカツ……恐喝にあったんです」
「ええッ、恐喝!?」
警官は驚愕の眼差しでこちらを見つめた。大いなる満足とともに、重々しく頷く。
「とにかく、まあとにかく、こちらへ、どうぞ」
警官が椅子をすすめる。腰掛けると警官が身を乗り出してくる。
「その時の状況を詳しく話してくれますか」
このひと言を待っていたのだ。安心し、事の顛末を語る。凶悪な二人組に脅されたこと。周りには助けを求められそうになかったこと。しかしそんな状況でも果敢に抵抗し、機転を利かせて駅に駆けこみ、難を逃れたことなど……。
しかし、ふと気がつくと警官の目は最初の勢いを失っていた。
警官は、何か腑に落ちないような、少し退屈そうな表情でこちらをただ見ている。メモの手も、すっかり止まってしまっていた。私はお客にまったく受けないまま、高座で噺を続ける落語家のような気分になった。
話し終えると、少しの間沈黙がおりた。通りを過ぎゆく人が、ちらりと交番の中をのぞく。かすかな羞恥が胸に疼く。
「で……」
当惑したような面もちで、警官が口を開いた。
「結局、被害は、あったんですか?」
「いえ、ですからお金は取られてないんです、何とか振り切りましたから!」私は言った。
「じゃあ、被害はなかったわけですね?」
「ええと、お金は取られてません」
「つまり、被害は、ないと」
「ええ、まあ被害という被害は、ないといえばないですが…」
「ないんですね?」
「ええ、はあ、ないです……」
「……まあ、実際に被害があった、ということであれば、これはもう我々としても対処するんですが、実質的な被害がない、ということであれば、なかなか、そうですね、被害がないということなら…」
警官はボールペンをいじりながら、何だか曖昧なことを言った。
「……それにですね、まあ、竹下通りの恐喝とかで被害に遭うのは、だいたいが若い人なんですよね、高校生とか中学生とか。あなたみたいな人がそういう恐喝に遭うというのは、ちょっと、ねえ……今までにそういうのは、聞いた事がないんで……」
交番のパイプ椅子は急速に居心地が悪くなり始めていた。義を通さんとわざわざ出向いてきた私が、遠回しに状況証拠を突きつけられている犯人のような心持ちになってきているのはどういうわけか。
警官はボールペンをいじりながら、私の顔を見て尋ねた。
「まあ、つまりそういう被害者は総じて若い人なんで……ところであなたは、おいくつなんですか?」
「三十です」 私は答えた。
「えッ、三十! あなた三十歳なんですか!」
警官は何故か非常に驚いた。
「サイトーくんサイトーくん! この人三十なんだって!」
警官は側にいた若い警官に、何だか嬉しそうな声で言った。
サイトーくんと呼ばれた若い警官は、「へーえ、三十!」といって「はっはっは」と快活に笑った。しょうがないので私も笑った。
「いやー、あなた三十には見えませんよ、若く見られるでしょう、若く!」
警官は嬉しそうにいった。
「はあ、まあ」
女性にとって、実年齢より若く見られることは嬉しいことかもしれない。だが男が若く見られても仕事上で軽んじられることが多く、特にメリットはない。若い男はなめられるのだ。自分の外見が急に恥ずかしいものに思えてくる。何故警官はことさらにそのことにこだわるのか。彼はさらに繰り返した。
「いや、ほんとに若いですよ、あなた……しかもそんなの着てるから余計ねえ、そういう上着、なんていうのそれ」
「ジージャンですが…」
「昨日もそれ、着てました?」
「着てました」
「あーッ。だからだ。だからですよう。そんなの着てたから、暗がりで余計に若く見られちゃったんだなあ! あなたみたいなねえ、大人が竹下通りで声かけられることって普通ないですから! ねえ、サイトーくん!」
警官は晴れ晴れとした顔で言った。サイトー巡査はまた「はっはっは!」と快活に笑った。私もへらへらと笑った。
「そうかそうかあ、間違えちゃったんだなあ、相手は」
警官はノートをぱたん、と閉じて私に笑顔を向けた。
「いやーいやいや、ほんとにね、じゃあ、これからは気をつけてくださいねえ。服も、そういうんじゃなくて、背広とか着てたらいいんじゃないですか、はっはっは!」
「そうすねはは」
「ではどうもわざわざありがとうございました」
押し出されるような格好で警官に見送られて、交番を出た。
表参道の歩道に立つと、今、自分が行くべき場所のまったくない、寄る辺ない身であることを急に悟った。私は何となく、ただ何となく歩き出し、たまたま見かけた回転寿司の店に吸い込まれるように入った。
紙のおしぼりで手を拭き、粉の茶を飲む。イカの皿を取ってほおばると、ふいに涙が目に滲んだ。言うまでもないことだが、わさびのせいである。わさびのせいなのである。
|