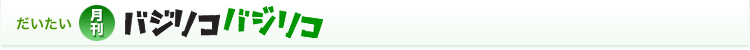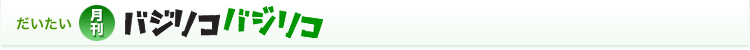タカサカさんと、そしてUFOサークルの皆さんと一緒にUFOを呼ぶのだ。遠くかすかなゴミのようなものでもなく、目の端をさっとかすめるだけでない、くっきりとした、どこからどう見ても疑いようもないUFOがしっかり、ばっちり、この目で見られるのだ。UFOサークルは以前にもUFOを呼び寄せた実績もあるという。疑いは、ない。
もっとも目撃例の多い、オレンジ色の小判型だろうか。小学生はニヤニヤしながら考えた。
それとも、球体型か。ソンブレロ型だと嬉しいな。小学生は電話機を置いた途端、タヌキの皮算用ならぬUFO算用を始めた。
まあ、ソンブレロでなくても土星型でもよしとしよう。アダムスキー型も悪くはないが、いまひとつ、有名になりすぎたきらいがある。まあ、本当にくるんだったら文句は言わないが、固く見積もっても小判型は来るよな。ちょっと平凡だけど、編隊で来てくれるのならかまわない。
…とか何とかいった想像を全部ぶっちぎって、いきなり巨大葉巻型母船が現れたりなんかしちゃったりなんかしちゃったりなんかしてェ!
はしゃぎのあまり、小学生の口調は思わず広川太一郎になるのだった。
小学生は学校でこのビッグ・ニュースを吹聴した。クラスの注目が一身に集められ、男子は羨み、女子は熱い視線を浴びせかけてくるはずであった。だが本物のUFOが現れるというのに、意外にも世間の風は冷たく、小学生の目算はあっさりと瓦解した。
「ハヤカワさー、ユーフォー呼ぶんだってよユーフォー」
みんながどっと笑った。小学生もすかさず笑った。卑屈な笑いだった。
「いやーUFO研究家なんていう変な人と知り合っちゃってえ、色々あって、まーちょっとつき合わなくちゃなんなくってさ」
そんな話はもはや誰も聞いておらず、話題は日本ハムの選手のホームランに移っていた。小学生は話の輪からはずれ、意味もなく教室の中をうろうろした。「卑怯」という画数の多い漢字が、頭のどこかに点滅していた。
所在なくなるという小学校教室でもっとも過酷な状況に陥らんとしていた小学生を救ったのは、級友のオビカワ君だった。彼は教室の隅で、小学生に熱心に問うた。
「ほんと? ほんとにユーフォー出んの? おれ、見たい。ユーフォー、見たい! なーおれも連れてってくれよー。ユーフォーサークル、オレもいきてーよー」
巨人ファンで、日頃はUFOのユの字にすら関心を示さないオビカワ君が、何故か熱心に私をかき口説いた。
小学生は自信を取り戻し、鷹揚に頷いた。
わかったわかった、オレからタカサカさんに話つけといてやるよ。大丈夫だってば。オレ、すごく仲いいし、それに人数が多いほど思念波も強くなるっていうしな。
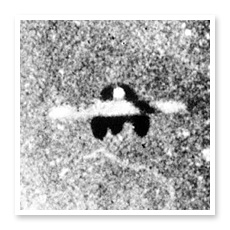
そして、期待のうちに、UFOを呼ぶ日がやってきた。
もう、日はとっぷりと暮れていた。いつもは、児童会館の屋上でやるというUFOコンタクトだったが、その日の集合場所は市内の空き地であった。二十人ほどが集まった。子どももいたが、大人もいた。
「金星のダニエルさん、応答願います…」
集まったメンバーは円陣を組み、手と手をつないで、ひたすら念じた。
仰ぎ見るのは、何ということもない、ありきたりの東京の夜空だった。だが、じっと目を凝らすと、その煤けた空の向こう側には、意外なほど多くの星が多く瞬いているのがわかる。
そして、目が慣れるに従い、そこは夜空、などという日常的なものとはほど遠い、暗く、底知れない、広大無辺の空間であることが徐々に認識されてきた。
無限というものの片鱗に触れたような恐ろしさ。呑みこまれ、いずことも知れず連れ去られたが最後、この懐かしい場所へは二度と帰れないのではないか。もう誰とも会えないのではないか。そんな童話じみた恐怖が、現実感を伴って胸を締めつける。
それは夜の海面、倦むことなくうねる暗い波間を見つめる時に感じる、ある種の郷愁と恐れ、そして畏怖の念にも似た感情だった。
だが、その畏怖すべき暗黒空間に、UFOサークルメンバーの思念、メッセージは清き白銀の光となって、駆け上がってゆくのだ。そう思うと、次の瞬間にも眩い光を放つ巨大UFOが眼前に現れるようにも思えた。また、瞬く星々の中に、UFOはすでに紛れており、何もかも承知の上、我々を黙って見守っているような気もした。我々はひたすら、念じた。大人も、子どもも真剣であった。どうぞ姿を見せてください、この空き地に降りたってください!
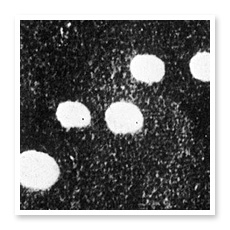
集まった人々は三々五々、散り始めていた。誰もが、首をさすったり頭を振ったりしていた。長い時間、メンバーは休憩もないまま空を仰ぎ見ていたのだ。
「ユーフォー、来なかったなー」
オビカワ君は伸びをして、「コキコキ」と頭を左右に振りながら言った。
「ん…」
小学生は咽の奥で曖昧な音声を発した。
「あーあ、こんなことならナイター見てればよかったなー」
オビカワ君はそう言いながら、一本足打法で素振りをした。小学生は、黙っているほかなかった。
「でもよー、次やったらきっと来るかもなー。あの研究者の人もそう言ってたもんな。次やる時があったらまた呼んでなー」
オビカワ君は自転車にまたがりながら、快活に言った。その言葉が彼の気遣いであることは、痛いほどわかった。
「うん、じゃなー」
小学生はオビカワ君に手を振りながら、「立場がない」という状況を、身をもって学習していた。
UFOは、来なかった。
よく考えたら当たり前だ。いきなり呼んですぐ来るなんて、池の鯉じゃあるまいし。小学生は前向きに考えた。
ちょっと虫が良すぎるよ。自分だって、こないだシマヅ君やシイキ君が遊びに来たとき、歯医者に行くからと断ってしまったじゃないか。小学生の自分にさえ、いろいろと用事というものがあるのだ。
UFOにだって、都合というものがあるのだろう。
「都合、つけてもらえないかしら」
そう言って、母はいやな笑いを浮かべ、ハンカチで口を押さえながら何度も頭を下げた。
「何度も、ほんとに悪いんですけど」
そういってまた頭を下げる。化粧の匂いが、かすかに鼻をついた。
「うちの人が、ああいうアレなもんですから…」
叔母は、かすかに眉をひそめたかに見えた。きっとそれは錯覚だったのだろう。隣室から戻ってきた叔母は微笑を浮かべて、紙幣をそっと滑らしてよこした。
「これ、裸で悪いけど」
二万円あった。母はそれを押し戴くように受け取った。
その日、母は突然「叔母さんとこいくから、あんたも来て」と小学生を親戚の叔母の家に連れてきたのだった。
小学生は、叔母の茹でたそうめんをずるずるとすすりながら、母の意図を計りかねていた。そして、親戚の家で食べる飯はどうしてこう咽につかえる感じがするのだろう、とも思った。
さりげなく席をはずし、窓から外を見上げる。UFOは、飛んでいなかった。地上でも、天空でも、いろいろと都合が悪いことは多いのだろう。
UFOノートの切り抜きと、目撃情報は増え続けていった。
しかし、それと同時に、心に不満がつのってきているのも、否めない事実であった。
これだけ、これだけ熱心にやっているのに、どうしてUFOはもっとこう、派手に、はっきりと、それと分かる形で姿を現さないのか。
小学生は、UFOノートに貼られた「UFOといえば、いえなもくない」といった程度の目撃情報を、だんだん恨みがましい目つきで眺めるようになっていた。そして、話すに足る目撃体験をした人を、激しく羨んだ。
特に妬ましかったのは、昭和47年、UFOと接触したという談話を発表した、四国は高知県の中学生だ。この少年たちは、近所の田んぼでUFOを発見、何とこれを「捕獲」することに成功したというのだ。
それは、形もサイズも帽子状の小型のものであった。形態からいって、あきらかに人工のものであった。
この少年たち、UFOの搭乗員と何らかの接触を試みたかというとさにあらず、中学男子本能丸出しに、ブロックをぶつけたり、隙間から水を流し込んだり、ドライバーでこじ開けようとしたりと、さんざん野蛮な振る舞いをした挙げ句、タンスの奥にしまい込んだのだという。
だがUFOは、何らかの超次元的な方法を用いてタンスを脱出、いつの間にか、田んぼに戻っているのだ。
何度も逃亡を繰り返す小型UFOを、彼らは飽きもせず何度も捕獲した。そして、さらに厳重に保管しようと、彼らはそのUFOをリュックに入れ、電気コードで腕にぐるぐる巻きにした上で、自転車に別の少年の家に運ぼうとした。
するとリュックの中のUFOはだしぬけに浮かび上がり、自転車もろとも少年を引き倒し、いずこともなく消えた、というのだ。
たわけどもがッ!
小学生は地団駄を踏んだ。UFOが、よりにもよって、こんな愚かな連中のところに現れるとは。
小型UFOは、きっと偵察用のもので母船からの電磁波によって操縦されていたのだろう。もしUFOが異星人の宇宙船であるとしたら、地球人の愚かで野蛮で様子は、きっとあまさず観察されたしまったに違いない。宇宙レベルの恥だ。
UFOよ、なぜ、ボクのところにはこないのか!
もし小型UFOとの接触に成功したら。小学生は熱心に夢想した。
とにかくまず、相手を知性体と認識し、こちらに悪意も何もないところを見せることが肝要だ。そしてその一方、ぬかりなく警察と科学研究所に連絡する。「科学研究所」というものがどこにあるのかは知らないが、どこかにあるのは間違いない。おっと、その前にタカサカさんにも知らせなきゃ。
そしてUFOの逃亡を防ぐには。小学生は技術的な諸問題をも検討し始める。
電磁波を遮断するには、鉛が有効なんだ。あらかじめ、大きめの鉛の箱を作っておいて、小型UFOを捕獲したら、即座にその中に入れてしまえばいい。鉛の箱は、釣りに使う鉛のオモリを熱して溶かし、板状に成形してから接合すればいい。しかし鉛というのは、どのくらいの熱で溶けるものなのだろうか。
予備実験が必要だ。
小学生は、つつじヶ丘駅前の釣具屋「丸井」に行って、ぶっこみ用オモリ20号を買ってきた。鯉釣り用に使う、鉛製のオモリである。柔らかそうな金属だ。簡単に溶けそうな気もする。
小学生はアパートの裏手で火を焚き、オモリを中にぶちこんだ。焼き芋とまったく同じ手法のそれは、実験というにはいささか杜撰に過ぎたかもしれない。オモリはちっとも溶けなかった。火力を強めようと、灯油を火につぎ足した。火は勢いよく燃え上がったが、そのうち、アパートの大家に見つかり、こっぴどく怒られた。
科学実験は大家のおかげで頓挫した、だが、まあいい。小型UFOの捕獲など、確率的にもまず起こりえないし、この四国のとんちき少年の事件は、非常に希な例だったのだろう。
父は、出がけに何か言った。よくは聞き取れなかったが、怒気を含んだそれは、「人の稼ぎで生きてやがるくせに」という風に聞こえた。ドアが叩きつけられる。母の顔は、能面のようだった。
♪ジャンピーング・フジーパーン
♪ジャンピーング・フジーパーン
♪イキイキ・フジーパン!
テレビでは、まん丸な顔のキャラクターが飛び跳ねる、脳天気なフジパンのCMが流れていた。このCM は何故かいつも二回繰り返されるのだ。小学生は、あのまん丸の動きは、テキサス州で目撃された球体型UFOに似ている、と思った。
母は、前掛けで顔を覆っている。小学生は考える。これだけ毎日UFOのことを考えているのだ。一回ぐらい、ただの一回ぐらい、こう、モノスゴイのが目の前に来てくれたっていいではないか。
自分だけがUFOのことを理解している。情熱をもっている。他の馬鹿な連中がUFOを目撃しているのは、何かの間違いだ。自分は選ばれた人間なのだ。UFOが明快に姿を現さないのは、何らかの意図、それも、こちらがその深い洞察と深謀に思わず頭を垂れるような、高尚な理由があるはずなのだ。
二間のアパートでは、逃げ場はない。丸めた母の背を見ながら、小学生は宇宙意思というものについて考えていた。家庭内温度はますます冷えてゆき、小学生のUFO熱はどんどん上がっていった。

同じクラスに、ムラニシさんという女子がいた。
クラスの男子は、何かというと、ムラニシさんのことをからかった。背が高く、活発だというただそれだけの理由で、男子は彼女に「原始人モコモコ」などというあだ名をつけ、「モッコモコー、モッコモコー!」と囃したてていた。
「うるさーい!」男子が騒ぎ始めると、彼女は元気良くキックをかました。「パンツ見えたパンツー!」男子はますます喜び、さらに大騒ぎした。
無論、その中には小学生もいた。ことUFOに関しては選民思想を持っていた小学生も、イタズラをしたり女子をからかったりすることにかけては、他のバカ男子と何一つ変わらないのだった。
放課後、だったと思う。
帰り支度をぐずぐずとやっていたせいだろう。教室に、小学生は一人だった。
教室を出ようとした時に、ふと後ろの棚に封筒が置いてあるのが目に入った。ムラニシさんが置いた封筒だ。封筒の表には、こう書かれていた。
おうちで写した
ユーホーちゃん
みんな みてネ・
ムラニシ
子どもながらに、苦笑した。
ばっかだなあモコモコは。「ユーフォー」ていうだけでも間違ってるのに、「ユーホー」だってやがる。頭悪いよまったく。そもそもUFOの発音は「ユー・エフ・オー」が正しいのであり、その意味は、あんあいでんてぃふぁいど・ふらいんぐ・おぶじぇくと…。
私は、とりあえず見ておこうか、というぐらいの気分で、封筒から写真を取り出した。
はっとして、目を伏せた。
いやなものを、見てしまった気がした。鼻の奥がツンとし、心臓がひとつ、どーん、と鳴った。
それを直視するのには、何故かためらわれた。だが、小学生はおそるおそる、写真を見直した。
それは、異様な写真であった。
おそらく、ムラニシさんの家の庭から撮ったものだろう。カメラはほぼ真上を向いており、家の軒先と、柿か何かの木が映っている。写真のほとんど全面を占めるのは、曇り気味の、何ということもない空だった。
だが、その空には異様なものが浮いていた。
真っ黒だった。紡錘形の両端を切り落としたような、細長い形をしており、かなりの大きさがあるように思われた。
それは、1967年7月3日、アメリカのロードアイランドでジョセフ・セリア氏が撮影した葉巻型UFOとまったく同じ形をしていた。
この葉巻型UFOには、射出口のようなものが確認でき、そこから小型円盤が飛び出したという。そしてこの写真の葉巻型UFOにも、その射出口らしいものが見受けられるのだ。
本や、雑誌に載っているUFO写真は、多くの場合モノクロで、粒子は粗く、コントラストも高すぎ、構図も何だか出来すぎていて、一見、イラストだか写真だか判別がつかないようなものが多かった。そして、小学生はUFO写真とは、そういうものなのだろうと思っていた。
だが、この写真は違う。
まったく、普通の写真なのだ。いかにも素人が空に向けてパチリとやったような、無造作な構図。ごく普通の色合いの、ごく普通のサービスプリント。
その、あまりにも普通で日常的な写真は、そこに映し出されている物体の異様さを、際だたせていた。
封筒には三枚の写真が入っていた。そのいずれもに、葉巻型のその異様な物体は、くっきりと映っていた。私はその写真を穴の空くほど見つめた。
家に帰った。
机の脇に積んであるUFOノートが目に入った。
それは、色あせて見えるどころか、限りなく恥ずかしく、みっともないものに思えた。
モコモコ風情にすら。
しかも、葉巻型。
黒いものが沸き立っていた。それは徐々に数を増し、やがて小学生の胸の中でぐるぐると回り始め、いつ果てるともない、楕円軌道を描いた。
その日を境として、まるで憑き物が落ちたかのように、小学生はUFOのことを口にしなくなった。
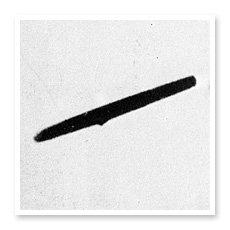
数年が、経った。家は隣町に引っ越していた。
アパートはさらに狭くなっていた。そこには玄関の上がり口すらなく、ドアを開けるともう生活臭の漂う台所が丸見えだった。ブロック塀には大きな木札が下がり、そこには下手くそな字で「コーポ田中」と大書してあった。
その頃すでに退職していた父は、朝から晩まで寝床からテレビの時代劇を見ていた。小学生は中学生となっており、部活が終わったあとも、なるべく家に帰るのを遅くするため、あちこちをふらふらと歩き回った。
帰り道だった。家の前でふと空に目をやった。雲間が明るく輝いている。
飛行機だろう、と思った。
しかし、どうもおかしい。その光はまったく動かない。動かない上に、どんどんその光度を増してくるのだ。眩しいほどである。
飛行機や気球や無論のこと、人工衛星、流星、金星、レンズ雲や渦巻雲、放電現象、光の屈折、ラジコンから雲に映ったヘッドライトまで、UFOと見間違いやすいものはいくらでもある。
光がそのどれとも違っていることは、元UFOマニアの中学生には、すぐわかった。
輝いている。雲間に水銀灯を点灯したようだ。ヘリコプターが至近距離にいるのかとも思った。だがあたりはまったく無音で、虫の声がかすかに聞こえるだけだ。太陽は西に沈みかけている。光があるのは東の空だ。
「あ…あ?」
呆けたようにその光を見ていた中学生の胸に、いつぞやの情熱がふいに、蘇った。急に我に返ったようだった。現認者を。誰か、現認者を。
中学生は家のドアを勢いよく開け、狭い台所にいる母に行った。母は眉根にしわを寄せ、背を丸くして鍋の前に立っていた。老婆のようだった。
「ちょっ、ちょっと」
「何」
「いいからちょっと、とにかくちょっと」
「今、ほうれん草煮てるんだけど…」
「ほうれん草いいから、とにかく」
母を引っ張り出すと、中学生は空の一角を指さし、「あれ、あれ」と言った。
「あらやだ」
母の目が空の一点を凝視した。眉根を寄せ、両手で口をおさえ、汚らしいものでも見るような目つきで光を見つめている。
「やだ何あれ」母が言った。
「UFOじゃないかと思うんだけど…」私は光を凝視しながら言った。母は何も答えず、ただただ、眉根にしわを寄せてその光を見上げるばかりだった。
たっぷり、三分ほどは見つめていたと思う。その不思議な光は、白熱するかのようにその光を強めていったが、やがて弱くなっていき、ゆっくりと遠ざかるように小さくなると、ふいに消えた。
遠くに、車の音がする。虫の声がやたらと耳についた。
「ふうーん…」
母はそれだけ言うと、前掛けでちょっと手をふき、鍋に戻っていった。中学生はしばらく光の消えた空を見つめていた。
その翌日から中学生の胸のうちに、あの過ぎ去った日の情熱、UFOに対する熱い熱い思いが復活した…かと思いきや、このUFO目撃はそれきりのことで終わってしまった。
父と母は、もう本当に駄目なようであった。離婚、という二文字が中学生の胸に重く居座っていた。その後、中学生がこの不思議な光のことを思い出すことは、なかった。
|