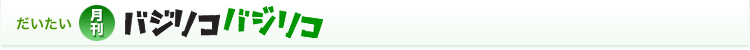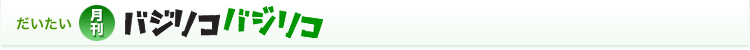生きていた。生き延びてくれた。
ぎくしゃくした歩き方ではあるが、すでに松葉杖は無く、相変わらず長い前髪から半分覗いた顔も、血色がいい。明子は身震いせんばかりの、万感の想いをもって相手の姿を眺めていた。
しかし一方、八重子の表情は浮かない。ちらちらとこちらを観察し、小首をかしげていたかと思えば、
「お加減は如何で御座いましょう。妾は、東京探偵社のお手伝いをさせていただいております者で――」と、なんの心算か他人行儀な自己紹介を始めた。
明子は訝って、「ええ、きっと今も唐草先生から、色々にご指示を受けていらっしゃるのでしょう? そう承知していますよ、八重子さん」
女は顔をあげた。明子に近づき、その顔を正面からまじまじと見つめたのち、「岡田先生。岡田先生なのですね」
素ッ頓狂な問いに失笑しかけた明子だったが、直後、はっと事態の深刻さに気付いて、「昨日までの私は、貴方が誰か――自分が何者かも分からないほど、意識朦朧としていたのね。そうなのね?」
すると八重子は小さくかぶりを振って、「いいえ、決して朦朧というのでは――」
「遠慮をしなくていいの。そういう気遣いはむしろ迷惑です。取り乱したりはしませんから、どうか本当のところを話して頂戴。仲間じゃないの」
八重子は返答に困った風情で、きらきらした左眼を揺らしている。暫くそうしたのち、意を決したように、「掛けさせていただいても宜しいですか」
「御免なさい、気がまわらなくって。どうぞ坐って頂戴」
女は一礼して、寝台の傍らの椅子に腰をおろした。
唐草先生からは、余計なことは喋らないようにと、強く云い含められております。その命に背く覚悟で、共に死線を彷徨った岡田先生には、妾が存じあげている、ありのままをお話ししようと思います。
だけど――どこからどう、ご説明すれば宜しいのでしょうか。そうでなくても妾は口下手ですから、きっと甚だしく要領を得ないことでしょう。だからせめて率直に、思い返されるがままにお話しします。
先生がようやっとお目覚めになったのは、妾たちが山崎邸に潜入したあの晩――それは憶えていらっしゃいますよね? そうですか。安心致しました――あの晩から数えて二週め、まだ中野の病院にいらっしゃるときでした。
ちょうど唐草先生がお見舞にいらして、妾の様子を御覧になっているときで、すると病室に看護婦が入ってきて、
「お目覚めになりました」と云います。
「どちらが」と先生は問い返されました。
「断髪のお嬢さんです」と看護婦が答えました。
唐草先生はすぐさま部屋から出ていかれましたが、妾も岡田先生とお話をしたくて、まだ身を起こすのがやっとだったんですけど、寝台を下りたんです。看護婦が引き留めようとするのを無視して、廊下へ出ようとしました。でも撃たれた脚に力が入らなくって、けっきょく壁に凭れたまま、一歩も動けなくなってしまいました。
看護婦も外に出ていってしまったので、すっかり見放されたような気でおりましたら、やがて彼女が松葉杖を持って戻ってきて、妾の脇の下に差してくれました。
「使い方は知ってる?」
知りはしませんでしたが、ご存知のように元々軽業師で御座いますから、杖に体重を預けているだけで、重心をどう動かせば前に進めるかは分かりました。
そうして生まれて初めて松葉杖を突いて、妾はなんとか先生の病室まで辿り着くことができたんです。でも中に入ることは叶いませんでした。若い女の方の――そのときは岡田先生だと思いました――叫び声が廊下にまで響いてきました。殺される、殺される、と仰有っていました。
妾に足並みを揃えてくれていた看護婦が、慌てて病室に飛び込んでいきました。大丈夫だ、心配なく、という唐草先生の声も聞えましたが、叫び声は激しさを増す一方です。別の看護婦が飛び出してきて廊下を走り去っていきました。ドアが開きっぱなしになっていたので覗き込みますと、ちょうど唐草先生と目が合いました。
「戻っていなさい」と厳しい調子で命じられました。
さっきの看護婦がお医者を連れて戻ってきて、ドアが閉じられました。唐草先生のお言葉に逆らって待っていたところで。入れていただけるような状況とは思えませんでした。妾は諦めて、また松葉杖を突いて自分の部屋へと戻ったんです。
その日はそれっきりでした。暫くして妾の部屋においでになった唐草先生に、
「岡田先生は」とお尋ねしましたが、
「君はなにも心配しなくていい」と仰有るばかりでした。
唐草先生は翌日も朝から病院にいらっしゃいましたが、妾のことなんかより岡田先生がご心配でいらしたのは間違いありません。先生がまだお休みになっていたものだから、仕方なく妾の病室を訪ねてこられたようです。これといってお話がある訳でもなく、
「本を読んでいいかな」と仰有って、椅子の上で外国語のご本を開いておいででした。
「なんのご本ですか」と妾が問うと、
「人の心の不思議を説いた本だよ」とのお答えでした。
看護婦が入ってきて、前日と同じように、
「お目覚めです」と告げました。
それからも、また前日の再現のようでした。唐草先生は急いで出ていかれ、妾も松葉杖でそれを追いましたが、また病室には入れませんでした。前日と同じく女の方の大声が聞えました。ただ、今度の声はより落ち着いていると申しますか、本来の先生のお声に近い感じでしたので、妾は、おやこちらが岡田先生のお声で、昨日のは看護婦だったのかしら、と思いました。
でも耳を澄ませているうち、なにがなんだか分からなくなってまいりました。と申しますのも叫ばれている内容が、育ちが良いとは云えない妾でさえ赤面してしまうような、ひどく卑猥なものだったからです。妾はその場に居てはならないような気がしまして、みずから部屋に戻りました。
翌日、やっと先生のお姿を拝見することができました。また同じように唐草先生のあとを追って病室の前に参りましたら、今度は静かで、やがて気配を察した唐草先生がドアをお開けになりました。小さく頷いて、入っても構わない、という合図をなさいました。
「その女は?」と寝台の上から問われましたのは、他でもない岡田先生です。
ですけど、なにか変なのです。妾に対する素ッ気なさを差し引いても、奇妙でした。お貌立ちも髪型もまさしく先生でいらっしゃいながら、別人のようにその――ええ、はっきりと申し上げます――陰険な雰囲気をまとっておいでなのです。先生とはまったく違う暗く厳しい環境でお育ちになった、双児のお姉さまか妹さんといった風情でした。
「さっき岡田明子くんのことならなんでも知っていると仰有ったけれど、彼女のことは分からないのかね」寝台に向かって唐草先生が問われました。
「知ってるわ。役立たずの援軍。なんの用かと訊いているの」
べつに用向きは無いのですから、妾は黙って俯いているほかありませんでした。そこで考えておりましたのは、態度や雰囲気が違おうとも、この方は岡田先生に違いないということでした。ある経験からの類推です。その経験とは――すみません、やはり妾は口下手で、話が無意味に前後してしまいました。これはあとでお話しします。
「自分を心配してくれる人に対して、そういう云いようは感心しないね」と唐草先生が助け船を出してくださいました。
ふん、と岡田先生は鼻でお笑いになり、「なぜあの晩、唐草大先生は骨惜しみをして、みずから山崎邸に乗り込もうとなさんなかったのかしら」
「貴方がそう望んだのだ」
「私ではなくて明子が、よ。お蔭でこっちは悲惨な状況だわ」
「こっちというのは」
「臆病な女工のお春も、酔いどれダンサーの昴も、おおかた山崎に呑み込まれてしまった。ほかの薄っぺらな人格たちも、早晩次々と喰われていって、残るのは私と、せいぜい明夫だけでしょうね」
「山崎の怨念は、そんなにも強靭なのかい」
「怨念ね――まあ怨念だか亡霊だか知りませんけど、本当の問題は山崎よりも、明子の心の闇の深さなのよ。子供の頃からひたすら清純を、廉潔を強いられてきた明子は、自分のなかの堕落や腐敗を、お春や昴や、不良娘や、無学な長屋の女将といった、架空の存在へと切り分けてきた。それが今や、山崎という悪徳の象徴的存在に統合されつつあるの。唐草先生の失策のお蔭で」
「しかし貴方――ええと、なんとお呼びすればよかろうね」
「だから暗澹【あんたん】と名乗ったじゃない。暗澹たる先行きの暗澹。お気に召さなければ安本丹【あんぽんたん】でも木村屋の餡麪包【あんパン】でも結構ですけど、明子の深層意識は私をそう呼んでいる――暗澹と」
「ではそう呼ぼう。暗澹さんと明夫くんは、山崎なんか平ちゃらなんだね?」
「平ちゃらではないわ。明子の実像に近いから、そう簡単には統合されないだろうと期待しているだけよ」
「そうなのか。しかし同性の貴方はともかくとして、異性であり、さして思慮深いとも僕には思えない明夫くんを、なぜそのように思われるのかな」
岡田先生――いえ、今はただ暗澹と呼ばせていただきます。いくらお姿が同じとは云え、先生の同格として語り続けることが、やっぱり妾にはできそうもありません――暗澹は、唐草先生を愚弄するようにげらげらと笑って、「私が明子の裏返しだとしたら、明夫はただ明子を逆様にしただけ。額縁ごとひっくり返せば、まったく同じ絵だわ。気付かなかったの」
「気付いていたよ。貴方の所見を聞きたかっただけだ」
「明子や明夫のことで私を試そうだなんて、いい度胸をしているわ。ご感想は?」
「冷静だし客観的だね、もしかすると明子くん以上に。しかし暗澹さんには、自分もまた明子くんによって仮想され、音無教授によって引き出された、便宜上のペルソナに過ぎないとの自覚がある――明子くんそのものではなくて。そうなんだね?」
音無教授というのが何処のどなたか、また便宜上のなにやらというのも妾には意味が分かりませんでしたが、それまで聞いていた遣取りのうち、この唐草先生の問掛けが、不可解だったにも拘わらずいちばん印象に残っています。暗澹が、少々傷ついたような表情を覗かせたからかもしれません。
「私は暗澹。明子ではないわ」
「しかし貴方のこれまでの物言いは、自分が明子くんと同等か、より上位の存在であるかのようだ」
「明子の人生が一冊の本だとしたら、私はその作者。明子は幼い頃から私を想定して、自分にとって不都合な現実の責めは、ぜんぶ私に負わせてきた。私は明子から生まれたけれど、明子は私を、自分を生んだ存在として設定している。鶏と卵なのよ」
「成程。そういえば仮想人格のうちに、作家もいると聞いたことがある。それが貴方か」
「明子はそう片付けているようね。私が音無先生の前で韜晦していた所為もあるけれど、明子は私の正体に薄々気付きながら、作家なんて捜査の役に立ちはしないと決めつけて、断固、呼び出すことは拒んできた。呼び出されたって私も困りますけど。社会正義に奉仕するだなんて真ッ平だもの」
「だが、これからは違うんだろう?」
「こうして改めて眺めてみると、唐草先生ってなかなかの二枚目ね。もし先生に電源を入れられたなら、また出てきちゃうかも。でもそれ以外は御免だわ。だって私、怠惰に眠りこけているのがいちばん好きなの。明子が覚醒するまでまだ暫くかかりそうだけど、またよっぽどの用向きが出来でもしないかぎり、私が起き出してくることはないでしょう。せいぜいお春や昴たちの、断末魔の叫びに付き合ってあげて頂戴」
「今は余程の緊急事態――そういうことか」
すると暗澹は、薄ら笑いを浮かべたままではありましたが、小さく吐息して、「明子は弱い。それを自分では認められない程に、弱いの。明夫と私は、彼女の最後の牙城。もし私たちが山崎に負け、喰らい尽くされてしまったら、明子の運命は二つに一つ。山崎の悪徳に染まるか、狂うか。そのときはどうか、先生の手で明子を殺してあげて頂戴。これが私の用向き」
唐草先生が、どのようお答えになったかは――そればかりは、妾の口からは申せません。
以後も暗澹は、唐草先生に秋波を送りながら戯れ言をかさねていましたが、不意に、眠くなった、と云って横になり、目を閉じました。以来、妾は一度も暗澹とは接しておりません。唐草先生については存じません。
先生のなかの他の人々とは、何度も接してきました。
例えばお春。いつも気が動転している小娘で、きゃあきゃあとよく大声で叫びます。妾のこともどこか怖がっているようです。この療養所に移ってからは殆ど現れませんので、暗澹が云っていたとおり、山崎の亡霊に食べられてしまったのではないかと、心配です。
ダンサーの昴とも、ここ二週間ばかりご無沙汰です。二日めに現れたのは彼女だったと、あとで分かりました。いつも酔ッ払っているという気でいて些末を気にしませんし、下品な言葉遣いさえ我慢していれば話の分かる女でもありますから、もしやお春と同じく――という事情でしたら、とても残念です。
朝子というフラッパーは、そのじつ暢気で世間知らずのお嬢さんです。自分に悪い事など起きはしないと固く信じて、厭なことはぜんぶ夢として片付けてしまいます。だからある意味で扱いやすいのですが、話題といったら流行りの映画やジャズや洋服のことばかりなので、妾は話を合わせるのに一苦労です。
長屋の女将さんは千景さんといって、妾にはこの人が、いちばん普通と感じられます。ほかの女たちもめいめい勝手に、自分がなぜ病院や療養所に居るのかを想像し、その物語を信じているのですが、千景さんは自分が暴漢に襲われたのだと思いこんでいます。頭を強く殴られて、だからおかしな夢ばかりみるのだと納得しています。妾のことは同じ事件で巻添えをくった気の毒な女だと思っていて、逆に身体を心配してくれます。
明夫さん――で御座いますか。
ええ、もちろん存じ上げています。
いいえ、中野の病院内や、この療養所では一度も。
暗澹を、やはり岡田先生であると信じられたのは、すでに明夫さんを存じ上げていたからです。先程申し上げた経験というのはそれです。ええ、もちろん明夫さんには驚きました。これは死に際の夢か幻に違いないと思いましたくらいです。
だけどそのあと暗澹や、お春や昴や朝子や千景さんと接してきた今は、なんとなくでは御座いますが、ご事情が察せられるのです。きっと岡田先生は、妾ども凡人には想像もつかぬかたちで、たくさんの人生を生きておいでなのでしょう。
山崎から麻薬を注射された先生は、がくりと力を失って、椅子に腰を落とされました。
悪事に酔い痴れている山崎は、そして運転手も支那人たちも、引き攣れたような笑いをあげました。妾は一味が憎くて堪らず、また儘ならない我が身が情けなく、その場で憤死してしまうかと思った程です。
だけど、やがて気付いたのです。地べたに這いつくばっている妾の位置からだけは、見えたのです――先生が、くわと目を見開かれているのが。
次の瞬間には行動を起こしておいででした。まさに妾が瞬きをしているあいだに、立ち上がり、椅子の背を掴み、逆さに振り上げて、余所を向いていた運転手の頭めがけて振り下ろされたのです。椅子は衝撃でばらばらに壊れ、運転手は、根元を伐られた大木みたいに、山崎の方へと倒れていきました。
山崎は後退りながらピストルを取り出しましたが、地面のがらくたを踏んで転び、誤って発射された弾丸が、支那人の一人に当たりました。頭に当たって、この男は即死しました。
支那人たちは大騒ぎを始めて、屈強そうな一人が、支那語で抗議しながら山崎に詰め寄りました。山崎はその男も撃って、殺してしまいました。残った支那人たちは、先を争って蔵から逃げ出していきました。
そうこうしているあいだに、先生は妾が投げた短剣を拾い、構えておいででした。しかし山崎も立ち上がって体勢を整えました。銃口は先生へと向いています。
「瑛子さんを返してもらうよ」と先生が仰有いました。
「貴様は――」と山崎が愕然として呟きます。
直後、先生は短剣を手裏剣のように打たれ、同時に銃声が響きわたりました。
残響がおさまっても、先生は二本の脚で力強く立っておいででした。驚きが、山崎の手許を狂わせたのです。先生のお声が、まるきり男性のものに変わっておいでだったから。
それどころか妾の目には――すでに大量の血を失って霞みかけた目に、では御座いましたが――お姿も、立派な紳士そのものでした。
山崎はあやつり手を失った木偶よろしく、その場に崩れ落ちていました。先生の打たれた短剣が、みごと男の喉笛を貫いたのです。虚空を睨みつけたまま事切れている悪漢を、男性のようになられた先生――今にして思えば明夫さん――は、しばし呆然として見下ろしていらっしゃいました。
ええ、山崎は死んだのです。
完全な正当防衛であるから、なんら心配には及ばないと唐草先生は仰有っています。また運転手は気を失っていただけで、頭に瘤が出来ていた程度とのこと。なんたる石頭でしょうね。
明夫さんが妾に視線を向け、
「瑛子さんは何処」と尋ねられます。
「階上【うえ】です」とお答えしました。
明夫さんは段梯子を駆け上がり、やがて敷布でくるんだ瑛子さんを肩に担いで下りてこられました。瑛子さんは眠っているようにも、また亡骸のようにも見えました。明夫さんはその段になって初めて、妾の下の血溜まりに気付かれたようです。
「君、大変な出血じゃないか。止血をしないと」いったん瑛子さんを下ろされ、敷布の端を引き裂いて、「お嬢さん、裾を捲らせてもらうよ」
妾は頷き、身をお任せしました。失礼、と明夫さんは跪かれ、妾の着物も腰巻きも捲り上げると、脚の付根を強く縛って血を止めてくださいました。
「ふたりとも、一刻も早く医者に診せなければ。ねえ君、僕は自動車で来たんだろうか」
「はい。でもだいぶ離れた場所に」
「そうだ、山崎は立派な自家用車を――」明夫さんはのびている運転手のポケットをまさぐると、大きな銀色の鍵を見つけ、取り出されました。「これだ。うん、ロールスロイスとある」
それから妾たちを山崎の豪奢な自動車へと運び込み、全速力で運転なさって、中野の大きな病院へと運んでくださったのです。たくさんの血を失っている妾は、道中眠くてなりませんでしたが、
「眠らないほうがいい。意識をしっかりと保っていなさい」と仰有るので、唇を噛みしめて我慢していました。
病院の前に自動車を横付けした明夫さんは、クラクションを何度も高らかに鳴らしました。応じて、あちこちの窓に灯りが点ります。明夫さんはほっとしたように微笑して、後ろの座席を見返し、横たわっている瑛子さんを見つめておいででした。やがて助手席の妾に仰有いました。
「あの人が目覚めたとき、僕はもう日本には居ないだろう。いつ戻ってこられるかも分からないんだ。だから君の口から、こう伝えてくれないだろうか、明夫は上海で元気にやっている」
「分かりました」
「幸せを祈っている、と」
「はい」
病院から出てきた人たちが自動車を取り巻きはじめたとき、押し寄せてきた安堵で、妾の瞼はいよいよ重くなりました。だけどそのとき、運転席にいらっしゃるのが明夫という男性ではあり得ず、本当は岡田明子先生である筈で、また山崎の手で南米の秘薬を注射されたそのお身体が、尋常である訳はないと思い出したのです。
そう病院の人たちに説明しようと、運転席を振り返りますと、先生はいつしか座席に身を沈め、穏やかに眠っておいででした。美しい女性の横顔がそこにありました。
(この章続く) |
|